不動産の売買契約では「契約した物」と実際に引き渡された物が違う、あるいは品質に問題があるケースが発生することがあります。
これを法律上は「契約不適合」と呼びます。
今回は、この契約不適合に関して民法で定められた通知義務と、買主が取れる手続きについて学んでいきましょう。
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 不動産取引における契約不適合とはどういう状態を指すのか?
→契約書で約束した内容と実際に引き渡された不動産が一致していない状態をいいます。 - 契約不適合責任の追及に期間が設けられているのはなぜか?
→法律が 取引の安全と公平さ を守るためです。 - 追及期間が1年である理由は?
→多くの不具合は 引き渡しから1年以内に生活していれば発見できるものだからです。
📘 今回の分野:不動産/不動産取引

今回は不動産取引に関する法律についての範囲を学びます。
❓️ 問題文の紹介
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物の種類や品質について不適合がある場合、買主は、不適合を知ったときから2年以内に通知をしないと、不適合を理由とする履行の追完請求等をすることができない。
◯か✘か?
問題文を読むと、引っ掛けてきそうなポイントはやはり数字ですよね。
「2年以内」という期間が正しいかどうか。
期間を問われる問題は山のようにあるので、しっかりその期間の意図や背景をイメージできるようにしておきたいです。
そうすれば、正答率は上がると思います。
正解と解説を見ていきましょう。
✅ 正解と解説の要点

民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物の種類や品質について不適合がある場合、買主は、不適合を知ったときから2年以内に通知をしないと、不適合を理由とする履行の追完請求等をすることができない。
◯か✘か?
→正解:✘
正解は✘でした。
問題文中で誤っている箇所は、やはり「2年以内」の期間でした。

正しい期間はどれだけなのか、ポイント解説を見ていきましょう。
✅️ポイント解説
- 改正民法(2020年4月施行)では、買主は目的物の不適合を発見した場合、原則として 「知ったときから1年以内」 に売主へ通知しなければなりません。
- この期間を過ぎると、追完請求(修理や交換)、代金減額請求、損害賠償請求などの権利を主張できなくなります。
- 売主が不適合を知っていながら黙っていた場合には、この通知期間の制限は適用されません。
🔍 深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 不動産取引における契約不適合とはどういう状態を指すのか?
→契約書で約束した内容と実際に引き渡された不動産が一致していない状態をいいます。 - 契約不適合責任の追及に期間が設けられているのはなぜか?
→法律が 取引の安全と公平さ を守るためです。 - 追及期間が1年である理由は?
→多くの不具合は 引き渡しから1年以内に生活していれば発見できるものだからです。
不動産取引における契約不適合とはどういう状態を指すのか?

不動産売買で「契約不適合」とは、契約書で約束した内容と実際に引き渡された不動産が一致していない状態をいいます。
言い換えると、
- 契約で「こういう家(土地)を売ります」と約束したのに
- 実際に引き渡されたものが、その約束と違っていた
このとき「契約不適合」が発生します。
契約不適合の具体例
- 種類の不適合
例:契約書では「宅地」として売買契約したのに、実際は農地だった。 - 品質の不適合
例:新築と聞いて買ったのに、実際にはリフォーム済みの中古住宅だった。
例:雨漏りしないはずの家なのに、天井から水が漏れてきた。 - 数量の不適合
例:土地を「100㎡」と約束していたのに、実際に測量したら「90㎡」しかなかった。
なぜ重要なのか?
買主は大きなお金を払うのに、契約どおりの不動産が手に入らないと大問題です。

一方で売主も、責任をどこまで負うのかがルールで決まっていないと不安ですよね。
そこで民法は、契約不適合が起きたときに買主が取れる手段(追完請求・代金減額請求・損害賠償請求など)や、通知義務の期限(原則1年以内)を定めているのです。
契約不適合のポイントまとめ
- 契約不適合とは「約束した内容と違う不動産が引き渡されること」。
- 種類・品質・数量の3つの観点で問題があれば「不適合」とされます。
- 民法で、買主がとれる救済手段や通知期限が定められています。
契約不適合責任の追及に期間が設けられているのはなぜか?

「契約不適合責任の追及(買主が売主に責任を問える期間)」に期限があるのは、法律が 取引の安全と公平さ を守るためです。順を追って説明します。
取引に終わりをつくるため
もし買主が何年経っても「やっぱり不具合があった!」と主張できると、売主はずっと不安を抱え続けることになります。
- 10年前に売った家で「雨漏りがある」と言われたら?
- 売主としては「いつまで責任を負わされるの?」と安心して生活できません。
そこで法律は「一定期間を過ぎたら責任を問えない」として、取引に区切りをつける仕組みにしているのです。
早期に問題解決を促すため
不動産の欠陥や不具合は、早く対応するほど修繕もしやすいし、証拠も残っています。
逆に長く放置すると、
- 欠陥の原因は売主の責任なのか?
- それとも買主が使い方を誤ったのか?

区別が難しくなりますよね。
だから「発見から1年以内に通知してね」というルールを設けて、早めに動いてくださいねと促しているのです。
売主と買主のバランスを保つため
- 買主の立場:大金を払っているので、不良品(不適合物)を掴まされたら救済を受けたい。
- 売主の立場:売却後ずっと責任を負わされるのは酷すぎる。
この2つを調整するために「発見から1年以内」という期間が設けられています。
追求期間が設けられている理由_まとめ
契約不適合責任の追求に期間がある理由は――
- 売主の負担をいつまでも続けないようにするため(取引の安全)。
- 欠陥の原因をはっきりさせるため(証拠保全)。
- 双方の立場のバランスをとるため。

「買主も早めに動く責任がある」という考え方です。
追及期間が1年である理由は?

不動産取引の性質に合わせた「ちょうど良い期間」だから
不動産は高額な財産であり、売買後に隠れた欠陥(雨漏り・シロアリ・地盤の問題など)が発覚することもあります。
ただし、多くの不具合は 引き渡しから1年以内に生活していれば発見できる ものです。
つまり「欠陥を見つけるには十分」「売主が責任を負い続けないためにも区切りが必要」という両方のバランスをとった期間が1年なのです。
証拠の確保が可能な現実的な期間だから
時間が経つと欠陥の原因が
- もともと建物にあったものなのか
- それとも買主の使い方のせいなのか
区別が難しくなります。
例えば10年後に「雨漏りがある」と言われても、
・建物の老朽化
・台風や地震など外部要因
・買主の管理不足
の可能性も出てきます。
1年なら「売主の責任かどうか」をまだ判断しやすく、紛争を防ぎやすい 期間といえます。
売主と買主の利益を調整した妥協点だから
- 買主の立場:せっかく買った不動産が契約内容と違えば、救済を受けたい。
- 売主の立場:引き渡し後も長期間ずっと責任を負うのは負担が重すぎる。

この両方を考慮して「原則1年」としています。
ただし、合意によって2年に延ばすことは可能ですし、売主が知っていて黙っていた場合には制限されません。
追及期間が1年である理由まとめ
契約不適合責任の追及期間が 1年とされている理由 は、
- 欠陥は通常1年以内に発見できるから。
- 証拠を確保して責任の所在を判断できる現実的な期間だから。
- 売主・買主双方のバランスをとった妥協点だから。

「発見から1年以内」というルールは、不動産取引に安心と公平さを与えるための仕組みなのです。
まとめ・今回の学び
- 不動産取引における契約不適合とはどういう状態を指すのか?
→契約書で約束した内容と実際に引き渡された不動産が一致していない状態をいいます。
→種類・品質・数量の3つの観点で問題があれば「不適合」とされます。 - 契約不適合責任の追及に期間が設けられているのはなぜか?
→法律が 取引の安全と公平さ を守るためです。
→買主も早めに動く責任があります。 - 追及期間が1年である理由は?
→多くの不具合は 引き渡しから1年以内に生活していれば発見できるものだからです。
→不動産取引に安心と公平さを与えるための仕組みのひとつです。
不動産売買についての内容をまとめました。
数字だけで覚えるのと、その数字の背景や意図とともに覚えるのでは理解度が全く違います。
忘れてしまっても、ここに書いてありますので、必要に応じて見に来てくださいね。
次回予告:借地借家法について
次回は 借地借家法 からの出題です。
定期建物賃貸借契約(いわゆる定期借家契約)は、更新がなく、期間が満了すれば契約が終了するのが原則です。
ただし、期間が1年以上の契約については、賃貸人(貸す側)が「契約が終わりますよ」という通知を、一定の時期に賃借人(借りる側)へ行わなければ、終了を主張できないルールになっています。
ではその通知は、期間満了の1年前から 【何ヶ月前】まで の間に行う必要があるのでしょうか?
試験でもよく狙われるポイントなので、しっかり確認していきましょう!



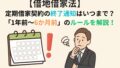
コメント