賃貸借契約のルールは普段の生活ではあまり意識しませんが、試験では細かい条文が問われます。
特に「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」は更新がない特殊な契約形態です。
今回の問題では「更新拒絶に正当事由が必要かどうか」がテーマになっています。
実生活でも不動産の賃貸を考えるときに役立つ知識なので、一緒に整理していきましょう。
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 借家権とはなにか?
→「大家さん(貸主)と借りる人(借主)の力関係を公平にするためのルール」です。 - 定期借家権とはなにか?
→期間をあらかじめ定めて、更新がない借家権のことです。 - 普通借家権と定期借家権の違いを比較
→どちらも「建物を借りる権利」ですが、法律上の扱いが大きく違います。
📘 今回の分野:不動産/不動産に関する法令

今回学ぶ範囲は、不動産分野の借地借家法に関する内容です。
借地借家法には、普通借家権と定期借家権があります。
特に今回は定期借家権の内容について詳しく解説していきたいと思います。
❓️ 問題文の紹介
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
◯か✘か?
問題文を読み替えると、
貸主側に正当な事由がある場合 → 貸主は契約の更新を拒むことができる。
ということでしょうか?
なにか、もっともらしい問題文ですね。
なので、正しい問題文だと思い、◯を選択しました。

でも、記事にしているということは・・・そういうことです‼️
✅ 正解と解説の要点

借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
◯か✘か?
正解:✘
正解は✘(誤り)でした。
✘:正当な事由がないと拒むことが出来ない。
◯:期限が決められているので、そもそも正当な事由がいらない。
ということのようです。
ポイント解説も見ていきましょう‼️
✅️ポイント解説
- 定期借家契約は「契約期間の満了によって当然に終了」するのが原則です。
- 普通借家契約と違って「更新」という考え方がなく、貸主に正当事由がなくても終了できます。
- ただし、契約期間が1年以上の場合には、終了の通知義務(満了の1年前から6か月前まで)がある点が試験のポイントです。
🔍 深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 借家権とはなにか?
→「大家さん(貸主)と借りる人(借主)の力関係を公平にするためのルール」です。 - 定期借家権とはなにか?
→期間をあらかじめ定めて、更新がない借家権のことです。 - 普通借家権と定期借家権の違いを比較
→どちらも「建物を借りる権利」ですが、法律上の扱いが大きく違います。
借家権とはなにか?

借家権(しゃっかけん)とは、建物を借りて住んだり使ったりする権利のことです。
法律的には「建物賃借権」といいますが、日常的には「借家権」という呼び方をします。
つまり、大家さん(貸主)と賃貸契約を結んでアパートや一軒家を借りている人が持っている権利が「借家権」です。
借家権のポイント
- 使う権利がある
→ 契約した目的どおりに建物を使える。住居なら住めるし、事務所契約なら事務所として利用できる。 - 家賃を払う代わりに権利を維持できる
→ 家賃を支払っている限り、貸主は正当な理由なしに追い出せない。借主は安心して生活や事業を続けられる。 - 借地権とは違う
→ 借地権は土地を借りる権利。借家権は建物を借りる権利。混同しやすいので注意。
具体例
例1:アパートを借りる場合
あなたが月5万円でアパートの1室を借りて住んでいるとします。
このとき、あなたは「借家権」を持っており、大家さんが勝手に契約を解除して追い出すことはできません。

たとえば「自分の親戚を入居させたいから退去して」と言われても、正当事由(よほどの理由)がない限り拒否できるのです。
例2:店舗を借りる場合
パン屋を開きたい人が、駅前の建物1階を借りたとします。
このときも借主には「借家権」があり、賃料を払っている限り、オーナーは勝手に契約を切って出ていけとは言えません。

借家権があることで、安心して事業を継続できます。
借家権が重要な理由
- 借主の生活基盤や事業基盤を守るために、法律でしっかり保護されている。
- 特に「更新」「解約」「立ち退き料」などの場面で、借主を一方的に不利にさせないようルールが定められている。
✅ まとめると、借家権とは 「建物を借りて住んだり使ったりする権利」 で、借主の生活や仕事を守るために強く保護されているものです。
定期借家権とはなにか?

定期借家権(ていきしゃっかけん)とは、期間をあらかじめ定めて、更新がない借家権のことです。
これは平成12年(2000年)の法改正で導入された制度で、正式には「定期建物賃貸借契約」に基づく借家権です。
普通の借家(普通借家契約)だと契約期間が終わっても更新されるのが一般的ですが、定期借家権は契約期間が満了すれば自動的に終了します。

つまり「〇年で必ず終わる借り方」です。
定期借家権の特徴
- 更新がない
→ 期間が来れば必ず終了。更新の請求もできません。 - 書面で契約する必要がある
→ 口約束や口頭では無効。必ず公正証書や契約書などの書面が必要です。 - 終了の通知義務
→ 契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6か月前までに「終了しますよ」と通知しなければなりません。 - 普通借家契約と比べて貸主に有利
→ 借主の保護よりも「貸主が柔軟に建物を運用できる」ことに重点が置かれています。
具体例

例1:社宅として5年間だけ貸す場合
企業が社員のために建物を借りたいとします。
貸主と「5年間だけの定期借家契約」を結んだ場合、5年が経過すると自動的に終了します。社員がまだ住んでいても更新はできません。
例2:建替え予定の物件を貸す場合
仮に地主は「3年後に建物を建て替える予定」としているとします。
普通借家契約だと借主を退去させにくいですが、定期借家契約なら「3年間で終了」とあらかじめ決めておけるので、建替え計画に支障が出ません。
例3:短期間の利用(イベントや留学など)
例えば、留学のために「1年間だけ住む部屋が欲しい」と思った借主が、定期借家契約で1年契約を結ぶこともあります。期間満了で終了するので、貸主も借主も予定通りに解約できます。
定期借家権ができた背景
昔の普通借家契約は借主を強く保護する仕組みでしたが、そのために「貸したら返ってこない」「自由に活用できない」という貸主側の不満がありました。

定期借家権は、不動産をより柔軟に使えるようにするために生まれた制度です。
定期借家権_ポイントまとめ
- 普通借家権:更新あり。借主が強く保護される。
- 定期借家権:更新なし。期間満了で終了。貸主のニーズに対応。
- 実務では「建替え」「社宅」「短期利用」などに多く使われている。
✅ 一言でいうと、定期借家権は「期限付きで、必ず終わる借家権」です。
普通借家権と定期借家権の違いを比較

普通借家権と定期借家権は、どちらも「建物を借りる権利」ですが、法律上の扱いが大きく違います。
比較表を以下にまとめたので、違いをしっかりと把握しましょう。
| 項目 | 普通借家権 | 定期借家権 |
|---|---|---|
| 契約期間 | 原則1年以上(1年未満は無効) | 期間の制限なし(1年未満もOK) |
| 更新 | 期間満了後も自動的に更新されるのが原則 | 更新なし。期間満了で必ず終了 |
| 更新拒絶 | 貸主は「正当事由」がなければ更新を拒めない | 正当事由は不要。契約終了で必ず退去 |
| 終了通知義務 | 不要(更新が前提) | 契約期間が1年以上の場合、満了の1年前~6か月前までに終了通知が必要 |
| 契約方式 | 書面でも口頭でも有効 | 必ず書面(契約書や公正証書)が必要 |
| 借主保護の度合い | 借主を強く保護(住居の安定重視) | 貸主のニーズを重視(柔軟に活用可能) |
| 利用されるケース | 一般的な住居用賃貸(アパート・マンションなど) | 建替え予定の物件、社宅、短期利用、期間限定の貸し出し |
ポイントの整理
- 普通借家権は「借主を守る仕組み」。更新が前提なので、長く住み続けたい人には安心です。
- 定期借家権は「貸主を守る仕組み」。期限付きなので、建替えや短期利用など柔軟に使えます。
イメージ例
- 学生が4年間アパートに住む → 普通借家契約が一般的。更新して長く住むことができます。
- 建替え予定の建物を3年間だけ貸す → 定期借家契約が便利です。
満了で必ず終了します。
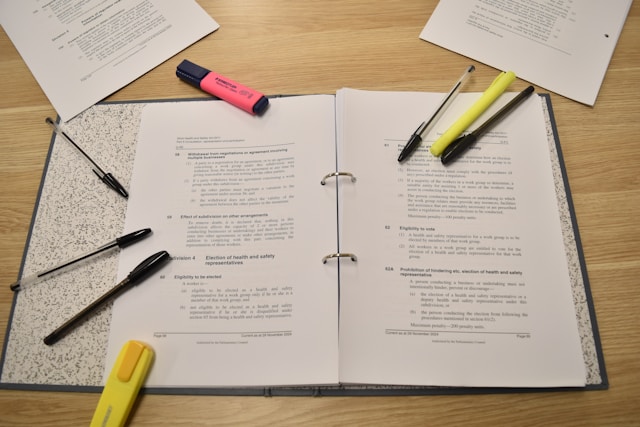
✅ 試験対策としては「正当事由が必要かどうか」と「更新の有無」が最大の違いです。
まとめ・今回の学び
- 借家権とはなにか?
→「大家さん(貸主)と借りる人(借主)の力関係を公平にするためのルール」です。
借家権がなければ、借主が突然立ち退きを迫られる危険があります。
そのリスクをなくすために「借家権」という強力な権利が認められているのです。 - 定期借家権とはなにか?
→期間をあらかじめ定めて、更新がない借家権のことです。
つまり、「〇年で必ず終わる借り方」です。 - 普通借家権と定期借家権の違いを比較
→どちらも「建物を借りる権利」ですが、法律上の扱いが大きく違います。
試験対策としては「正当事由が必要かどうか」と「更新の有無」が最大の違いです。
前回に引き続き、借地借家法についてまとめました。
今回は定期借家権に焦点を当て、普通借家権との比較もしています。
このあたりの理解がなかなか進まない場合は、この記事を反復的に確認しにきてください。
次回予告:賃貸借契約の期間について
次回は、借地借家法の中でも「賃貸借契約の期間」に関する重要な規定を取り上げます。
問題はこうです。
「借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、【何年】未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。」
建物の賃貸借契約では、期間の定め方がとても大切です。
特に「何年未満だと無効扱いになるのか?」は試験でも頻出ポイント。
実務でも大家さんや借主にとって大きな意味を持ちます。

次回は、この【年数】の考え方と、期間の定めがないときにどう取り扱われるのかを詳しく解説していきます。お楽しみに😁


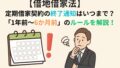

コメント