所得税の配偶者控除は、配偶者の所得が少ないときに税金を軽くしてくれる制度です。
ただし、控除を受けられるかどうかは「配偶者の所得」だけでは決まりません。
実は、納税者本人の所得金額が高すぎる場合も、控除を受けられないルールがあるのです。
今回は「年収が高い人は、配偶者控除を受けられない」という条件について、問題形式で確認していきましょう。
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の◯点です。
- 配偶者控除の条件と控除額について
→配偶者控除は、「配偶者の所得が低い家庭の税金を軽くするための控除」です。
控除額は900万円〜1000万円の間で徐々に減額されます。 - なぜ「1,000万円」という線引きがあるの?
→「どこまでを高所得者とみなすか」が議論され、年収約1,220万円(給与所得控除
を引くと所得金額1,000万円)以上が【高所得者】として区切りとして妥当と判断されました。 - 「老人控除対象配偶者」が「配偶者控除」と分けて制定されている理由
→高齢の配偶者がいる世帯は生活負担が大きくなりやすいためです。
📘 今回の分野:タックスプランニング/所得控除/配偶者控除
今回学ぶ範囲は、タックスプランニング分野の「配偶者控除」についてです。
配偶者控除が適用される条件を漏れなく理解します。
いろいろな数字が絡んで複雑な部分ですが、一緒に確認していきましょう。
❓️ 問題文の紹介
納税者の本年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多募にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
◯か✗か?
今回の問題文のポイントは、所得金額が1,000万円超えている場合にどうなるのか、です。
私が今回間違えてしまった要因は、『配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず』という点です。
配偶者分の所得が関連するだろうと考え、✘と回答しました。
回答を確認しましょう。
✅ 正解と解説の要点
納税者の本年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多募にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
◯か✗か?
→正解:◯(正しい)
正解は、◯(正しい)でした。
今回注目すべき点は、『配偶者の合計所得金額の多募にかかわらず』の一文です。
「適用」は配偶者の所得金額にかかわらず出来ますが、「控除金額」は配偶者の所得金額が一定を超える場合は減っていきます。
この違いはしっかりと把握しておきましょう。

配偶者控除の適用は、配偶者の所得金額は関係ないようです。
✅️ポイント解説
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除は適用できない。
- 配偶者の所得がゼロであっても、この基準を超えたら控除は受けられない。
- これは2018年(平成30年)の税制改正で導入されたルール。
- 高所得者への控除制限の一環として、年収約1,220万円超(給与所得者の場合)が対象
🔍 深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 配偶者控除の条件と控除額について
→配偶者控除は、「配偶者の所得が低い家庭の税金を軽くするための控除」です。
控除額は900万円〜1000万円の間で徐々に減額されます。 - なぜ「1,000万円」という線引きがあるの?
→「どこまでを高所得者とみなすか」が議論され、年収約1,220万円(給与所得控除
を引くと所得金額1,000万円)以上が【高所得者】として区切りとして妥当と判断されました。 - 「老人控除対象配偶者」が「配偶者控除」と分けて制定されている理由
→高齢の配偶者がいる世帯は生活負担が大きくなりやすいためです。
配偶者控除の条件と控除額について

配偶者控除は、【納税者と生計を一にする配偶者(民法上の配偶者に限る)】がいて、その配偶者の所得が少ない場合に、納税者の所得から一定額を差し引ける制度です。
要するに「配偶者の所得が低い家庭の税金を軽くするための控除」です。
適用条件(4つのポイント)
① 配偶者がいること
- 民法上の婚姻関係があること(事実婚は不可)
- 同居・別居は問わないが「生計を一にしている」必要あり
② 配偶者の合計所得金額が48万円以下
- 給与所得者の場合、給与収入103万円以下(給与所得控除55万円を差し引いた額が48万円)
- 年金や事業所得なども含めた合計所得金額で判定
③ 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 900万円以下 → 満額控除
- 900万円超~1,000万円以下 → 控除額が減額
- 1,000万円超 → 控除なし
④ 青色申告・白色申告など申告の有無は問わない
- 給与所得者も、事業所得者も利用可
控除額(納税者本人の所得に応じて変わる)
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額(一般の配偶者) | 控除額(老人控除対象配偶者) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超~950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 0円 | 0円 |
※老人控除対象配偶者:その年12月31日時点で70歳以上の配偶者
「配偶者特別控除」との違い
- 配偶者控除は配偶者の所得が48万円以下の場合に適用
- 配偶者特別控除は配偶者の所得が48万円超~133万円以下の場合に段階的に控除
- どちらも本人の所得が1,000万円超の場合は受けられない
配偶者控除_ポイントまとめ
- 配偶者控除の判断は「配偶者の所得」と「本人の所得」の両方を見る
- 控除額は本人の所得に応じて3段階
- 高所得者は配偶者控除も配偶者特別控除もゼロになる
なぜ「1,000万円」という線引きがあるの?
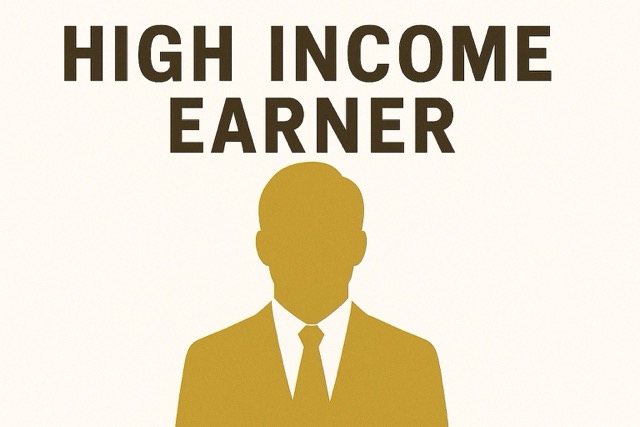
税制の公平性の確保
- もともと配偶者控除は、専業主婦(夫)など所得のない配偶者がいる家庭の税負担を軽くするために作られた制度です。
- しかし、高所得者も同じ控除を受けられると、税負担の公平性が保ちにくくなります。
- 年収が2,000万円ある人が38万円の控除を受けるのと、年収500万円の人が同じ38万円の控除を受けるのでは、家計への影響の大きさが全く違う
- 高所得者への税優遇は「逆進性」が強まり、社会的な不公平感を生む
- 年収が2,000万円ある人が38万円の控除を受けるのと、年収500万円の人が同じ38万円の控除を受けるのでは、家計への影響の大きさが全く違う
「逆進性」について
簡単に言うと
お金持ちの人ほど、税金を払っても生活にあまり影響がありません。
それなのに、所得が少ない人と同じ金額の控除(税金の割引)をあげてしまうと、お金持ちのほうが得をしてしまうように見えるんです。
例え話
- 年収2,000万円の人も、年収500万円の人も、配偶者控除で38万円の所得が引かれるとします。
- 38万円の控除で減る税金は、税率の高い高所得者のほうが金額が大きくなります。
- すると、「収入が多い人ほど税金の割引額が大きい」=税の負担割合が逆さになることがあります。
これを防ぐために、「本人の所得が1,000万円を超える人は控除を受けられない」というルールにして、税の公平さを保っているのです。
財源バランスの調整
- 日本は少子高齢化で社会保障費が増加しており、税収確保が重要な課題です。
- 高所得者層に対する控除を減らすことで、財源の一部を確保し、必要な支出(子育て支援や社会保障)に回す狙いがあります。
- この考え方は「応能負担(所得の多い人ほど多く税を負担する)」という税制の基本理念に沿っています。
なぜ1,000万円なのか
- 政策決定時、国税庁や財務省の試算によって「どこまでを高所得者とみなすか」が議論されました。
- 年収ベースに換算するとおおむね給与収入1,220万円(給与所得控除を引くと所得金額1,000万円)あたりが区切りとして妥当と判断された
- このラインを超えると、日本国内では上位数%の高所得層に入るため、「税優遇の対象から外しても社会的合意が得られやすい」とされた背景があります。
制度改正の経緯
- 2018年(平成30年)税制改正で導入されました。
- それまでは高所得者でも満額の配偶者控除が受けられました。
- 改正により、900万円超から段階的縮小、1,000万円超でゼロという形に変更されました。
「老人控除対象配偶者」が「配偶者控除」と分けて制定されている理由
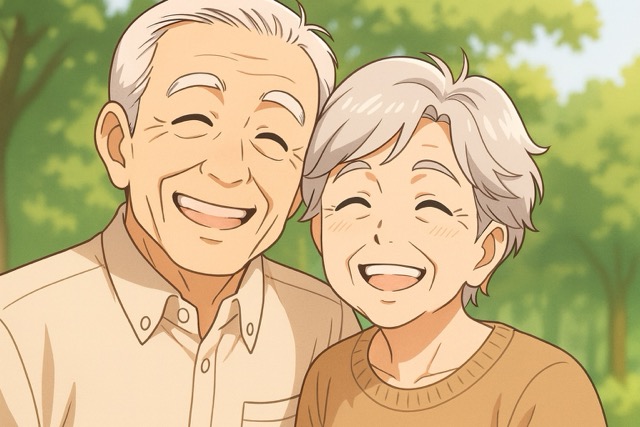
老人控除対象配偶者とは
- その年の 12月31日時点で70歳以上 の配偶者
- 民法上の配偶者で、生計を一にしていることが条件
- 所得要件(合計所得48万円以下)や、本人の所得要件(1,000万円以下)は通常の配偶者控除と同じ
区別されている理由
(1) 高齢者世帯は医療・介護費がかかりやすい
70歳を超えると、病院通いが増えたり、介護サービスが必要になる可能性が高まります。
これらは保険でカバーされない部分も多く、生活費の負担が大きくなりやすいのです。
(2) 働いて収入を得ることが難しい
高齢配偶者は、就業収入を得る機会が限られます。
現役世代のように働いて補うことが難しいため、世帯収入が少なくなる傾向があります。
(3) 税制による生活支援
こうした背景から、税金の控除額を少し上乗せして生活を支えるために、老人控除対象配偶者には通常より多い控除額(+10万円)が設定されています。
控除額の違い(本人の所得900万円以下の場合)
- 一般の配偶者控除:38万円
- 老人控除対象配偶者:48万円(+10万円)
つまり、老人控除対象配偶者は「所得が低い配偶者がいて、しかもその配偶者が高齢で生活負担が重い世帯」に対して、より手厚く税負担を軽くするために区別されている制度なのです。
まとめ・今回の学び
- 配偶者控除の条件と控除額について
→配偶者控除は、「配偶者の所得が低い家庭の税金を軽くするための控除」です。
控除額は900万円〜1000万円の間で徐々に減額されます。
→配偶者控除の適用は、配偶者の所得金額の影響はありません。 - なぜ「1,000万円」という線引きがあるの?
→「どこまでを高所得者とみなすか」が議論され、年収約1,220万円(給与所得控除
を引くと所得金額1,000万円)以上が【高所得者】として区切りとして妥当と判断されました。 - 「老人控除対象配偶者」が「配偶者控除」と分けて制定されている理由
→高齢の配偶者がいる世帯は生活負担が大きくなりやすいためです。
→医療・介護費用の負担や働けなくなることへの配慮です。
所得については、なかなかコントロールできるものではありませんが、扶養内で働いている方は意識している方は多いと思います。

扶養内で働いている方は、家計がどうなっているのか、ぜひ一度確認してみましょう‼️
次回予告:住宅ローン控除について
次回は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用条件について取り上げます。
住宅ローンを使ってマンションを購入したとき、この控除を受けるには借入金の返済期間が何年以上必要か把握していますか?
実は、この条件には正しいポイントと誤解しやすい部分があります。
控除の対象になる返済期間や、その他の要件をしっかり整理して解説します。


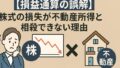

コメント