マイホームを売って新しい家に買い替えるとき、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」という制度があります。
これを使うと、譲渡所得にかかる税金を大きく減らせる可能性があります。
ただし、適用を受けるためには、いくつかの厳しい条件があり、特に「所有期間」と「譲渡価額の上限」がポイントになります。
今回は、その要件について試験問題を通して確認していきましょう。
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』とはどういうもの?
→マイホームを売って新しいマイホームに買い換えるときに、本来かかる税金を将来に繰り延べてくれる制度です。 - なぜ10年超が要件なのか?
→生活拠点として長く住んでいた証拠を示すためです。 - なぜ1億円以下が対象なのか?
→「普通の家庭向けの制度」という線引きをするためです。
📘 今回の分野:不動産の税金(買換え特例)

今回学習していく分野は、不動産における居住用財産の譲渡に係る特例についてです。
その特例の中でも『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』について詳しく解説していきたいと思います。

『マイホームを買い替える』という行為は、実生活においては、なかなか経験することがないかもしれません。
ただし、「こういう特例もあるんだな」くらいの知識を持っておけば、万が一当事者になった際も税制面で損をしなくなるはずです。
買い替えの特例に関する記事があるということだけでも覚えていただけたらと思います。
❓️ 問題文の紹介
個人が自宅の土地および建物を譲渡し、『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において当該譲渡資産の所有期間が【□1】を超えていることや、当該譲渡資産の譲渡対価の額が【■2】以下であることなどの要件を満たす必要がある。
【□1、■2】それぞれに入る年数と金額はいくらか?
この問題は時間をおいて何回か解いたんですが、何回も所有期間の選択で間違えてしまいました。
選択肢は、【5年と10年】。
毎回【5年】を選んでいました。
振り返って考えてみると、5年が3つの選択肢の中で、2つの選択肢に入れられていたため(下記のように)正解の確率が高いのではないかと思って、選んでいました。
- □1_5年、■2_1億円
- □1_5年、■2_1億6000万円
- □1_10年、■2_1億円
制度の意図や背景が頭に入っていれば、迷うことなく【3番】を選んでいますよね。
正解を確認して、正確な知識を取り入れましょう‼️
✅ 正解と解説の要点

個人が自宅の土地および建物を譲渡し、『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において当該譲渡資産の所有期間が【□1】を超えていることや、当該譲渡資産の譲渡対価の額が【■2】以下であることなどの要件を満たす必要がある。
【□1、■2】それぞれに入る年数と金額はいくらか?
→正解:【□1_10年】、【■2_1億円】
正解はそれぞれ、□1:10年、■2:1億円 でした。

正解を見ただけでは、「理解出来た」とは言えません。
10年と1億円の設定された背景も学び、イメージできるようにしましょう。
それではポイント解説を見ていきます。
✅️ポイント解説
この特例を受けるには、自宅を「10年以上所有」している必要があります。
また、譲渡する金額(売却額)は「1億円以下」でなければなりません。
これは高額な不動産取引では特例の適用を認めず、あくまで一般的な住宅の買換え支援を目的としているからです。
🔍 深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』とはどういうもの?
→マイホームを売って新しいマイホームに買い換えるときに、本来かかる税金を将来に繰り延べてくれる制度です。 - なぜ10年超が要件なのか?
→生活拠点として長く住んでいた証拠を示すためです。 - なぜ1億円以下が対象なのか?
→「普通の家庭向けの制度」という線引きをするためです。
『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』とはどういうもの?
1. そもそも「譲渡所得」とは?

家や土地を売ると、その売却益(売った値段-買った値段など)に税金がかかります。これを「譲渡所得(じょうとしょとく)」といいます。
特にマイホームを売るときは金額が大きいので、税金も大きくなりがちです。
2. 「買換え特例」とは?
この特例は、
👉「長年住んだマイホームを売って、新しいマイホームを買った人」
のために用意された、税金を軽くするルールです。
簡単に言うと、
「古い家を売った利益に、本来なら税金がかかるけれど、新しい家に買い換えるならその課税を将来に繰り延べてあげますよ」
という制度です。
3. 中学生向けの例え
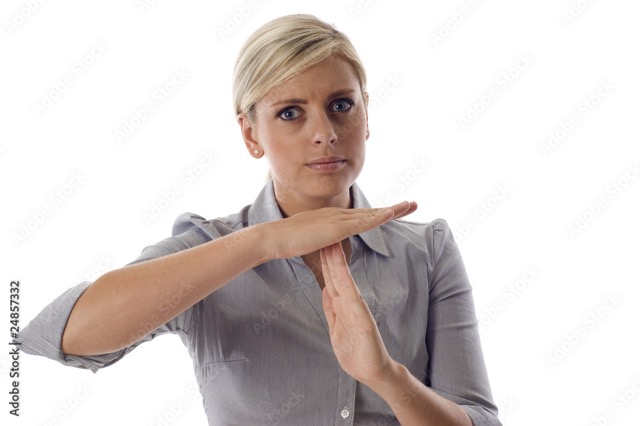
例えば、あなたが10年以上住んだ家を 5,000万円で売った としましょう。
その家を買ったときの値段や諸費用を差し引いたら、利益が2,000万円出た とします。
普通なら、この 2,000万円に税金 がかかります。
(譲渡所得の税率は20%強なので、数百万円になることもあります。)
でも、売ったあとに 新しい家を買った(しかも条件を満たした場合)なら、
「じゃあ今回の利益は課税しないで、新しい家を売るときまで繰り越しますね」
となります。

つまり、「いったん課税を待ってあげる」イメージです。
4. 適用の条件
この特例を受けられるには、次のような条件があります。
- 売った家や土地の所有期間が10年超
- 売却価格が1億円以下
- 売った年の前年から翌年までの3年間に新しい家を取得して住む
- 新しい家の床面積が50㎡以上などの住宅要件
5. 具体的なシナリオ
Aさんは、
- 20年前に自宅を3,000万円で購入
- 2025年にそれを5,000万円で売却(利益2,000万円)
- 同年に新しい自宅を4,800万円で購入
普通なら、利益2,000万円に課税されます。
でも「買換え特例」を使うと、今回は課税されず、将来この新しい家を売ったときにまとめて精算されます。
6. 注意点
- この特例を使うと、「居住用財産の3,000万円特別控除」とは併用できません。
- 将来、新しい家を売るときに「過去の利益+そのときの利益」で税金を計算されるので、完全に税金がなくなるわけではないのです。
- あくまで「先送り」なので、注意が必要です。
買換え特例_まとめ

「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」とは、
👉 マイホームを売って新しいマイホームに買い換えるときに、本来かかる税金を将来に繰り延べてくれる制度です。
簡単に言えば、
- 長年住んだ家を売って
- 新しい家を買ったら
- 「今すぐ税金払わなくていいよ、次のときにまとめてね」
という仕組みです。
なぜ10年超が要件なのか?

1. 制度の目的
この「買換え特例」は、生活のために長く住んでいた家を売って、新しい家に引っ越す人を助ける制度です。
つまり、
👉「家を投資の道具にして短期間で売った人」ではなく、
👉「本当に長年住んでいた人」だけが対象なのです。
2. なぜ10年?
10年という期間を設けるのは、
「その家が本当にマイホームとして生活の拠点になっていた」
ことを示すためです。
もし「3年」や「5年」しか住んでいなくても特例を受けられたら、どうなるでしょう?
- 家を買って、少し住んで値上がりしたらすぐ売る
- 税金を繰り延べして新しい家に移る
- これを繰り返して利益を上げる

こんなふうに節税テクニックとして悪用されてしまう可能性があります。
だからこそ「10年超」という長い期間を要件にして、
投資目的ではなく、実際に生活のために住んでいた人だけに絞っているのです。
3. 具体例で考える
- 例1:Bさん(3年しか住んでいないケース)
Bさんは、3年前に4,000万円で家を買いました。
不動産価格が上がって、今その家を5,000万円で売ると1,000万円の利益です。
→ もし10年ルールがなかったら、この利益にすぐ課税されず、特例を使って「節税目的の転売」が可能になってしまいます。 - 例2:Cさん(15年住んでいたケース)
Cさんは、15年前に2,500万円で家を買いました。
子どもが大きくなり、今の家が手狭になったので4,000万円で売却し、広い家を買うことにしました。
→ この場合は明らかに「生活のための買換え」なので、特例を使って税金を繰り延べできるのが妥当です。
4. 10年超_理由まとめ
- 「10年超」の要件は、生活拠点として長く住んでいた証拠を示すためです。
- 短期売買による投資的な節税利用を防ぐためのルールです。
- だから、制度の趣旨に合う「本当に長年住んで買換えが必要な人」だけが対象になります。

つまり、「10年」という区切りは「節税目的の転売」と「本当に生活のための引越し」とを分けるためのフィルターなのです。
なぜ1億円以下が対象なのか?

1. 制度の目的を思い出そう
「特定の居住用財産の買換え特例」は、
👉 普通の家庭が、長く住んだ家を売って、新しい家に買い換えるときに税金を軽くする制度
です。
つまり、国が助けたいのは「生活のために引っ越す人」であって、
「お金持ちが豪邸を売買するとき」ではありません。
2. なぜ「1億円以下」にしたのか?
もし金額の制限がなかったらどうなるでしょう?
- 2億円、3億円の豪邸を売っても特例が使えます。
- 結果として、お金持ちが何千万円もの節税をできてしまいます。
- 「本当に困っているわけではない人」だけが得をしてしまうのは不公平です。
これでは税金の制度として公平ではなくなります。
だから、国は「普通の家庭向けの制度ですよ」という線引きをするために、
「売却額1億円以下」というルールを作ったのです。
3. 具体例で考えてみよう

- ケース1:一般的な家庭の場合
佐藤さんの家は30年前に3,000万円で購入。
今売ったら6,000万円になりました。
→ 売却額6,000万円は 1億円以下なので特例が使えます。 - ケース2:豪邸を持つ家庭の場合
鈴木さんは20年前に8,000万円で大豪邸を購入。
今売ったら2億円になりました。
→ 売却額2億円は 1億円を超えるので対象外。

こうして「普通の家」と「豪邸」を区別しているのです。
4. 中学生向けのたとえ

学校で「修学旅行の補助金」があったとします。
- 普通の家庭 → 補助があると家計が助かる
- とてもお金持ちの家庭 → 補助がなくても全然困らない
だから学校は「収入がある一定以下の家庭だけ補助します」と決めますよね。
これと同じで、税制でも「売却額1億円以下の住宅に限定」して、制度を公平にしているのです。
5. 1億円の要件_まとめ
- この特例は「普通の家庭の買換え支援」が目的です。
- 豪邸や高級物件まで対象にすると不公平になります。
- そこで「売却価額1億円以下」という条件を設けています。

「1億円」という金額は、生活のためのマイホームと、富裕層の豪邸を分ける“しきい値”(特例の適用ライン)なのです。
まとめ・今回の学び
- 『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』とはどういうもの?
→マイホームを売って新しいマイホームに買い換えるときに、本来かかる税金を将来に繰り延べてくれる制度です。
→「今すぐ税金払わなくていいよ、次のときにまとめて支払ってね」という意味です。 - なぜ10年超が要件なのか?
→生活拠点として長く住んでいた証拠を示すためです。
→短期売買による投資的な節税利用を防ぐための縛りのルールです。 - なぜ1億円以下が対象なのか?
→「普通の家庭向けの制度」という線引きをするためです。
→この特例は「普通の家庭の買換え支援」が目的で、高級物件は対象外です。
今回は、『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』について解説しました。
なんとなくでもイメージが付いたのではないでしょうか。
文章だけではなかなか覚えられませんからね。
特例を受けるための要件の理由や背景をイメージできるようにすることが、その特例を理解する一番の近道だと思います。
この記事には、理由や背景が書かれていたなということだけでも覚えていってください。
次回予告:特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

今回学んだ「買換え特例」に続いて、次回は譲渡損失に関する特例を取り上げます。
テーマは、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。
この制度を使うと、マイホームを売って損が出た場合でも、他の所得(給与など)と損益通算ができます。
さらに控除しきれなかった損失は、翌年以降に繰り越すことが可能です。
では問題です。
👉「譲渡の年の翌年以後、最長で『何年』以内で繰越控除が認められるでしょうか?」

次回はこの年数を確認しながら、仕組みや注意点をわかりやすく解説していきます。
お楽しみに!



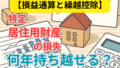
コメント