相続に関する税制の中でも注目される「空き家に係る譲渡所得の特別控除」。
相続した居住用家屋やその敷地を売却する際に、条件を満たせば最大3,000万円の控除を受けることができます。
今回は、その要件の一つである「譲渡資産の譲渡対価の額」に関する問題を見ていきましょう。
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』とはなにか?
→最大3,000万円まで利益を税金から引いてもらえる制度。 - なぜ6000万円でなく1億円以下が要件なのか?
→「一般的な住宅を守るための制度」であり、高額すぎる物件は対象外にする、という線引きが 1億円 なんです。 - なぜ「3年後の年末まで」という期間が設定されているのか?
→3年は「検討・売却に十分な時間」と「放置を防ぐバランス」を考えた期間。
→年末で区切るのは、税金計算の区切りに合わせるため。
📘 今回の分野:不動産の税金

今回学ぶ範囲は、不動産の税金:居住用財産の譲渡に係る特例の中の『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』についてです。
上記の特例を簡単に言えば、空き家を譲渡した場合、譲渡所得から3000万円を控除してくれるというものです。
空き家の3,000万円控除を受けるためには、どのような要件があるのか。
注意しなければならない点も含めて、具体例を示しながら解説していきます。
❓️ 問題文の紹介
個人が相続により取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地を譲渡し、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が6,000万円以下であることなどの要件を満たす必要がある。
◯か✗か?
居住用の家屋+敷地で6000万円以下は、そんなもんなのかな、と思いました。

ただ、土地の価格には差があるので、そのあたりも考慮しないとダメでしたね。
正解を確認してみましょう‼️
✅ 正解と解説の要点

個人が相続により取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地を譲渡し、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が6,000万円以下であることなどの要件を満たす必要がある。
◯か✗か?
→正解:✘(誤り)
正解は✗、誤りの文章でした。
論点は、譲渡資産の譲渡対価の額が6000万円以下であるかという点。
ポイント解説ではなく、深堀りの方で「なぜ1億円なのか」について触れていますので、ご確認いただけたらと思います。
✅️ポイント解説
正しくは「譲渡対価が 1億円以下 であること」が要件です。
他の主な要件:
- 被相続人が一人暮らしだった居住用家屋であること。
- 耐震基準を満たすリフォームをしてから譲渡、または取り壊して譲渡すること。
- 相続開始から3年後の年末までに譲渡すること。
🔍 深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』とはなにか?
→最大3,000万円まで利益を税金から引いてもらえる制度。 - なぜ6000万円でなく1億円以下が要件なのか?
→「一般的な住宅を守るための制度」であり、高額すぎる物件は対象外にする、という線引きが 1億円 なんです。 - なぜ「3年後の年末まで」という期間が設定されているのか?
→3年は「検討・売却に十分な時間」と「放置を防ぐバランス」を考えた期間。
→年末で区切るのは、税金計算の区切りに合わせるため。
『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』とはなにか?
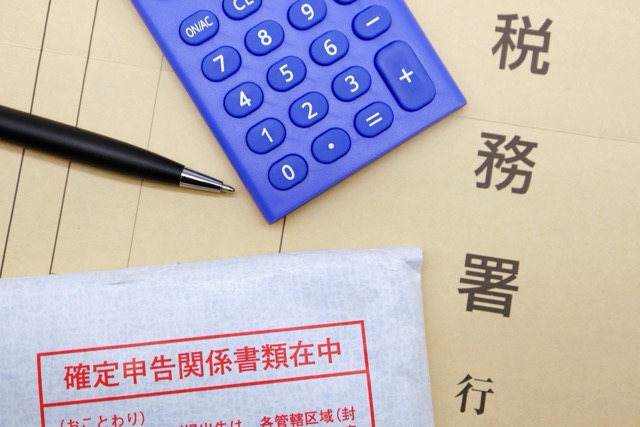
まず「特例」ってなに?
特例とは「特別に認められたルール」のことです。
税金の世界では
「本当なら税金を払わなきゃいけないけど、特別に軽くしてあげますよ」
という意味で使われます。
この特例ができた理由
日本には「空き家」が増えています。
空き家が放置されると…
- 景観が悪くなる
- 不審火や犯罪の温床になる
- 地域全体の安全に悪影響
こうした問題を減らすために
「相続で空き家を受け取ったら、売却して有効活用してほしい」
という国の思いから作られた制度です。
内容をシンプルに言うと

- 相続した実家(空き家)を売ったとき、
- 最大3,000万円まで利益を税金から引いてもらえる
→ これが「空き家の3,000万円控除」の特例です。
適用の条件
ただし誰でもOKではなく、いくつか条件があります。
- 被相続人(亡くなった方)が一人暮らしだった自宅であること
- その家を相続した人が売却すること
- 売却のときに耐震基準を満たしているか、取り壊してから売ること
- 譲渡価格が 1億円以下 であること
- 相続から 3年を経過する年の12月31日まで に売却すること
具体例でイメージ
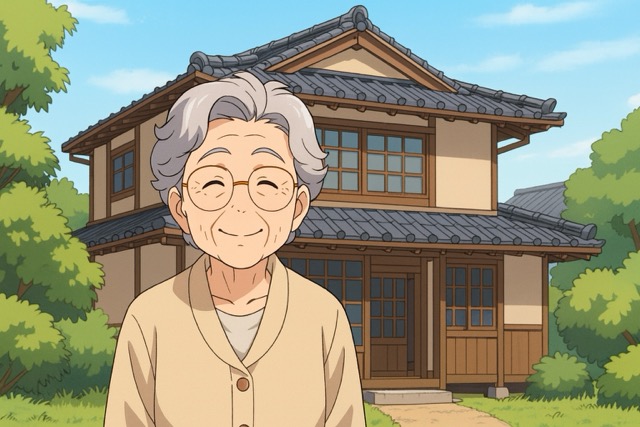
例えば…
- おばあちゃんが住んでいた家を相続したけど、誰も住まない
- その家を売ったら2,500万円の利益が出た
- 本来ならその2,500万円に税金がかかる
- でも特例を使えば「3,000万円までは非課税」なので 税金ゼロ!
逆に、もし5,000万円の利益が出た場合は…
- 3,000万円は控除される
- 残りの2,000万円だけが課税対象
中学生向けのたとえ
イメージとしては「学校で配られる給食費の補助」です。
- 普通なら毎月5,000円払わないといけない
- でも「特例」として3,000円分の補助が出る
- だから実際に払うのは2,000円で済む

これと同じで、空き家を売ったときの利益から3,000万円まで補助(控除)がつく、という仕組みなんです。
空き家特例_まとめ
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、
👉 相続した空き家を売るときに、最大3,000万円まで税金の計算から引いてくれる制度です。
👉 空き家を放置せずに売却してもらうことで、社会の空き家問題を解決する狙いがあります。
なぜ6000万円でなく1億円以下が要件なのか?

制度の目的から考える
この「空き家に係る譲渡所得の特別控除」は、
👉「放置された空き家を減らして、地域の安全や景観を守る」
ことが目的です。

つまり、地方や郊外でよくある「誰も住まなくなった実家」を売却してもらうための制度なんです。
もし6,000万円だったら?
たとえば、
- 東京や大阪の都心部にある家や土地は、普通に売っても6,000万円を超えることが多いです。
- もし上限が6,000万円なら、都市部の物件はほとんど対象外になってしまいます。
これだと「地方の空き家だけ」しか救えなくなり、制度の公平性がなくなってしまいます。
1億円以下ならどうなる?
- 1億円にすると、都市部の中規模な住宅も対象に含められます。
- ただし「豪邸」や「超一等地のマンション」(2億円、3億円など)は対象外。
- 要するに「一般的な住宅を守るための制度」であり、高額すぎる物件は対象外にする、という線引きが 1億円 なんです。
具体例でイメージ
- 地方の空き家:売値が2,000万円 → 条件クリア(もちろん対象内)
- 都心の普通の一戸建て:売値が8,000万円 → 条件クリア(対象内)
- 都心の豪邸や億ション:売値が1億5,000万円 → 上限オーバーで対象外
中学生にもわかるたとえ
イメージとしては「学校の補助金」みたいなものです。
- 収入が普通の家庭(例:世帯年収500万〜800万)は補助金がもらえる。
- でも超お金持ち(年収3,000万、豪邸暮らし)は補助金の対象外。

空き家特例も同じで、「ふつうの人が持っている家」までを守りたいから1億円にしているんです。
✅ まとめると
- 6000万円だと都市部の普通の住宅が救えない
- 1億円にすることで、一般的な住宅を幅広くカバーできる
- でも豪邸は対象外にしたいから、上限を設けている
なぜ「3年後の年末まで」という期間が設定されているのか?

そもそも期限を決める理由
制度の目的は 「空き家を放置せず、なるべく早く処分してもらうこと」 です。
もし期限がなかったら…
- 相続した人が「いつか売ろう」と思って何十年も放置
- その間に家が老朽化して倒壊の危険
- 地域の景観や治安が悪化
👉 これでは制度の意味がなくなります。

だから「時間制限」が必要なんです。
なぜ「3年後の年末まで」なのか?
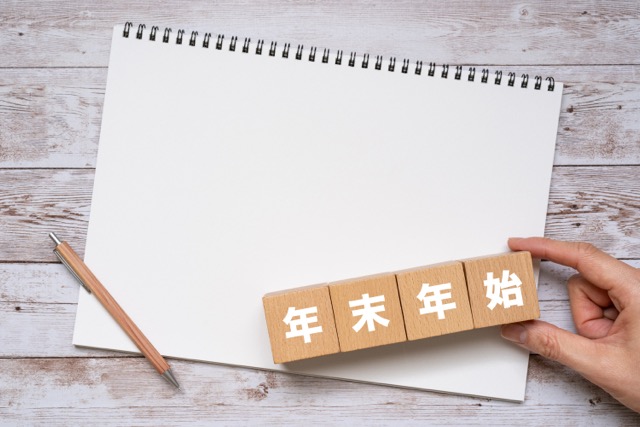
ここには実務的な理由があります。
- 相続税の申告期限との関係
- 相続税の申告期限は「相続開始から10か月以内」。
- その後、売却の検討や買主探しにある程度の時間が必要。
- 3年という期間は「売却活動をするには十分な時間」と考えられている。
- 相続税の申告期限は「相続開始から10か月以内」。
- 年末で区切るのは税金計算のため
- 税金は「1月1日から12月31日」までを1年として計算します。
- 「年末まで」という期限なら、誰でも理解しやすい。
- 税金は「1月1日から12月31日」までを1年として計算します。
具体例でイメージ
- 2023年6月:おばあちゃんが亡くなり、空き家を相続。
- 2024年:リフォームするか、取り壊すか検討。
- 2025年:不動産会社に相談して売却活動スタート。
- 2026年12月31日までに売れば、特例が使える。
👉 相続から約3年半の猶予があるので、「十分準備できるけど、放置はできない」絶妙なラインなんです。
中学生向けのたとえ

これは「夏休みの宿題」に似ています。
- 宿題をずっと放置すると、夏休みが終わったときに大変なことになる。
- だから「8月31日まで」という期限が決まっている。

空き家特例も同じで、「3年後の12月31日まで」という期限があるから、人は動くんです。
もし期限がなかったら、ずーっとやらずに放置する人が出てしまいます。
期間設定の理由_まとめ
- 期限があるのは「空き家を早く市場に出してほしい」から。
- 3年は「検討・売却に十分な時間」と「放置を防ぐバランス」を考えた期間。
- 年末で区切るのは、税金計算の区切りに合わせるため。
👉 要するに「放置防止+わかりやすさ」のために「3年後の年末まで」と決められているのです。
まとめ・今回の学び
- 『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』とはなにか?
→最大3,000万円まで利益を税金から引いてもらえる制度。
→「相続で空き家を受け取ったら、売却して有効活用してほしい」という国の思いから作られた制度です。 - なぜ6000万円でなく1億円以下が要件なのか?
→「一般的な住宅を守るための制度」であり、高額すぎる物件は対象外にする、という線引きが 1億円 なんです。
→もし上限が6,000万円なら、都市部の物件はほとんど対象外になってしまいます。 - なぜ「3年後の年末まで」という期間が設定されているのか?
→3年は「検討・売却に十分な時間」と「放置を防ぐバランス」を考えた期間。
→年末で区切るのは、税金計算の区切りに合わせるため。
→「放置防止+わかりやすさ」のために「3年後の年末まで」と決められています。
『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』について解説しました。
昨今、少子高齢化とともに空き家問題が話題になっていますよね。
この特例が周知されれば、少しは問題解消の一助になるかもしれません。
私もこの勉強をして初めて知りました。

次回も税制上、オトクな情報をお届けできればと思っています。
次回予告:NOI利回りとは?
次回は、不動産投資の計算問題を取り上げます。
「投資総額1億円で購入した賃貸用不動産の年間収入の合計額が1,000万円、年間費用の合計額が350万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、【何%?】である。【】内に入る数値はいくらか?」
不動産投資の利回りは、単なる数字遊びではなく「投資の収益性」を見抜く重要な指標です。
試験での頻出テーマでもあり、実務でも役立つ考え方ですので、ぜひ次回の解説で一緒に確認していきましょう!
お楽しみに‼️


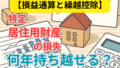

コメント