みなさん、FPの勉強は順調ですか?
私は今停滞しています。
なぜか?
ライフプランニング分野の「6つの係数」が意味ワカラン状態だからです‼️
この状態、なんとか解消したいですよね。
「6つの係数」をしっかり理解したい‼️
そんな私と同じような状況のそこのアナタ!
一緒に学んでいきませんか?
この記事を読み切れば、きっと「6つの係数」の理解が深まっていること間違いなしです‼️
(むちゃくちゃハードル上げてるけど大丈夫かな・・・?)
それでは一緒に読み進んでいきましょう‼️
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の2点です。
- ライフプランニング「6つの係数」って何?
→将来の資金計画においての試算に用いる数値です。 - よくあるケアレスミスを紹介‼️
→「今 → 将来」なのに逆の係数を使う。
→「一括のお金」なのか「毎年のお金」なのか混同する。
などが挙げられます。
今回の分野:資産計算で使う6つの係数(ライフプランニング)
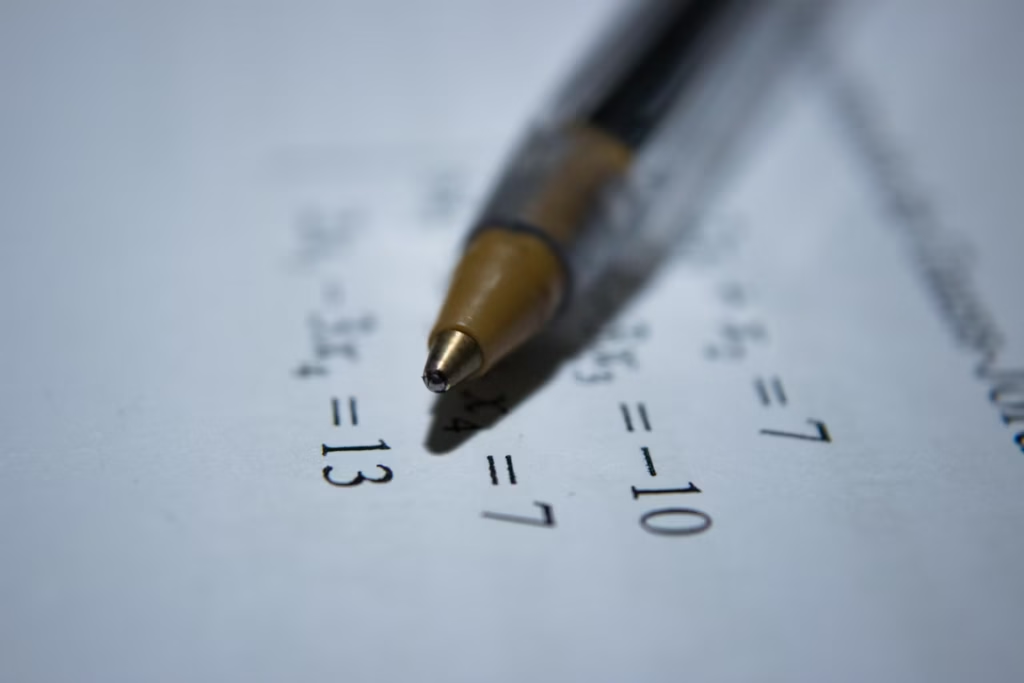
FP3級のライフプランニング分野を勉強していて、最初につまずいたのがこの「6つの係数」でした。
問題集にはよく出てくるけど、「とりあえず数字を表にあてはめて終わり」では、何をしているのかピンきていません。
そこで今回は、この内容をわかりやすく整理してみました。
❓️ 問題文の紹介:「6つの係数」の使い分け
- 15年で900万円を用意する。
- 毎年均等積立。
- 利率(年率)1.0%で複利運用。
必要となる積立金額は?
与えられた係数は以下の通り。
- 現価係数 :0.8613
- 資本回収係数:0.0721
- 減債基金係数:0.0621

最初は全然わかりませんでした。
当てずっぽうで選んだら間違えた問題です。
答えを見ると、900万にどれかの係数をかけたら、その答えの選択肢と合致しました。
回答に書いてあるとおりに掛け算をして求める、というふうに覚えることもできます。
でも、とりあえず正解することはできるけど、理解はできない。

ただ覚える・・・
それでは意味はないので、もう少し掘り下げていきましょう。
正解と解説の要点:900万円を用意するにはこの係数!

- 15年で900万円を用意する。
- 毎年均等積立。
- 利率(年率)1.0%で複利運用。
必要となる積立金額は?
与えられた係数は以下の通り。
- 現価係数 :0.8613
- 資本回収係数:0.0721
- 減債基金係数:0.0621
正解:900万円×0.0621=558,900円(毎年)
正解は、減債基金係数(0.0621)を用いて算定します。
558,900円(=900万円×0.0621)を毎年積み立てると、15年で目標金額900万円を積み立てることが出来るという計算になります。
一旦、利息なしの場合を考えてみましょう。
900万円/15年 = 600,000円/年になりますね。
60万円は900万円の内、何%にあたるか、割り出しておきましょう。
60万円/900万円 = 0.0667(6.67%)
ここで、3つの係数の中で、現価係数が大きく異なる数値なので除外します。
正解は残り2つの内、ひとつ。
資本回収係数を考えます。
900万円に0.0721をかけると64.89万円になり、15年より早い段階で目標金額に到達してしまうことがわかります。
利息が積立金額を助けてくれる(積立金額が少なくて済む)という観点から、0.0667より小さい係数、0.0621を回答する、という導き方もあります。
✅️ポイント解説:「6つの係数」って何をするもの?
かんたんに言えば、「お金の今の価値と、未来の価値をすばやく計算できる便利な数値」です。
| 係数の名前 | 何を計算するか |
|---|---|
| ① 終価係数 | 現在のお金が将来いくらになるか |
| ② 現価係数 | 将来のお金の今いくら必要か |
| ③ 年金終価係数 | 毎年積み立てたら将来いくらになるか |
| ④ 年金現価係数 | 将来定額でもらえるお金ために今いくら必要か |
| ⑤ 減債基金係数 | 将来の一定額を貯めるために今いくらずつ積立? |
| ⑥ 資本回収係数 | 今あるお金を分割払い(複利運用)で一定期間で取り崩すには? |

現在のお金を黄色で、将来のお金を青色でマーキングしてみました。
見やすいかな?
これらは「年利◯%で◯年間」などの条件があれば、すぐに使える係数が表になっています。
これをかけるだけで計算できる、超便利なモノなんです。
6つの係数について_深堀り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- ライフプランニング「6つの係数」って何?
→将来の資金計画においての試算に用いる数値です。 - よくあるケアレスミス
→「今 → 将来」なのに逆の係数を使う。
→「一括のお金」なのか「毎年のお金」なのか混同する。
などが挙げられます。
ライフプランニング「6つの係数」って何?

「6つの係数」とはなにか?
一言でいうと、
将来の資産計画を計算するための「時間と利息」が考慮された便利な係数です。
たとえば、こんなことを考えたことはありませんか?
- 10年後に100万円ほしい。今いくら貯めればいい?
- 毎年10万円ずつ積み立てたら、20年後はいくらになる?
- 老後に毎年50万円ずつ使うには、今いくら必要?
こういう「未来のお金」と「今のお金」をつなぐ計算を、
一発でできるようにしたのが 6つの係数 です。
電卓で毎回ゴリゴリ計算する代わりに、
「係数表」を見て掛け算するだけで答えが出る仕組みになっています。
なぜ「6つ」あるの?
お金の計算には、大きく分けて次の3パターンがあります。
① 今のお金 → 将来いくらになる?
② 将来ほしいお金 → 今いくら必要?
③ 毎年コツコツ積立・取り崩し
これをさらに細かく分けると、全部で6種類の計算パターンになるため、
「6つの係数」が用意されています。
📘 6つの係数を超かんたんに整理
まずは細かい名前より、「役割」をイメージしましょう。
| 係数の役割 | 何を知りたい? | イメージ |
|---|---|---|
| ① 今 → 将来 | 今の100万円が10年後いくら? | 貯金がふくらむ |
| ② 将来 → 今 | 10年後に100万円ほしい。今いくら? | 逆算する |
| ③ 毎年積立 → 将来 | 毎年積立したら合計いくら? | コツコツ貯める |
| ④ 将来目標 → 毎年積立 | 目標金額を貯めるには毎年いくら? | 割り算の発想 |
| ⑤ 元金 → 毎年受取 | まとまったお金から毎年いくら使える? | 年金イメージ |
| ⑥ 毎年受取 → 必要元金 | 毎年〇円使うには元金いくら必要? | 老後資金 |
具体例で見てみましょう‼️実際に計算してみる

例①:今の100万円は10年後いくら?
- 今 :100万円
- 年利:3%
- 期間:10年
このとき使うのが、
「終価係数」= 今のお金を将来に増やす係数です。
仮に係数が「1.34」だったとすると、
100万円 × 1.34 =134万円

何もしなくても利息でお金が増える、というイメージです。
例②:毎年10万円ずつ貯めたら20年後いくら?
- 毎年:10万円積立
- 年利:2%
- 期間:20年
このとき使うのは、
「年金終価係数」= 積立の合計を求める係数です。
仮に係数が「24.3」なら、
10万円 × 24.3 =243万円

毎年コツコツ積み立てると、利息もついて増えていく、というイメージです。
例③:老後に毎年50万円使いたい。元金はいくら必要?
- 毎年:50万円使いたい
- 期間:20年
- 年利:1%
このとき使うのは、
「年金現価係数」= 毎年使うお金から、元金を逆算する係数です。
仮に係数が「18.0」なら、
50万円 × 18.0 = 900万円

つまり、老後資金として約900万円必要、という考え方になります。
よくあるケアレスミスを紹介

以下に、今回取り扱った「6つの係数」の問題においての、
よくあるケアレスミスの代表例を3選紹介します。
対処法も記載していますので、もし当てはまるようでしたら参考ください。
ミス①:今と将来、どちらの金額を求めたいのか?
「今 → 将来」なのに逆の係数を使ってしまう
- 将来金額を出したいのか?
- 今の金額を出したいのか?
まずここをハッキリさせるのが大切です。
ミス②:一括か、毎年か
「一括のお金」なのか「毎年のお金」なのか混同する
- 一括 → 終価係数・現価係数
- 毎年 → 年金系の係数
この切り分けができると、一気に正解率が上がります。
ミス③:単純な読み間違い
期間と利率の読み間違い
- 10年なのか?20年なのか?
- 年利なのか?月利なのか?
問題文は必ず線を引いて読むクセをつけると安心です。
まとめ・今回の学び:
- ライフプランニング「6つの係数」って何?
→将来の資金計画においての試算に用いる数値です。
一覧表を記載したので参考ください。
一度、係数を用いて計算してみるとイメージが付いていいかもしれません。 - よくあるケアレスミス
→「今 → 将来」なのに逆の係数を使う。
→「一括のお金」なのか「毎年のお金」なのか混同する。
などが挙げられます。
→対処法も本文に記載しましたので、ご確認ください。
今回はライフプラン分野の「6つの係数」についての問題文を取り上げ、解説しました。
イメージはつきましたか?
正直、「係数を丸暗記する」だけではすぐ忘れます。
でも、「どんな場面で、何を計算したいのか」
を意識しながら学ぶと、定着度合いは段違いです。
このブログでは、こうしたつまずきやすい知識を
ひとつずつ自分の言葉で解説していきます。
参考になれば幸いです。

次回は「ファイナンシャルプランナーのあるべき姿とは?」という点を深堀りしていきます。
次回予告:ファイナンシャルプランナーの出来ること/出来ないこと

ファイナンシャルプランナーといえば、お金のプロ!というイメージはありますが、具体的な内容って把握されていますか?
FPの仕事は、その資格を持っていたとしても制限されています。
次回は「ファイナンシャルプランナーの出来ること/出来ないこと」について解説していこうと思います。
→こちらをクリック

お楽しみに‼️


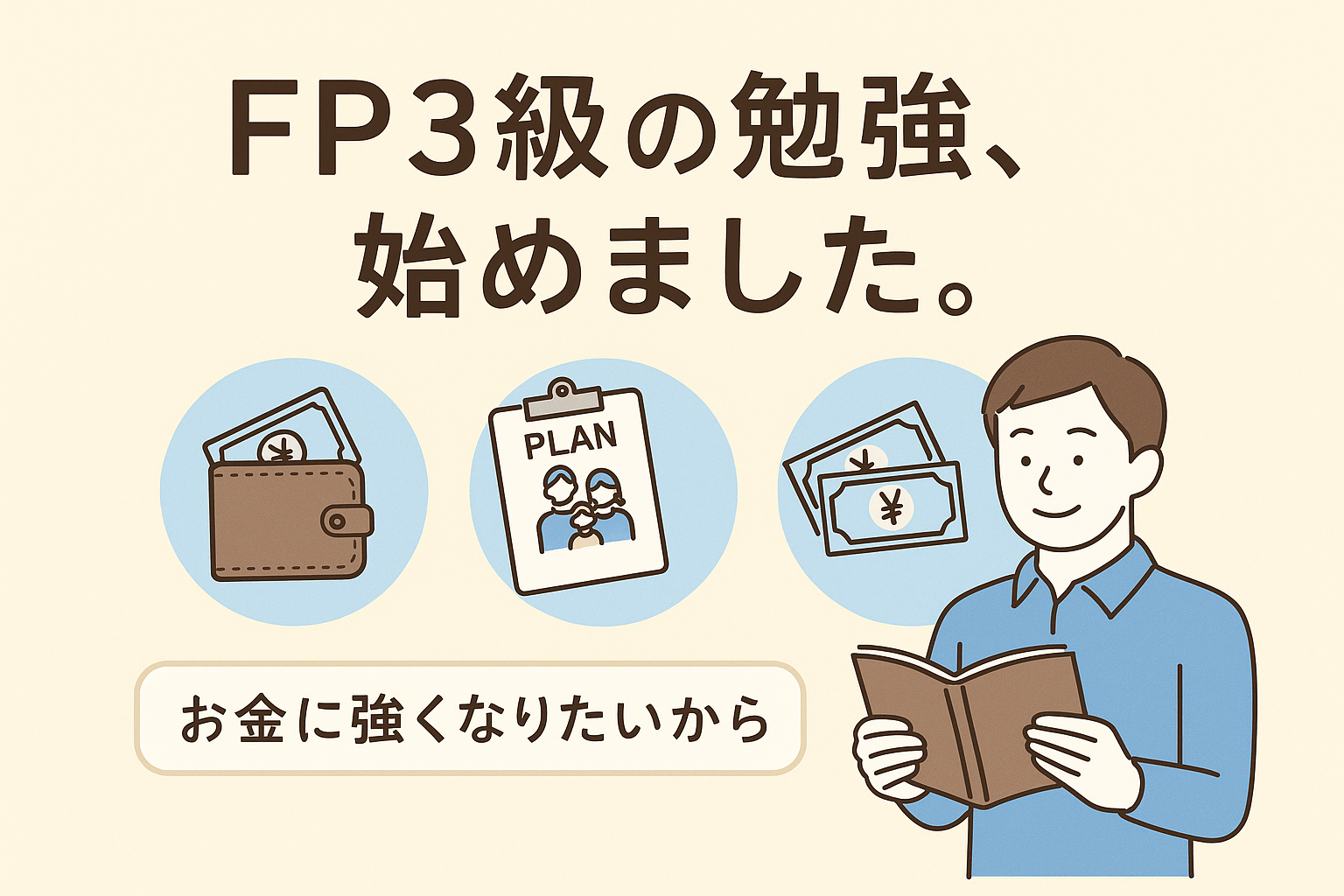

コメント