「火災保険に入っていれば、地震のときも安心…」と思っていませんか?
実は、火災保険だけでは地震による被害はカバーされません。
そのため、地震保険の加入が重要になるのですが、ここで注意すべきなのが、【保険金額の「上限」】です。

どうも、こいちろです😁
今回もFPの知識を自分の血肉に変えていきましょうっ‼️
この記事は、本業に飽き飽きしてきた建築士が綴る、新たな知識を得るためのブログです。
今回は、地震保険の保険金額が火災保険とどう関係しているかを、FP3級の問題をもとに整理していきます!
よろしければ、お付き合いください☺️
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の4点です。
- 地震保険が単独で契約できない、その理由。
- 地震保険の「30〜50%」って何のこと?
- 地震保険に上限がある理由は?
- 火災保険と地震保険の役割の違いとは?
📚今回の分野:リスク管理(損害保険)/地震保険と火災保険の関係
今回学ぶ範囲は、リスク管理(損害保険)/地震保険と火災保険の関係です。
地震保険と火災保険の違い、補償範囲を明確にして、正しい知識で契約しましょう‼️
📝問題文の紹介
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の【□1】の範囲内で設定することになるが、
居住用建物については、【■2】、生活用動産(家財)については1,000万円が上限となる。
□1:◯〜●%か?
■2:何千万円か?
選択肢は以下の3つです。
- □1:30%〜50%、■2:3000万円
- □1:30%〜50%、■2:5000万円
- □1:50%〜80%、■2:5000万円
3と5の数字が多いですね。

私は1.の選択肢を選びました。
参考書には、なんとなくですが、3の数字が多かったかな〜と。
ほんと、なんとなくの記憶ですが。。。
・・・正しい知識を身につけましょうね。
なんとなくでは、実践(生活)の役には立ちません。
それでは正解と解説を確認しましょう‼️
✅正解と解説の要点
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の【□1】の範囲内で設定することになるが、
居住用建物については、【■2】、生活用動産(家財)については1,000万円が上限となる。
□1:◯〜●%か?
■2:何千万円か?
正解_□1:30〜50%、■2:5000万円

5の数字のほうが多い・・・。
覚え方が間違っているかも知れません💦
どのような意図・背景で正解の数字に決められているのか確認しましょう。
その前にポイント解説から見ていきます‼️
✅️ポイント解説
地震保険は、単独で契約することはできず、火災保険に付帯するかたちで加入します。
そして、地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内で設定する必要があります。
さらに、保険金額には上限があります:
- 建物(居住用):上限 5,000万円
- 家財(生活用動産):上限 1,000万円
この上限は、仮に火災保険で1億円をかけていても、地震保険ではそれ以上は補償されないという意味です。
🔍深掘り考察!!:
今回の考察は、以下の点に絞って解説していきたいと思います。
- 地震保険が単独で契約できない、その理由。
- 地震保険の「30〜50%」って何のこと?
- 地震保険に上限がある理由は?
- 火災保険と地震保険の役割の違いとは?
🔍 地震保険が単独契約できない理由とは?
✅ 理由1:保険金支払いリスクが極端に大きいから
地震は一度に広い地域・多くの人に被害が及ぶ災害です。
たとえば、巨大地震が起これば、何万世帯・何千億円単位で保険金の支払いが必要になることもあります。
これだけ大規模な損害に備えるのは、民間の保険会社だけでは対応しきれないのです。
そのため、地震保険は「政府と民間が共同で運営する制度(=地震再保険制度)」となっています。

この制度の中で、「信頼できる火災保険の契約に付ける」という条件を設けて、
無制限な加入や乱用を防いでいるのです。
✅ 理由2:建物の実態把握と保険の適正性を担保するため

火災保険に加入するには、建物の構造・築年数・所在地などが審査されます。
これによって「保険金額が妥当かどうか」が確認されています。
その火災保険に付帯させる形(オプション)にすることで、
- 同じ建物について2つの保険(火災+地震)が整合性ある内容で契約される
- 重複や過大請求のリスクが減る
というメリットもあります。
🧩 単独契約できない理由まとめ
| 地震保険が単独で契約できない理由 | 内容 |
|---|---|
| リスクが大きすぎるため | 保険会社だけで支えるのが難しい(政府と共同) |
| 加入審査の合理化 | 火災保険で建物の情報をすでに確認しているから |
| 制度の乱用防止 | 加入のルールを明確にして不正や過剰契約を防ぐため |
少し難しい話にも思えるかもしれませんが、

「火災保険が“地盤”になって、地震保険が“追加オプション”として機能している」と考えるとわかりやすいですよ。
✅ 地震保険の「30〜50%」って何のこと?
地震保険は、火災保険にセットでつけるオプションのような保険です。
ただし、火災保険と同じ金額をまるごとカバーできるわけではなく、火災保険の金額の30%〜50%の範囲内でしか保険金額を設定できません。
🔍 具体的な例で説明すると
たとえば…
| 火災保険の契約金額 | 地震保険で設定できる金額 |
|---|---|
| 2,000万円(建物) | 600万円〜1,000万円(=30〜50%) |
| 1,000万円(家財) | 300万円〜500万円(=30〜50%) |
このように、火災保険で設定している金額がベースになりますが、
地震保険の契約はその30〜50%の範囲内でしかできないのです。

なぜ100%ではダメなのでしょうか。
その理由も見ていきましょう‼️
100%ではだめな理由① 地震の被害は広範囲で大きすぎる
火災や風災と違って、地震は一度に何万件もの被害が出る災害です。
そのため、保険会社が支払う金額も莫大になります。
100%補償にしてしまうと、保険制度そのものが破綻するおそれがあるのです。
100%ではだめな理由② 最低限の生活再建が目的だから
地震保険は、元どおりに建て直すための保険ではありません。
「被災してすぐに生活を立て直すための資金をサポートする」ことが目的です。
そのため、補償は“必要最低限”の範囲にとどめられているという考え方になっています。
✅ 地震保険に上限がある理由は?
一言でいうと、地震の被害は大きすぎるからです。
火災や風災のように「一部の家だけ」が被害を受ける保険とは違い、地震が起きると同時にたくさんの人の家が壊れることがよくあります。
🔍 たとえば…パン屋さんの例で考えてみましょう
あなたがパン屋さんだとします。
近所の人100人に「万が一、パンが買えなくなったら代わりに配りますよ」と約束して、保険のような契約をしたとします。
- 通常のトラブルなら、1人か2人にパンを配るだけなので大丈夫。
- でも、大地震で100人全員が一度にパンを求めてきたら?
→ 材料も人手も全く足りません…。
これと同じことが、保険会社にも起きるのです。
💥 地震が起きると保険金の支払いが一気に集中する
火災保険なら、「Aさんの家だけが燃えた」などの個別対応がほとんどです。
でも地震だと、「地域全体」「数万人」が同時に被害に遭うことも。
これに対応するために、国(政府)と民間保険会社が一緒になって、
保険金の支払い能力を守る仕組みを作っているのです(=地震再保険制度)。
🚧 だから上限がある

保険金の上限(建物は5,000万円、家財は1,000万円)を設けることで、
- 保険制度が壊れないように守る
- 多くの人に最低限の補償が行き渡るようにする
という目的があります。
✨ 地震保険に上限がある理由まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 地震は一度に大勢が被害に遭う | → 通常の保険より支払いが集中しやすい |
| 保険制度を守るために上限がある | → みんなに行き渡るようにするため |
| 国と民間が一緒に支えている | → 特別な再保険制度が使われている |
「なぜ地震保険に制限があるのか」を理解しておくことで、
過剰な期待をせず、自分に必要な補償額を考えるヒントになりますね。
🔥 火災保険と🌏地震保険、それぞれの役割の違い
| 項目 | 火災保険 | 地震保険 |
|---|---|---|
| 補償される災害 | 火災、落雷、風災、水ぬれ、盗難など | 地震、噴火、津波による損害 |
| 加入方法 | 単独で契約できる | 火災保険に付帯して加入(単独では不可) |
| 補償の範囲 | 実際の損害額に応じて補償(最大で保険金額まで) | 全損・半損などの損害区分により定額支払い |
| 保険金の上限 | 契約者が自由に設定できる(上限なし) | 建物:5,000万円、家財:1,000万円まで |
| 運営 | 民間保険会社 | 国(政府)と民間の共同運営(地震再保険制度) |
✅ 火災保険の役割(=日常的な損害への備え)
火災保険は、日常的に起こりうるリスクに備えるものです。
- 台風で屋根が壊れた
- 火事で家具が焼けた
- 隣家の火災によるもらい火
こうした「個人単位の被害」に対して、損害額に応じて保険金が支払われるのが特徴です。
✅ 地震保険の役割(=大規模災害への最低限の補償)
一方、地震保険は想像以上に広範囲な損害が出る災害を想定しています。
- 地震で家が倒壊
- 津波で家財が流される
- 噴火による損壊
このようなときに備えて、被災直後の生活再建の足がかりとなるような最低限の補償を目的としています。

たとえば、全壊なら「地震保険で3000万円が支払われた」というような定額式で支給されるのが特徴です(ただし保険金額の範囲内で)。
💡補足のたとえ話:火災保険と地震保険は「かさ」と「防災リュック」

- 火災保険は、【毎日持ち歩く「傘」】のような存在。
→ 雨が降ってもすぐに対応できる、身近で使いやすい道具。 - 地震保険は、【めったに使わない「防災リュック」】のような存在。
→ 滅多に使わないけど、災害のときには命を守る大事な備え。
このように、目的も補償の性格も違うということを理解しておくと、保険の使い分けもイメージしやすくなります。
✨まとめ・今回の学び
- 地震保険は、火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内で設定する
- 上限は、建物5,000万円・家財1,000万円まで
- 火災保険では地震は補償されないため、地震保険の加入も重要
- 地震保険は政府と民間の共同運営で、補償に限度があるのが特徴
📝次回予告:普通傷害保険で補償されないものって何?
次回のテーマは、「普通傷害保険で補償されないものって何?」です。
たとえば、ケガをしたときに役立つ「普通傷害保険」。
ただし、この保険、どんなケガでも補償してくれるわけではありません。
「えっ、そんなケースは対象外なの?」と驚くような例もあるかもしれません。

試験でも引っかかりやすいポイントなので、しっかり整理しておきましょう‼️
どうぞお楽しみに😁



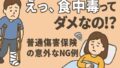
コメント