「利回りって、けっきょく何を見ればいいの?」
債券の問題に出てくる「表面利率」「利回り」「購入価格」…言葉だけだと難しく見えますが、仕組みは意外とシンプル。
今回は、ちょっと高めに買った債券の「単利最終利回り」を、一緒に計算しながら理解していきましょう!
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 債券とは何か?
- 債券の基礎用語の意味(今回の問題に絡むもの)
- 債券の単利最終利回りの計算方法
📘 今回の分野:金融資産運用/債権
今回学ぶ範囲は、金融資産運用/債券の範囲です。
特に、債券の単利最終利回りの計算内容について、何をしているのかしっかりと理解できるよう噛み砕いて解説します。
聞き慣れない用語もたくさん出てくるので、用語の意味を把握しながら学んでいきましょう‼️
❓️ 問題文の紹介
表面利率(クーポンレート)3%、残存期間6年の固定利付券を、額面100円当たり103円で購入した場合の単利最終利回りは、何%であるか?
求めるのは、最終的な利回りがいくらになるか。

初見では、どう計算したらいいのか全くわかりませんでした。
利息をもらって、最終的には買った金額より少ない金額で売る・・・
得しているのか損しているのか、どっちでしょう?
✅ 正解と解説の要点
表面利率(クーポンレート)3%、残存期間6年の固定利付券を、額面100円当たり103円で購入した場合の単利最終利回りは、何%であるか?
→解答:{3.0円+(100円−103円)/6年}/103円x100 ≒ 2.43%
答えの式だけ見ても、なんのことやらわかりません💦
この式の中で何をしているのか、一つ一つ確認していきます。
✅️ポイント解説
単利最終利回りは、
【年間利息 + 償還差益・損失 ÷ 残存年数】÷ 購入価格 × 100
で求められます。
この問題では…
- 年間利息:100円 × 3% = 3円
- 償還差損:100円(償還額)−103円(購入額) = -3円(つまり損失)
一年間あたりの償還差損:-3円 ÷ 6年 = -0.5円/年
合計:3円(年間利息) − 0.5円/年(償還差損) = 2.5円 - 利回り:2.5円 ÷ 103円 × 100 = 約2.43%
🔍 深掘り考察!!
表面利率が3%でも、「高い価格(103円)」で買ってしまうと、償還時に損をするため、実質的に受け取る利回りは下がってしまいます。
💡つまり、「いくらで買ったか」も利回りにとってはとても重要なんです。
このような市場価格と利回りの関係を知っておくと、債券の仕組みがグッと理解しやすくなります。
計算内容を詳しく見る前に、「債券とは何か」「債券の基礎用語」についてもおさらいしながら見ていきましょう。
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 債券とは何か?
- 債券の基礎用語の意味(今回の問題に絡むもの)
- 債券の単利最終利回りの計算方法
債券とは何か?

「債券(さいけん)」って、一言でいうと お金の貸し借りの“証文(しょうもん)”みたいなもの です。
ざっくり説明すると…
たとえば、あなたが「国」や「会社」にお金を貸したいと思ったとしましょう。
そのとき、「国債」や「社債」といった債券を買うことで、お金を貸したことになります。
つまり、
💬「このお金、あとで利子(=利息)をつけて返すから、今貸してね」
という約束を、紙(=証券)やデータの形にしたものが「債券」です。
債券の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行者 | 国、地方自治体、企業など(お金を借りたい人) |
| 買う人 | 投資家や一般の人(お金を貸す人) |
| もらえるもの | 毎年の利息と、満期になったときのお金(元本) |
| 安全性 | 国が発行する「国債」は特に安全とされている |
たとえで言うなら…
「債券」は、
友だちにお金を貸して、「1年後に1割増しで返してね」と約束したメモ
みたいなイメージです。
注)友達とのお金の貸し借りはやめようね😉
ただ、相手が友だちじゃなくて、「国」や「トヨタ」みたいな大きな会社になるわけですね。
債券の基礎用語の意味(今回の問題に絡むもの)
今回の債券の問題に出てくる用語を以下にまとめました。
✅ 表面利率(ひょうめんりりつ)=クーポンレート
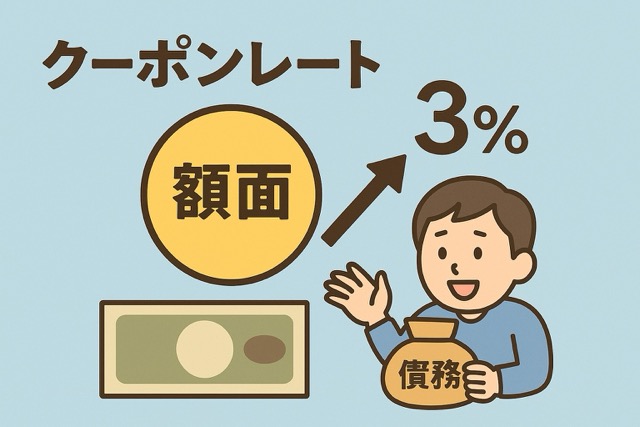
「毎年もらえる利息が、元のお金(額面)に対して何%か?」という割合です。
🔸 たとえば…
額面100円の債券で、毎年3円の利息(クーポン)が出るなら…
👉 表面利率 = 3%
これは「元本100円に対して、毎年3円もらえるよ」という“契約時の利回り”です。
※買う価格が100円とは限らないので、実際の儲けとは別です。
✅ 残存期間(ざんぞんきかん)
「その債券が満期になるまで、あと何年あるか?」という期間のことです。
🔸 たとえば…
・10年の債券を4年持ったら、
👉 残りは 6年 → 残存期間6年
この「残りの時間」があるから、何年分の利息がもらえるかが決まります。
✅ 固定利付債券(こていりつきさいけん)
「毎年決まった金額の利息がもらえるタイプの債券」のことです。
🔸 たとえば…
表面利率3%の債券なら、どんな景気のときでも
👉 毎年3円ずつ利息がもらえる、という意味です。
これと反対に、景気によって利息が変わるものは「変動利付債券」と呼ばれます。
✅ 単利最終利回り(たんり・さいしゅう・りまわり)
「買ったときの価格と、受け取る利息、満期の額面をもとにした、1年あたりの平均的な儲け率」のことです。
🔸 ポイント:
- 単利=利息を「複利(利息に利息)」で増やさず、「毎年一定」でカウントする考え方。
- 最終利回り=満期までずっと持ち続けたときの利回り。
🔸 たとえば…
表面利率4%の債券を「105円」で買って、5年間保有した場合、
・毎年の利息による利益:毎年4円(額面100円に対する4%)×5年=20円/年(利息)
・一年あたりの値上がり益:105円で買った債券を5年後に売却
一年あたり(100円(額面)−105円)/5年=−0.1円/年 の益(=損失)
→【毎年の利息による利益】【一年あたりの値上がり益】これら差もふまえて、【年平均でどれだけ得したか?】を出すのが「単利最終利回り」です。
用語のまとめ
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 表面利率 | 額面に対して、毎年もらえる利息の割合 |
| 残存期間 | 満期まであと何年あるか |
| 固定利付債券 | 利息が毎年固定されている債券 |
| 単利最終利回り | 債券の購入価格と満期までの利息をもとに計算する実質的な年平均利回り(単利ベース) |
債券の単利最終利回りの計算方法
今回の問題の計算において、どこで躓くのかわかりやすくするために、ステップ毎に立ち止まって確認していきましょう。
🔍 ステップ①:「毎年もらえる利息(クーポン)」を確認
- 額面:100円
- 表面利率:3%
👉 100円 × 3% = 3円/年 :一年あたりの利息
🔍 ステップ②:保有期間中にもらえる「利息の合計」を計算
- 残存期間:6年
- 毎年もらえる利息:3円/年
👉 3円/年 × 6年 = 18円
🔍 ステップ③:「満期に戻ってくる額面」との差額を確認
- 購入価格:103円
- 満期に戻ってくる金額:100円(←額面どおり)
👉 103円 − 100円 = 3円の損
利息は18円もらえますが、元本で3円損してるので
👉 18円 − 3円 = 実質の利益は15円
🔍 ステップ④:「1年あたりの利益(単利)」を出す
- 実質の利益:15円
- 保有期間:6年
👉 15円 ÷ 6年 = 2.5円/年 :一年あたりの儲け
🔍 ステップ⑤:「購入価格」に対する利回りを出す
- 年間の利益:2.5円
- 購入価格:103円
👉 2.5円 ÷ 103円 ≒ 0.02427… x100 → 約2.43%
✅ 答え:単利最終利回りは 約2.43%
🎓 補足:「利回り」って何のために出すの?
投資家が「この債券、買っていいか?」を判断するために
「実際どれだけ儲かるか?」をわかりやすくする指標が利回りなんです。

🧾 計算式(おさらい)
単利最終利回り=(利息合計−元本の損失)/(購入価格×年数)
まとめ・今回の学び
- 債券とは満期時に「いくらの利息をつけて返す」という約束のメモのようなもの。
- 債券にかかわる基礎的な用語をおさらいしました。
- 単利最終利回りの計算は1ステップずつの意味を理解しておきましょう。
次回予告:リターン2倍⁉ベンチマーク連動ファンドの正体とは?
先物取引やオプション取引などを活用して、日経平均やTOPIXなどのベンチマーク指数の2倍や3倍の値動きを目指すファンドがあります。
このようなハイリスク・ハイリターンな投資信託は、いったい何という種類のファンドに分類されるのでしょうか?
「派手に儲かりそうだけど、裏があるの…?」

そんな疑問にもお答えしながら、
あの○○型ファンドの特徴や注意点をわかりやすく解説します‼️
お楽しみに☺️




コメント