住宅ローンを使ってマイホームを購入すると、一定の条件を満たせば「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」が受けられます。
この控除は税金が戻ってくるため、多くの人にとって大きな節約効果がありますが、適用を受けるためには細かな条件があります。
今回は、「返済期間は20年以上じゃないとダメ?」という、試験でも出やすいポイントについて解説します。
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 住宅ローン控除の適用条件とは?
→4つの要件(①住宅、②居住、③ローン、④所得)があります。 - 住宅ローン控除の控除率について
→控除率は0.7%_年末のローン残高に控除率を掛けた金額が控除額です。 - 住宅ローン控除適用条件以外のポイント
→計算ルール、控除期間、借入金の上限、繰上返済の注意点、控除を受けるための手続きなどについて注意が必要です。
📘 今回の分野:タックスプランニング/税額計算と税額控除【住宅ローン控除】
今回学ぶ範囲は、タックスプランニング分野の「住宅ローン控除」についてです。
「住宅購入」は人生の中で一番高い買い物です。
住宅購入の際に住宅ローンを利用する場合、住宅借入金等特別控除(住宅ローン)というお得な制度があります。
この制度がどういったものなのか、しっかり理解していこうと思います。
❓️ 問題文の紹介
住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、20年以上でなければならない。
◯か✗か?
さて、今回の要点は借入金の償還期間が何年なのかという点ですね。
問題文は「20年」とあります。
私の今回の思考回路は、

借入金(住宅ローン)って35年とかよく聞くよね。
だから20年くらいあるんじゃない?
という感じでした。
住宅ローンを何年借りるかと、住宅ローン控除を受けるための条件(償還期間)は違うということを理解していなかったため、不正解となりました。
正しい知識を身につけるため、正解を確認しましょう‼️
✅ 正解と解説の要点
住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、20年以上でなければならない。
◯か✗か?
→正解:✘(10年)
正解は ✗ でした。
注目すべき点は合っていましたが、償還期間が何年必要なのかまでは理解できていませんでした。
正解のポイントを確認しましょう。
✅️ポイント解説
- 住宅ローン控除の返済期間要件は 10年以上 が正しい。
- 20年以上という条件はなく、10年以上あれば適用条件を満たす。
- この「返済期間10年以上」という条件は、住宅ローン控除が「長期的に住むための住宅取得を対象」にしているから。
🔍 深掘り考察!!
今回は、以下の3点について解説していきたいと思います。
- 住宅ローン控除の適用条件とは?
→4つの要件(①住宅、②居住、③ローン、④所得)があります。 - 住宅ローン控除の控除率について
→控除率は0.7%_年末のローン残高に控除率を掛けた金額が控除額です。 - 住宅ローン控除適用条件以外のポイント
→計算ルール、控除期間、借入金の上限、繰上返済の注意点、控除を受けるための手続きなどについて注意が必要です。
住宅ローン控除の適用条件とは?

①+②対象となる「住宅と居住」の条件
- 床面積:
原則50㎡以上で、1/2以上が自己居住用であること。
(令和4年以降、省エネ基準を満たす住宅や一定の中古住宅は40㎡以上でもOK) - 居住要件:
購入後6か月以内に住み始め、その年の12月31日まで住み続けること。 - 中古住宅の場合の要件:
新耐震基準適合住宅であること。
③「ローン」の条件
- 返済期間:10年以上
- 対象の借入金:銀行や住宅金融支援機構など、適法な金融機関等からの借入であること
(親族や知人からの借金は対象外) - 返済方法:元金と利息を分割して返済すること
④「所得」制限
- 年間の合計所得金額が 2,000万円以下
(超えると控除は受けられません)
その他の注意点
- 増改築やリフォームも条件を満たせば対象になります。
(耐震・省エネ・バリアフリー改修など) - 控除期間や控除率は取得した年や住宅の性能によって異なります。
- 繰り上げ返済で期間が10年未満になると、残りの年は控除が受けられなくなる可能性あります。
適用条件のポイントまとめ
- 面積:原則50㎡以上(条件付きで40㎡以上もOK)、1/2以上を自己居住用とすること
- 返済期間:10年以上
- 所得:2,000万円以下
- 所定の居住要件満たすこと
(購入後6か月以内に住み始め、その年の12月31日まで住み続けること。)
住宅ローン控除の控除率について
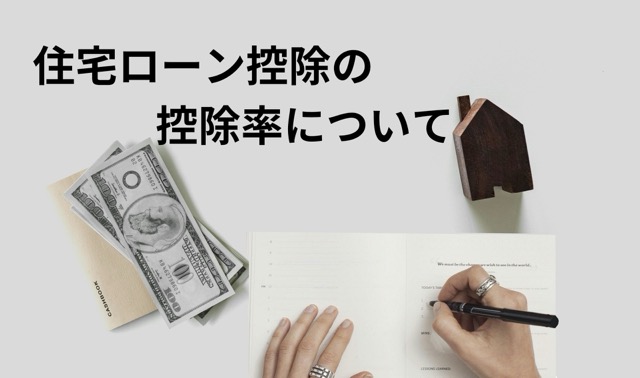
住宅ローン控除の控除率とは?
住宅ローン控除は、住宅ローン残高の一定割合を『所得税から直接引く(税額控除)』制度です。
つまり、計算で出た金額分、税金が安くなります。
控除率は住宅の取得時期や種類で変わりますが、令和4年以降の新制度ではおおむね次の通りです。
| 住宅の種類 | 控除率 | 控除期間 |
|---|---|---|
| 認定住宅(省エネ・長期優良など) | 年末残高の0.7% | 原則13年間 |
| 一般住宅(省エネ基準を満たさない) | 年末残高の0.7% | 原則10年間 |
| 中古住宅 | 年末残高の0.7% | 原則10年間 |
※上限となる借入金残高にも制限があります(例:一般住宅は4,000万円、認定住宅は5,000万円など)。
具体例で計算してみる
条件
- 一般住宅(省エネ基準なし)を令和6年に新築
- 借入額:3,500万円
- 金利:1.0%(35年ローン)
- 年末残高(1年目):3,400万円
- 控除率:0.7%
- 控除期間:10年間
- 所得税額:25万円/年(住民税額:20万円)
計算の流れ(1年目)
- 年末ローン残高 × 控除率
3,400万円 × 0.7% = 23万8,000円 - 所得税から控除
所得税額(25万円) > 控除額(23万8,000円)なので全額控除可能。
25万円 − 23万8,000円 = 所得税残額 1万2,000円 - 住民税からの控除(※所得税で控除しきれない場合のみ)
→ 今回は所得税で全額控除できたため、住民税控除はなし。
仮に所得税が少ない場合(例:所得税10万円)
- 所得税で10万円控除
- 残り 23万8,000円 − 10万円 = 13万8,000円 を住民税から控除可能(上限あり:13万6,500円)
- 住民税から控除できるのは上限までです。
控除率のポイントまとめ
- 控除率は原則0.7%(以前は1.0%でしたが、令和4年以降引き下げ)
- 控除額は年末ローン残高に控除率を掛けて計算
- 所得税から引ききれない場合は住民税からも控除できる(ただし上限あり)
- 年末ローン残高が大きい初期ほど控除額も大きく、年を追うごとに減っていく
住宅ローン控除適用条件以外のポイント
住宅ローン控除を利用する際に、適用条件以外で重要となるポイントを以下にまとめました。
「控除額」については前段で触れていますが、おさらいとして再度確認していきましょう。
控除額の計算ルール
- 計算式:
年末ローン残高 × 控除率(原則0.7%) - 控除できるのは所得税額の範囲内(残りは住民税から控除可能、上限あり)
- 控除額は年々減っていく(ローン残高が減るため)
控除期間と住宅の性能
- 控除期間は住宅の種類・性能によって変わる
- 認定住宅(長期優良住宅・ZEH等):最大13年
- 一般住宅:最大10年
- 認定住宅(長期優良住宅・ZEH等):最大13年
- 「13年控除」は新築で省エネ性能を満たした場合のみ
控除対象となる借入金の上限
- 上限額は住宅の性能や取得時期で異なる
- 認定住宅:5,000万円
- 一般住宅:4,000万円
- 認定住宅:5,000万円
- 上限を超えるローンを組んでも、控除計算に使えるのは上限まで
繰上げ返済の注意点
- 返済期間が10年未満になると、以後の控除は受けられない
- 早期完済の予定がある場合は制度のメリットが減る可能性あり
他の税制優遇との併用
- すまい給付金とは併用可能(ただし収入制限あり)
- 住宅取得資金の贈与非課税制度とも併用可能(ただし住宅ローン控除額が減る場合あり)
控除を受けるための手続き
- 初年度は確定申告が必要(給与所得者も)
- 2年目以降は年末調整でOK(勤務先に必要書類を提出)
中古住宅や増改築の場合の特例
- 中古住宅でも耐震基準を満たせば適用可能
- バリアフリー改修、省エネ改修、耐震改修などの増改築も対象(条件あり)
所得税と住民税の関係
- 控除しきれなかった分は翌年の住民税から引く(上限:13万6,500円)
- 所得税額が少ない人でも、一定の節税効果は得られる
住宅ローン適用条件以外のポイントまとめ
住宅ローン控除を最大限活用するには、
- 条件を満たす住宅・借入期間を選ぶ
- 控除額・期間・上限を理解する
- 繰上げ返済や他制度との併用の影響を確認する
が大切です。
まとめ・今回の学び
- 住宅ローン控除の適用条件とは?
→4つの要件(①住宅、②居住、③ローン、④所得)があります。
①面積:原則50㎡以上(条件付きで40㎡以上もOK)
1/2以上を自己居住用とすること
②居住要件:購入後6か月以内に住み始め、その年の12月31日まで住み続けること。
③ローン返済期間:10年以上
④所得:2,000万円以下 - 住宅ローン控除の控除率について
→控除率は0.7%_年末のローン残高に控除率を掛けた金額が控除額です。
①控除額は年末ローン残高に控除率0.7%を掛けて計算
②所得税から引ききれない場合は住民税からも控除可能(ただし上限あり)
③年末ローン残高が大きい初期ほど控除額も大きく、年を追うごとに減少 - 住宅ローン控除適用条件以外のポイント
→計算ルール、控除期間、借入金の上限、繰上返済の注意点、控除を受けるための手続きなどについて注意が必要です。
①条件を満たす住宅・借入期間を選択
②控除額・期間・上限を理解
③繰上げ返済や他制度との併用の影響を確認
住宅ローン控除に関する要点をまとめました。
住宅ローン絡みでわからないことがあれば、ここに立ち戻って確認しましょう‼️
次回予告:純損失の繰越控除について
青色申告をしていると、事業で赤字(損失)が出た年でも、他の所得と損益通算して税金を軽くできる場合があります。
しかし、それでも控除しきれない損失が残ったらどうなるのでしょうか?
実は、一定の条件を満たせば、その損失(純損失)を翌年以降に繰り越して、将来の黒字と相殺できる制度があります。

「繰越控除」ができる期間は何年間なのか、次回は詳しく解説します。
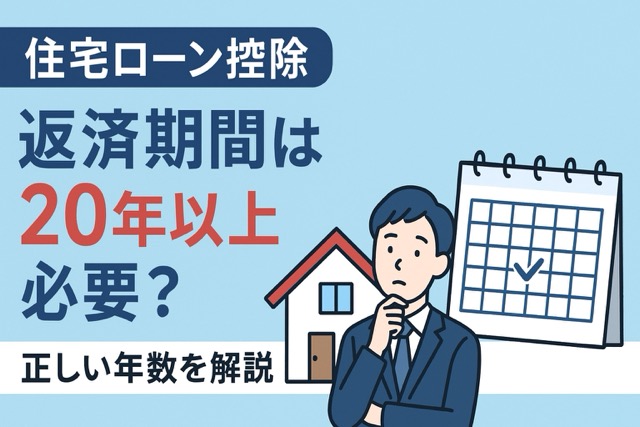



コメント