宅建業法の問題は、宅地建物取引士試験だけでなく、FP試験でも登場する重要なテーマです。
特に「専任媒介契約」の有効期間については、よくひっかけ問題が出題されるポイントです。
今回は、その内容を整理して解説していきます。
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の4点です。
- 宅地建物取引業法(以下、宅建業法)ってどういう法律?
→不動産の売買や賃貸を業務として行う会社や人にルールを定めた法律です。 - 媒介契約って何?
→不動産の売買や賃貸をしたい人が、不動産会社に仲介を依頼するために結ぶ契約のことです。 - 媒介契約って専任媒介以外にどういうモノがあるの?どう使い分ける?
媒介契約には、大きく分けて次の3つがあります。- 一般媒介契約_自由度を重視
- 専任媒介契約_バランス型
- 専属専任媒介契約_安心・スピード重視
- なぜ3ヶ月という契約の有効期間が設けられているのか?
→依頼者(売主や買主)を守るため。
不動産業者に適度な競争を促すため。
📘 今回の分野:不動産/不動産取引

今回は不動産取引における宅地建物取引業法(宅建業法)や、媒介契約について学んでいきたいと思います。
字面だけ見ると、なんとなく建物に関することなんだろうな、ということはわかると思います。
ただし、その中身を理解してこそ意味があります。
今回も具体例を示しながら詳しく解説していきますので、一緒に確認していきましょう。
❓️ 問題文の紹介
宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で6カ月である。
◯か✘か?
文章を見る限り、問われているのは期間が6ヶ月なのかどうかという点です。
単純に有効期間を把握していませんでした。
有効期間を決めている理由や背景を知れば、正しい知識が身につくと思います。
正解を確認しましょう‼️
✅ 正解と解説の要点

宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で6カ月である。
◯か✘か?
→正解:✘
正解は✗です。
問われている点はやはり有効期間です。
6ヶ月でないのであれば、何ヶ月と決められているのか。

確認していきましょう☺️
✅️ポイント解説
- 専任媒介契約の有効期間は「最長3カ月」と宅建業法で定められています。
- 依頼者と業者が合意しても有効期間を6カ月に延長することはできません。
- ただし、契約を更新することは可能で、その際も1回の更新につき最長3カ月が上限です。
- 一般媒介契約は有効期間の制限がなく、専任媒介契約・専属専任媒介契約だけが「最長3カ月」と定められている点がポイントです。
🔍 深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 宅地建物取引業法(以下、宅建業法)ってどういう法律?
→不動産の売買や賃貸を業務として行う会社や人にルールを定めた法律です。 - 媒介契約って何?
→不動産の売買や賃貸をしたい人が、不動産会社に仲介を依頼するために結ぶ契約のことです。 - 媒介契約って専任媒介以外にどういうモノがあるの?どう使い分ける?
媒介契約には、大きく分けて次の3つがあります。- 一般媒介契約_自由度を重視
- 専任媒介契約_バランス型
- 専属専任媒介契約_安心・スピード重視
- なぜ3ヶ月という契約の有効期間が設けられているのか?
→依頼者(売主や買主)を守るため。
不動産業者に適度な競争を促すため。
宅地建物取引業法ってどういう法律?

宅地建物取引業法とは、不動産の売買や賃貸を業務として行う会社や人にルールを定めた法律です。
目的は、取引をする人(家を買う人や借りる人)が不利益を被らないように保護し、また不動産業界の健全な運営を守ることです。
要するに、
「不動産屋さんが勝手に好き放題してトラブルにならないようにする法律」
です。
具体例で説明
例1:手付金を持ち逃げされないようにする
もし不動産業者が、お客さんから何百万円もの手付金を預かって、そのまま倒産してしまったら大変ですよね。
宅地建物取引業法では、保証金(供託金)を法務局に預ける義務があり、お客さんのお金を守る仕組みがあります。
例2:重要なことを説明する義務
マンションを買おうとしたとき、
- 「実は耐震性に問題がある」
- 「将来立ち退きが必要になる」
こういう大事なことを隠されたら大損です。
そこで宅建業法では、宅地建物取引士(宅建士)という資格を持つ人が『重要事項説明』をすることを義務付けています。

これによって、お客さんは大事なリスクを知ったうえで判断できます。
例3:媒介契約のルール
「専任媒介契約は最長3カ月まで」と決まっているのもこの法律の内容です。
これも、お客さんが特定の不動産会社に縛られすぎて不利にならないようにするための規定です。
宅建業法がないとどうなるか?
- 不動産業者が手付金を勝手に流用してしまう
- 買主に不利な条件を隠したまま契約させる
- 一部の業者が市場を独占して価格操作をする
こうした問題が起きやすくなります。

宅建業法は、それを防ぐための「ルールブック」の役割を果たしています。
宅建業法について_ポイントまとめ
- 宅地建物取引業法は、不動産業者の行動ルールを決めた法律
- 目的は「取引の安全」と「消費者の保護」
- 代表的な仕組みは「供託金制度」「重要事項説明」「媒介契約のルール」
媒介契約って何?

不動産の売買や賃貸をしたい人が、不動産会社に仲介を依頼するために結ぶ契約のことです。
簡単にいうと、
「お客さん(売りたい・買いたい人)」と「不動産会社」が結ぶ“お願いの約束”です。
「レストランで料理を頼むように、不動産を“売る・買う・借りる”ときは、不動産会社に“仲介をお願いする契約=媒介契約”をする」

というイメージを持っていただければ、理解しやすいです。
具体例1:自宅を売りたい場合
Aさんが「自分の家を売りたい」と思ったとします。
しかし、Aさん自身で買い手を探すのは大変です。そこで不動産会社Bに頼んで、
「代わりに買い手を探して契約までサポートしてね」
という約束を結びます。
→ これが「媒介契約」です。
具体例2:マンションを借りたい場合
Cさんが「駅近の1LDKマンションを借りたい」と思ったとき、不動産会社Dに相談します。
「条件に合う物件を探して、貸主との契約をまとめてね」
とお願いするのも「媒介契約」です。
媒介契約の種類
媒介契約には大きく3種類あります。
- 一般媒介契約
- 複数の不動産会社に同時に依頼できる
- 自分で買い手を見つけてもOK
- 例:「とにかく早く売りたいから、3社に同時にお願いする」
- 複数の不動産会社に同時に依頼できる
- 専任媒介契約
- 1社だけに依頼する
- 自分で買い手を見つけるのはOK
- 例:「信頼できる1社にだけ頼んで、報告もしてもらう」
- 1社だけに依頼する
- 専属専任媒介契約
- 1社だけに依頼する
- 自分で買い手を見つけてもダメ(必ずその会社を通さないといけない)
- 例:「不動産会社に完全に任せたい」
- 1社だけに依頼する
なぜ媒介契約が必要なのか?
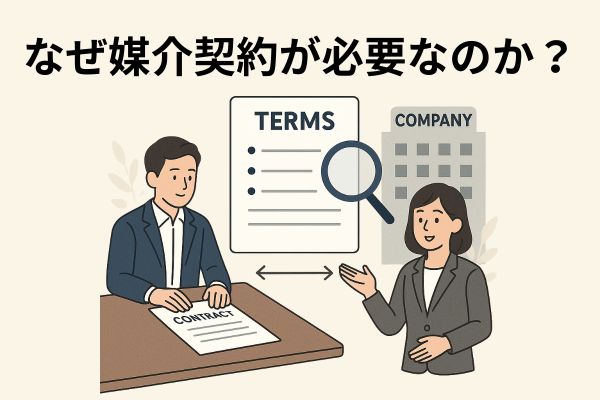
- 依頼者の権利を守るため
どの会社に、どんな条件でお願いしているのかを明確にしてトラブルを防ぐ。 - 不動産会社の義務を明確にするため
例えば「専任媒介契約」なら、業者は定期的に活動状況を報告する義務があります。
媒介契約について_ポイントまとめ
- 媒介契約とは「不動産取引の仲介をお願いする契約」
- 売りたい人・借りたい人が不動産会社と結ぶ
- 種類は「一般」「専任」「専属専任」の3つ
- 依頼者の保護と、不動産会社の義務明確化が目的
媒介契約って専任媒介以外にどういうモノがあるの?どう使い分ける?

媒介契約には、大きく分けて次の3つがあります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
それぞれ、依頼者と不動産会社との「縛りの強さ」が違います。
① 一般媒介契約
- 特徴
- 複数の不動産会社に同時に依頼できる
- 自分で買主や借主を見つけても契約できる
- 報告義務はない(不動産会社から活動報告が必ず来るわけではない)
- 複数の不動産会社に同時に依頼できる
- メリット
- 多くの会社に依頼できるので、買い手が見つかりやすい
- 自分でも動ける自由度がある
- 多くの会社に依頼できるので、買い手が見つかりやすい
- デメリット
- 不動産会社にとっては「他社に取られるかも」と思うので、本気度が下がりやすい
- 報告義務がないため、依頼者は進捗が見えにくい
- 不動産会社にとっては「他社に取られるかも」と思うので、本気度が下がりやすい
- 具体例
→「とにかく早く売りたいから、複数の不動産会社に同時にお願いしたい」
→「知り合いにも声をかけて、自分で買い手を見つける可能性も残したい」
② 専任媒介契約
- 特徴
- 1社だけに依頼する
- 自分で買主や借主を見つけることはできる(その場合も不動産会社を通す)
- 不動産会社には2週間に1回以上の報告義務がある
- 有効期間は最長3カ月
- 1社だけに依頼する
- メリット
- 1社が責任をもって動いてくれる
- 依頼者は進捗を定期的に知ることができる
- 1社が責任をもって動いてくれる
- デメリット
- 他の会社に同時依頼できないので、販売経路が狭くなる場合もある
- 他の会社に同時依頼できないので、販売経路が狭くなる場合もある
- 具体例
→「信頼できる不動産会社があるから、そこに集中して任せたい」
→「でも自分でも買い手を探しているので、両方の可能性を残したい」
③ 専属専任媒介契約
- 特徴
- 1社だけに依頼する
- 自分で買主や借主を見つけても、その不動産会社を通さないと契約できない
- 不動産会社には1週間に1回以上の報告義務がある
- 有効期間は最長3カ月
- 1社だけに依頼する
- メリット
- 不動産会社は「完全に任された」と思うので、最も力を入れて販売活動してくれる
- 報告頻度が多く安心感がある
- 不動産会社は「完全に任された」と思うので、最も力を入れて販売活動してくれる
- デメリット
- 自分で買主を見つけても必ず仲介手数料がかかる
- 不動産会社を選び間違えると身動きがとれない
- 自分で買主を見つけても必ず仲介手数料がかかる
- 具体例
→「仕事が忙しくて自分で動く余裕はないから、不動産会社に完全に任せたい」
→「早く確実に売却したいので、業者にフルパワーで頑張ってほしい」
どう使い分ける?
- 自由度を重視する人 → 一般媒介契約
→ 複数業者に依頼したい、知り合い経由で買い手が見つかる可能性がある場合 - バランス型 → 専任媒介契約
→ ある程度不動産会社に集中してもらいつつ、自分でも動きたい人 - 安心・スピード重視 → 専属専任媒介契約
→ 早く売りたい、完全に任せたい、進捗を細かく知りたい人
媒介契約の種類と使い分け_まとめ
- 媒介契約には「一般」「専任」「専属専任」の3種類がある
- 違いは「依頼できる業者の数」「自分で見つけられるか」「報告義務の有無・頻度」
- 依頼者が 自由度を取るか、安心感を取るか で選び方が変わる
なぜ3ヶ月という契約の有効期間が設けられているのか?

有効期間3カ月の理由
宅地建物取引業法で 専任媒介契約・専属専任媒介契約は最長3カ月 と定められています。
これには大きく2つの目的があります。
- 依頼者(売主や買主)を守るため
- もし有効期間が長すぎると、不動産業者が「どうせ他の業者に取られない」と安心してしまい、販売活動を手を抜くリスクがあります。
- 依頼者は長期間縛られることになり、不利な状況に陥る可能性があります。
- もし有効期間が長すぎると、不動産業者が「どうせ他の業者に取られない」と安心してしまい、販売活動を手を抜くリスクがあります。
- 不動産業者に適度な競争を促すため
- 3カ月ごとに契約を見直せるので、業者は「結果を出さないと次は更新してもらえない」と考え、一生懸命に営業活動をします。
- 依頼者は業者を比較して、信頼できる会社を選び直すことができます。
- 3カ月ごとに契約を見直せるので、業者は「結果を出さないと次は更新してもらえない」と考え、一生懸命に営業活動をします。
なぜ「6カ月や1年」ではないのか?
- 長すぎると依頼者が不利
→ 「専属専任契約」で1年縛られると、もし担当者がやる気を失っても他に変えられません。 - 短すぎると業者が活動しづらい
→ 1カ月などでは広告活動や販売活動の成果が出る前に契約が切れてしまいます。

そのため、3カ月が「依頼者保護」と「業者の活動期間」のバランスが良いと判断されたのです。
例1:もし6カ月だったら
Aさんがマンションを売りたいと不動産会社に専任媒介契約を依頼。
ところが担当営業があまり熱心に動かず、3カ月たっても内見すら入らない…。
でも契約が6カ月なら、Aさんはあと3カ月も待つしかなくなります。
例2:3カ月だからこそ
同じ状況でも、3カ月で契約を見直せるため、
「別の不動産会社に切り替えよう」と判断できる。
これが依頼者の保護につながります。
更新はできる
- 「最長3カ月」ですが、更新は可能です。
- つまり「まず3カ月 → 結果がよければ更新」という仕組みになっており、依頼者に選択肢が残されます。
契約の有効期間が3ヶ月である理由_まとめ
- 専任媒介契約・専属専任媒介契約が 最長3ヶ月 と決まっているのは、
① 依頼者を不利にしないため
② 不動産業者のやる気を維持させるため - 3カ月という期間は「短すぎず・長すぎず」の絶妙なバランス
- 契約は更新できるので、依頼者は状況を見て判断可能
まとめ・今回の学び
- 宅地建物取引業法(以下、宅建業法)ってどういう法律?
→不動産の売買や賃貸を業務として行う会社や人にルールを定めた法律です。 - 媒介契約って何?
→不動産の売買や賃貸をしたい人が、不動産会社に仲介を依頼するために結ぶ契約のことです。
宅建業法、媒介契約ともに、依頼者の保護と、不動産会社の義務明確化が目的となっています。 - 媒介契約って専任媒介以外にどういうモノがあるの?どう使い分ける?
媒介契約には、大きく分けて次の3つがあります。- 一般媒介契約_自由度を重視
- 専任媒介契約_バランス型
- 専属専任媒介契約_安心・スピード重視
依頼者が 自由度を取るか、安心感を取るか で選び方が変わります。
- なぜ3ヶ月という契約の有効期間が設けられているのか?
→依頼者(売主や買主)を守るため。
不動産業者に適度な競争を促すため。
3カ月という期間は「短すぎず・長すぎず」の絶妙なバランスになっています。
宅地建物取引業法、媒介契約について解説しました。
一度で完全に理解は出来なくても、なんとなくはイメージできたのではないでしょうか?

忘れてしまったら、また見に来てくださいね☺️
次回予告:売買契約の手付金について
次回は「宅地建物取引業法」に関するもう一つの重要なルールを取り上げます。
「宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領することができない。」
果たしてこの記述は正しいのでしょうか?
不動産取引における「手付金の制限」は、消費者を守るための大事な仕組みです。
このルールの背景と具体的な実務での意味を詳しく解説していきます。

次回もお楽しみに‼️
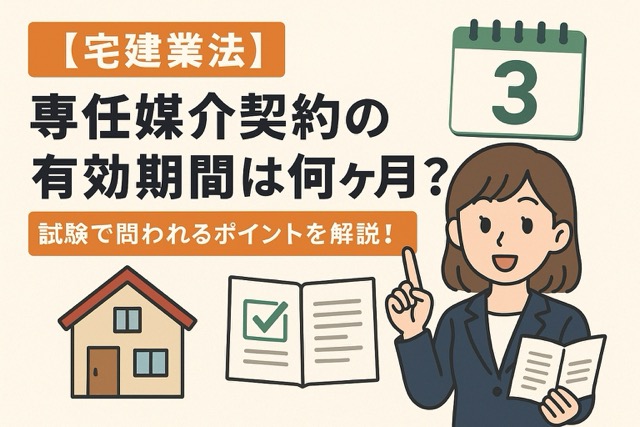



コメント