不動産を売却したときに大きな節税効果をもたらす「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」。
FP試験でも頻出のテーマですが、適用条件には細かいルールがあります。
今回は「適用を受けるためには10年以上所有していなければならない」という一見もっともらしい設問を題材に、正解とポイントを確認していきます。
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」とはなにか?
→ 自分が住んでいた家や土地を売ったとき、利益(もうけ)が出ても、その利益から最大3,000万円までを差し引いてくれる制度です。 - 所有期間の制限がある特例とは?
→1.軽減税率の特例
2.取得費加算の特例 - 他の制度との併用の可否について
→3,000万円控除 × 軽減税率の特例 → 併用できます。
📘 今回の分野:不動産の税金

今回は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」について解説していきたいと思います。
3,000万円の特別控除を受けるには、どのような要件があるのか。
他の制度との併用は可能なのか、など。
この記事では、不動産を譲渡する際に損しないような知識を身につけることができます。
FP試験の対策をしつつ、実生活でも活用しやすく、イメージしやすいように具体例説明していきますね。
まずは問題の確認からです。
❓️ 問題文の紹介
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。
◯か✗か?

3000万円もの控除を受けるんだから、10年の所有期間はようけんとしてあるんじゃない?
と思い、◯を選択しました。
まぁ、間違えたわけですが。。。
そもそも3000万円の特別控除が、どのようなシュチュエーションで発生するのか、いまいちイメージが掴めていなかったように思います。
そのあたりも詳しく確認が必要ですね。
✅ 正解と解説の要点

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。
◯か✗か?
→正解:✘(誤りです。)
正解は✘。
誤りの文章でした。
この問題文で問われているのは、「10年を超えていなければならない」かということでした。
この「3,000万円の特別控除」を受けるためには、所有期間が要件に無いようです。
詳しくは以降のポイント解説で確認していきましょう‼️
✅️ポイント解説
- 「3,000万円の特別控除」には所有期間の長短に関わらず適用できるのが大きな特徴です。
- 一方で「軽減税率の特例(長期譲渡所得の課税特例)」については所有期間が10年を超えていることが条件となります。
- つまり、設問は他の特例の条件を混同させる典型的なひっかけ問題です。
🔍 深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」とはなにか?
→ 自分が住んでいた家や土地を売ったとき、利益(もうけ)が出ても、その利益から最大3,000万円までを差し引いてくれる制度です。 - 所有期間の制限がある特例とは?
→1.軽減税率の特例
2.取得費加算の特例 - 他の制度との併用の可否について
→3,000万円控除 × 軽減税率の特例 → 併用できます。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」とはなにか?

一言でいうと、
自分が住んでいた家や土地を売ったとき、利益(もうけ)が出ても、その利益から最大3,000万円までを差し引いてくれる制度です。

税金は「もうけ」に対してかかります。
だから、もし家を売って2,000万円の利益が出たとしても、3,000万円控除を使えば課税される利益はゼロになります。
どうしてこんな特例があるの?
マイホームを売るときには「住み替え」や「生活の事情」が多く関わります。
・転勤で引っ越さないといけない
・家族が増えて手狭になった
・高齢でバリアフリーの住宅に住み替える
こういう場合に「短期間しか住んでいないのに大きな税金がかかる」となると、生活に負担が大きすぎます。

そこで国は「マイホームの売却に限っては特別に税金を軽くしますよ」という制度を作ったのです。
具体例で考えてみよう
例1:控除を使わない場合
- Aさんは10年前に2,000万円でマイホームを買いました。
- その家を5,000万円で売りました。
👉 もうけ(譲渡所得)は 5,000万 − 2,000万 = 3,000万円
この3,000万円に税金がかかります。

所得税・住民税あわせて約600万円くらい取られるイメージです。
例2:3,000万円控除を使った場合
- 上と同じ条件で3,000万円のもうけが出たとします。
- でも「居住用財産の3,000万円控除」を使うと…
👉 3,000万円(利益) − 3,000万円(控除) = 0円

課税される利益がゼロになるので、税金もかかりません!
ポイント整理
- マイホーム(住んでいた家や土地)を売ったときだけ使える
- 利益から最大3,000万円まで差し引ける
- 所有期間は関係ない(短くてもOK)
- ただし、一生のうち何回でも使えるわけではなく、同じ人は2回目以降は原則使えないルールがあります
3000万円の特別特例_まとめ

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」とは、
マイホームを売って利益が出ても、そのうち3,000万円までは税金がかからない、生活を守るための制度です。
👉 覚え方:
「マイホーム売却 → 利益から最大3,000万円分が“なかったこと”にできる」
所有期間の制限がある特例とは?
「居住用財産の3,000万円控除」は所有期間の長さに関係なく使える制度でしたが、世の中には「所有期間が○年以上じゃないとダメ」という制限がある特例もあります。
ここを混同すると試験でひっかかりやすいです。
代表的なのは次の2つです。
- 長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(取得費加算の特例)
今回は特に試験でよく問われる ①軽減税率の特例 を中心に解説します。
① 軽減税率の特例とは?

マイホームを売ったとき、所有期間が10年を超えていると税率が軽くなる制度です。
ふつう、家や土地を売って利益が出ると、
- 所得税15%
- 住民税5%
(合計20%+復興特別税)
がかかります。
でもこの特例を使えると、
利益のうち6,000万円まで → 所得税10%・住民税4%(合計14%+復興税)
に下がります。
具体例でイメージしよう
例1:所有期間が10年以下
Bさんは、マイホームを買って8年後に売りました。
- 利益(譲渡所得):2,000万円
- 所有期間:8年

この場合は 軽減税率の特例は使えません。
税率20%で計算 → 税金は約400万円。
例2:所有期間が10年を超える
同じ条件でBさんがマイホームを12年所有して売ったとします。
- 利益(譲渡所得):2,000万円
- 所有期間:12年
👉 今度は 軽減税率の特例が使えます。
税率14%で計算 → 税金は約280万円。

つまり、同じ利益でも所有期間が長いと税金がかなり安くなるのです。
② 相続に関する特例も期間制限あり
例えば「相続税の取得費加算の特例」。
これは相続した土地を売るときに、相続で払った相続税の一部を経費にできる制度です。
ただし、「相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで」に売らないと使えないという期限があります。
所有期間制限のある特例_まとめ
- 3,000万円控除 → 所有期間の制限なし
- 軽減税率の特例 → 所有期間10年超が必要
- 相続に関する特例 → 相続から一定の年数以内に売る必要あり
👉 覚え方:
「控除は広く使える、でも“税率が軽くなる”制度や“相続関係”は期間の縛りがある」
他の制度との併用の可否について
「居住用財産の3,000万円控除」はとても強力な制度ですが、他の制度と同時に使えるのか? という点には注意が必要です。
そもそも「併用」とは?
不動産を売ったときに使える特例はいくつもあります。
例えば、
- 3,000万円控除(利益から3,000万まで差し引ける)
- 軽減税率の特例(所有10年以上なら税率が下がる)
- 買換え特例(新しいマイホームを買うなら、売却益の課税を繰り延べられる)

「併用」とは、これらを同時に使えるかどうかということです。
ポイント整理
- 3,000万円控除 × 軽減税率の特例 → 併用できる
- 3,000万円控除 × 買換え特例 → 併用できない
つまり、
「税率を軽くする制度」とは一緒に使えるけれど、
「利益そのものを消す/繰り延べる制度」とは一緒に使えません。
具体例でイメージ
例1:3,000万円控除 + 軽減税率の特例
Cさんはマイホームを12年所有し、売って4,000万円の利益が出ました。
- まず3,000万円控除を使う → 課税対象は 4,000万 − 3,000万 = 1,000万円
- さらに軽減税率(14%)を適用 → 1000万円×14% → 税金は 約140万円

ダブルで節税できますね!活用しない手はないです‼️
例2:3,000万円控除 + 買換え特例
Cさんが同じ条件で、今度は新しい家を購入しました。
- 買換え特例を使うと
利益を将来に繰り延べることができます(つまり今は税金ゼロ)。 - でもここで 3,000万円控除を同時に使うことはできません。
なぜなら、もし両方を同時に使えたら「今も税金ゼロ・将来もなし」になって、税金逃れになってしまうからです。
中学生向けのたとえ

- 3,000万円控除=テストの点数から「マイナス30点」差し引ける制度。
- 軽減税率の特例=テストの点数にかかる「罰ゲームが少し軽くなる」制度。
- 買換え特例=「今回のテストの点数は、次のテストまで保留にしてあげる」制度。
👉 「マイナス30点」と「罰ゲーム軽く」は一緒にできる。
👉 でも「マイナス30点」と「次回まで保留」は同時にできない。
他の制度との併用について_まとめ
- 3,000万円控除は万能に見えるけど、併用ルールに注意!
- 軽減税率の特例とはOK
- 買換え特例とはNG
- 仕組みを「控除」「税率軽減」「繰延べ」と整理すると混乱しにくい
まとめ・今回の学び
- 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」とはなにか?
→ 自分が住んでいた家や土地を売ったとき、利益(もうけ)が出ても、その利益から最大3,000万円までを差し引いてくれる制度です。
→覚え方:「マイホーム売却 → 利益から最大3,000万円分が“なかったこと”にできる」 - 所有期間の制限がある特例とは?
→1.軽減税率の特例:10年を超えていると税率が軽くなる制度です。
2.取得費加算の特例:相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却しなければなりません。 - 他の制度との併用の可否について
→3,000万円控除 × 軽減税率の特例 → 併用できます。
→仕組みを「控除」「税率軽減」「繰延べ」と整理しましょう。
今回は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」とはなにか?について解説しました。
この特例の要件や、他の特例との併用の可否について、整理して理解できたのではないかと思います。
不動産の分野の特例は色々あるので、ひとつひとつの背景を理解することで記憶の定着につながります。
完璧に覚えなくても、この記事があるということだけでも覚えていってくださいね。
次回予告:買い替えの特例

マイホームを売って新しい家に住み替えるときに使える「特定の居住用財産の買換えの特例」。
実はこの制度を使うためには、いくつかの細かい条件があります。
たとえば、譲渡した年の1月1日において所有期間が【□1】を超えていることや、譲渡した金額が【■2】以下であること、などです。
次回はこの【□1】【■2】に入る正しい答えを確認しながら、買換え特例の仕組みを整理していきます。
FP試験でよく問われる“ひっかけポイント”でもあるので、ぜひ一緒に学んでいきましょう!

次回もお楽しみに(^^)



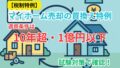
コメント