「物価が上がった」「暮らしにくくなった」と感じること、ありますよね。
そんな“暮らしの値段”の変化を数字で表すのが「消費者物価指数(CPI)」です。
でもその中身、ちゃんと説明できますか?
今回はこのテーマに沿って、仕組みと注意点をわかりやすく解説します!

こんにちは。こいちろです。
今回も一緒に新しい・正しい知識を身につけましょう
この記事は、現状に物足りなさを感じている筆者が、興味のある新たな知識をとりいれるためのブログです‼️
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 消費者物価指数ってどうやって算出されるの⁉️
- 消費者物価指数と企業物価指数の違いってなんなの⁉️
- これら以外に経済指標ってどういうものがあるの⁉️
📘 今回の分野:金融資産運用/経済と金融の基本
今回学ぶ範囲は、金融資産運用/経済と金融の基本です。
特に今回は、上記の範囲内の消費者物価指数の定義についてしっかりと確認していきましょう。
消費者物価指数と並んで企業物価指数というものもあるので、区別できるようにそれぞれの特徴を把握していきましょう‼️
❓️ 問題文の紹介
消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る【□1】の価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものであり、【■2】が毎月公表している。
□1、■2に入る語句はなにか?
- □1:財 、■2:日本銀行
- □1:財およびサービス 、■2:総務省
- □1:財およびサービス 、■2:日本銀行

3と解答しました。
なんとなくで選びました。
「発表元」が何処かまでは、復習できていませんでした。
企業物価指数が横並びになっているので、そちらの内容が混ざった選択肢だったのでしょう。
それでは正解を確認しましょう。
✅ 正解と解説の要点
消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る【□1】の価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものであり、【■2】が毎月公表している。
□1、■2に入る語句はなにか?
- □1:財 、■2:日本銀行
- □1:財およびサービス 、■2:総務省 ←正解
- □1:財およびサービス 、■2:日本銀行
正解は2番でした。
日本銀行が公表しているのは企業物価指数のようです。
ポイント解説を確認して、さらに深堀りしていきましょう。
✅️ポイント解説
「消費者物価指数(CPI)」とは、全国の世帯が日常生活で購入する商品やサービスの価格の変動を時系列で測定したものです。
・「□1」には「財およびサービス」が入ります(具体的には、食料・衣料・光熱費など)。
・「■2」には「総務省」が入り、毎月発表しています。
🔍 深掘り考察!!
今回の考察は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 消費者物価指数ってどうやって算出されるの⁉️
- 消費者物価指数と企業物価指数の違いってなんなの⁉️
- これら以外に経済指標ってどういうものがあるの⁉️
消費者物価指数ってどうやって算出されるの⁉️
消費者物価指数(CPI)は、「全国の世帯がふだん買っているものの価格の変化」を表した数字です。
このとき、すべての商品を調べるわけではなく、「代表的な品目」だけをピックアップして、それらの値段を定期的にチェックします。
📝 計算の流れはこうです!
- 基準となる年を決める(例:2020年)
この年の物価を「100」として、そこからどれだけ上がったか・下がったかを見ていきます。 - 調査する品目を決める(約600品目)
たとえば、米・パン・牛乳・電気代・交通費・医療費など。
ふつうの家庭がよく買うものや使うサービスが対象です。 - お店やサービスの価格を定期的に調査(毎月)
全国のスーパーや薬局などで実際の販売価格を調査します。 - 「ウェイト(重み)」をかけて合計する
たとえば「電気代」は家計に占める割合が大きいので、その分、影響も大きくカウントされます。
逆にあまり買わないものは、重みは軽くなります。 - 指数を出す(物価変動を数字で)
2020年=100だったとき、2025年に105なら「物価が5%上がった」という意味です。
💡 例えるなら…
CPIは「みんなの買い物かごの中身の、値札をぜんぶチェックして、どのくらい高くなったかを比べる作業」です。
買い物かごの中のパンや牛乳が軒並み値上げされていれば、「物価が上がった」と判断され、指数が高くなります。
✅ 消費者物価指数(CPI)の算出 まとめ
- 消費者物価指数CPIは生活に身近な物の価格の動きをチェックする統計
- 全国で毎月、決まった商品・サービスの価格を調べている
- 品目ごとに重み(家計に占める割合)を考慮して計算
- 「2020年を100として、いま何%上がったか」を数字で表す
消費者物価指数と企業物価指数の違いってなんなの⁉️
比較表としてまとめると、以下の通りになります。
| 指数 | 調べているもの | 誰の立場? | 主な使い道 |
|---|---|---|---|
| 消費者物価指数(CPI) | 一般家庭が買う商品やサービスの価格 | 消費者(私たち) | 年金の改定、物価上昇の判断、金融政策など |
| 企業物価指数(PPI/CGPI) | 企業同士で取引されるモノの価格(原材料・中間財など) | 企業 | 仕入れ価格の変動チェック、企業のコスト分析など |
🧺 消費者物価指数(CPI)とは?(おさらい)

「私たち消費者が、スーパーやお店で買う商品の値段がどれだけ変わったか?」を調べるものです。
- たとえば:お米、パン、光熱費、交通費、医療費など
- つまり、「生活に直接かかわるものの価格」の変化を見ています。
🟠 暮らしに直結しているので、年金額の改定や日銀の金融政策に反映されることが多いです。
🏭 企業物価指数(PPI/CGPI)とは?

企業同士がやりとりする「原材料」や「卸売の価格」がどれだけ変化しているか?を調べるものです。
- たとえば:鉄鋼、原油、木材、小麦粉など
- 家庭では直接買わないけど、商品を作るために必要な“もと”の価格ですね。
🔵 企業のコストに関係するので、「インフレの兆しがあるか?」を判断するヒントになります。
🧠 例えるなら…
- CPIは「スーパーのレジで払う金額」をチェックするイメージ。
- PPIは「工場が材料を仕入れるときの値段」をチェックするイメージ。
どちらも「物価」だけど、見ているステージが違うんです。
✅ CPIとPPIの比較 まとめ
- CPI(消費者物価指数)=家計が買うモノ・サービスの価格変化
- PPI(企業物価指数)=企業が買う原材料や商品価格の変化
- どちらも物価を見るための大事な指標だけど、対象とする価格と使い道が違う!
これら以外に経済指標ってどういうものがあるの⁉️
消費者物価指数や企業物価指数について確認できました。
上記以外にもいろいろな経済指標があるようです。
まずはどんなものがあるか、確認しておきましょう。

まずは経済指標とはなにか、についても確認します。
✅ 経済指標ってなに?
経済の「今、どうなってる?」を数字で見える化したものです。
体温計で熱を測るように、経済にも「物価」「雇用」「成長率」などいろんな温度計があります。
🧾 主な経済指標の種類と内容一覧
| 指標の分類 | 指標名 | 内容 | ざっくりイメージ |
|---|---|---|---|
| 物価系 | 消費者物価指数(CPI) | 一般家庭の物価 | 日用品やサービスの値段が上がった?下がった? |
| 〃 | 企業物価指数(PPI) | 企業の仕入れ値 | 材料費や卸売価格の変動を見る |
| 景気系 | GDP(国内総生産) | 日本全体で1年間に生み出されたお金の合計 | 景気がよいかどうかを見る基本中の基本 |
| 〃 | 景気動向指数(CI/DI) | 景気の先行きや今の状態を示す複合指標 | 経済の空気をまとめてチェックできる |
| 雇用系 | 有効求人倍率 | 求人1件に何人の応募があるか | 高いと人手不足、低いと仕事が少ない |
| 〃 | 失業率 | 働けるのに仕事がない人の割合 | 景気の良し悪しが出やすい指標 |
| 金融系 | 金利(政策金利) | 日銀が決めるお金の貸し借りの基本の利率 | 金利が上がるとローンが大変になる |
| 〃 | 為替レート(ドル円など) | 円と外国のお金の交換比率 | 輸出入・旅行・物価に影響大! |
| 貿易系 | 貿易収支 | 輸出-輸入の差 | 黒字なら輸出が多い、赤字なら輸入が多い |
🧠 例えるなら…
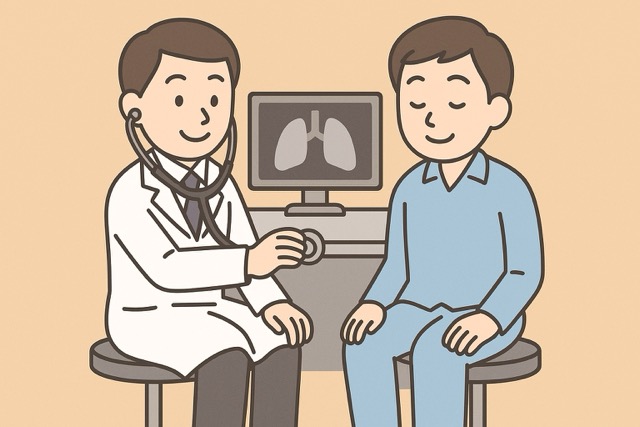
- 経済指標は、日本という巨大な体の健康診断表です。
- 体温(物価)、血圧(景気)、脈拍(雇用)、血液検査(貿易)みたいな感じで、それぞれの「数値」が異なる角度から体調を教えてくれます。
🔍 その他の経済指標 まとめ
- 経済指標は「経済の今」を知るための数字のツール。
- 物価・景気・雇用・貿易・金融など、多方面からチェックする必要がある。
- FP試験やニュースでもよく出てくるので、見慣れておくと日常にも役立ちます!
📝 まとめ・今回の学び
- 消費者物価指数ってどうやって算出されるの⁉️
→全国で毎月、決まった商品・サービスの価格を調べている。
品目ごとに重み(家計に占める割合)を考慮して計算。 - 消費者物価指数と企業物価指数の違いってなんなの⁉️
→CPI(消費者物価指数)=家計が買うモノ・サービスの価格変化
PPI(企業物価指数)=企業が買う原材料や商品価格の変化
対象とする価格と使い道が違う! - これら以外に経済指標ってどういうものがあるの⁉️
→物価・景気・雇用・貿易・金融など、多方面から「経済の今」を知るための数字のツール。
次回予告:債券投資のキホン「単利最終利回り」について!
次回のテーマは、債券投資のキホン「単利最終利回り」について!
例えば…
「表面利率(クーポンレート)が3%、残りの運用期間が6年の固定利付債券を、額面100円あたり103円で購入した場合、単利最終利回りはいくらになる?」
一見すると「金利が3%だから…」と考えたくなりますが、購入価格が額面より高いこのケースでは、ちょっとした計算のコツが必要です!
債券の仕組みが苦手な方にもわかりやすく、数字の動きを一つずつで解説していきます!
次回もお楽しみに!

計算一つずつをなるべく言葉を加えて解説するつもりなので、
興味のある方はぜひご確認ください☺️
よろしくお願いします。




コメント