不動産を相続したあとに売却する場合、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」を使うことで、譲渡所得税を軽減できる可能性があります。
ただし、この特例を受けるためには「いつまでに売却するか」という期限が決まっています。
今回は、その年数についての過去問を通じて理解を深めていきましょう。
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)とは?
→相続で受け継いだ土地や建物を売却したときに使える「税金を軽くする制度」です。 - なぜ期間制限があるのか?
→相続税負担と売却を結びつける救済措置の特例だから、です。 - 取得費加算の特例のメリット・デメリット
→メリット(代表例):節税ができる。他
→デメリット(代表例):売却タイミングの自由度の制限がある。他
📘 今回の分野:不動産譲渡時の税金

今回学ぶ範囲は、前回に引き続き、不動産の税金に関わる「譲渡所得」について取り上げます。
『相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)』についての内容を、具体例を挙げて、解説していこうと思います。

人によってはお得になる特例なので、しっかりと抑えておきましょう‼️
❓️ 問題文の紹介
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後【何年?】を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
【 】内に入る年数はいくらか?
今回の問題は、単純に知識不足でした。
選択肢は【2年、3年、5年】の三択。

よくわからなかったので、2年にしました💦
しっかりと知識を身に着けておきたいものです。
正解を確認しましょう‼️
✅ 正解と解説の要点

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後【何年?】を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
【 】内に入る年数はいくらか?
→正解:3年
正解は、3年でした。
なぜ3年なのでしょうか?
まずはポイント解説を確認して、3年である背景も理解して確実な知識として身につけましょう。
✅️ポイント解説

- 正解:3年
- ポイント:相続税の申告期限(相続開始から10か月後)の翌日から数えて「3年を経過する日まで」に売却することが条件です。
- つまり、実際には「相続開始からおおむね3年10か月以内」に売却しなければなりません。

この期限を超えてしまうと特例を使えなくなり、譲渡所得税が増える可能性があります。
🔍 深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)とは?
→相続で受け継いだ土地や建物を売却したときに使える「税金を軽くする制度」です。 - なぜ期間制限があるのか?
→相続税負担と売却を結びつける救済措置の特例だから、です。 - 取得費加算の特例のメリット・デメリット
→メリット(代表例):節税ができる。他
→デメリット(代表例):売却タイミングの自由度の制限がある。他
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)とは?

相続で受け継いだ土地や建物を売却したときに使える「税金を軽くする制度」です。
正式名称は 「相続税額の取得費加算の特例」 といい、次の仕組みになっています。
- 通常、不動産を売却すると「売却価格 −(購入価格+諸経費)」が譲渡所得になり、課税されます。
- しかし、相続で取得した財産は、自分が買ったわけではないので「購入価格(取得費)」が低く見積もられるケースが多いです。
- そのままだと譲渡所得が大きくなり、税金も高額に…。
- そこで、相続税を払った場合には「払った相続税額の一部を取得費に加算できる」ようにして、譲渡所得を少なくできるのです。
✦ 適用できる条件
- 相続または遺贈で財産を取得した人が対象。
- その財産に対して相続税を納めていること。
- 相続税の申告期限(相続開始から10か月後)の翌日から3年以内に売却すること。
✦ 具体例でシミュレーション

例:土地を相続して売却したケース
- 亡くなった父が持っていた土地:5,000万円で売却
- 父が購入した当時の価格(取得費):1,000万円
- 譲渡費用(仲介手数料など):200万円
- 相続税として納めた金額:800万円
● 特例を使わない場合
譲渡所得 = 5,000万円 −(1,000万円+200万円)
= 3,800万円
この3,800万円が課税対象になり、税率20%強で計算すると、およそ760万円超の税金になります。
● 特例を使った場合
取得費に「相続税額800万円」を加算できます。
譲渡所得 = 5,000万円 −(1,000万円+200万円+800万円)
= 3,000万円
課税対象が減るため、税金は600万円程度に。
→ およそ160万円の節税になります。
✦ ポイントと注意点
- 相続税を納めていない場合(基礎控除内でゼロ申告など)は、この特例は使えません。
- 「取得費に加算できる相続税額」は、相続した財産の中で譲渡した部分に対応する相続税額に限られます。
- 適用期限(相続開始から約3年10か月以内)を過ぎると使えなくなるので注意!
✦ まとめ
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」とは、
- 相続で取得した不動産を売却したとき、相続税として払った分を取得費に上乗せできる制度。
- これによって譲渡所得が減り、税金を軽減できる。
- 適用には期限があり、相続税を実際に納めていることが条件。

この特例は、特に「相続税を払った人が土地や建物をすぐに売る場合」に大きな効果を発揮します。
なぜ期間制限があるのか?

特例が「相続開始から相続税申告期限の翌日以後3年以内の譲渡」と決められているのは、主に次の理由です。
1. 相続税と譲渡税を結びつけるため
この特例は「相続税を負担した人が、すぐにその財産を売却する場合に救済する」制度です。
長い年月が経ってしまうと、
- 相続税を払った時点の評価額
- 売却時の時価
の関係が薄れてしまいます。
そのため、期間を区切って「相続税の負担と売却の関係がまだ強い時期」に限っているのです。
2. 不公平を避けるため
もし期間制限がなければ、
「相続税を払ってから10年後に売却しても取得費に加算できる」
となり、不公平が生まれます。
時間が経てば価格変動の影響が大きくなるため、税金の公平性を保つために3年と短めに区切っているのです。
3. 税務行政上の実務を明確にするため
相続税の申告が終わった後、売却がすぐ行われるケースを救済する制度なので、「申告期限の翌日から数えて3年」という基準を設け、実務的にもわかりやすくしています。
なぜ期間制限があるか_まとめ
- 「取得費加算の特例」は相続税を払った直後に財産を売る人への救済制度だからです。
- 長期間放置すると、相続税と売却の関係が弱まり、不公平になります。
- そのため、相続税申告期限の翌日から3年以内という期限が設けられています。
「なぜ3年?」=『相続税負担と売却を結びつける救済だから、時間が経ちすぎると不公平になるので短期間に限っている』

上記のアンダーラインのように覚えておきましょう‼️
取得費加算の特例のメリット・デメリット
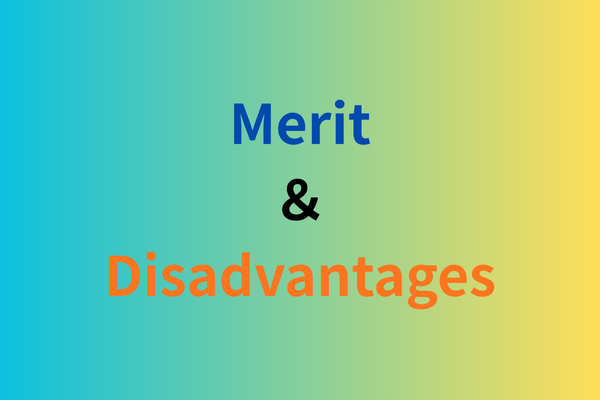
「取得費加算の特例(相続税の取得費加算の特例)」は節税に役立つ一方で、気をつけるべき落とし穴もあります。
ここでは メリット・デメリット を具体例を交えて整理します。
✦ メリット

① 譲渡所得が減って税金が軽くなる
- 相続税として支払った金額を取得費に上乗せできるので、売却時の利益(譲渡所得)が圧縮されます。
例:
- 売却価格:5,000万円
- 本来の取得費(父が購入した価格):1,000万円
- 譲渡費用(仲介手数料など):200万円
- 相続税:800万円
👉 特例なし:譲渡所得 = 5,000 −(1,000+200)= 3,800万円
👉 特例あり:譲渡所得 = 5,000 −(1,000+200+800)= 3,000万円

約800万円の所得を圧縮でき、税率20%強で計算すると 160万円前後の節税 になります。
② 相続直後の納税資金対策に有効
- 相続税は「現金一括納付」が原則。
- 不動産を相続しても現金が足りない場合、売却で得た資金を相続税に充てるケースが多い。
- この特例があることで、二重の税負担を少しでも軽減できる。
③ 相続人間の公平感が保たれる
- 複数人で相続した場合でも、相続税を負担した人が売却するときに取得費に加算できる。
- 「相続税を多く払った人ほどメリットを受けられる」仕組みなので、相続人間の不公平感を調整する役割もあります。
✦ デメリット
① 適用期限が短い
- 相続税の申告期限(相続開始から10か月)翌日から 3年以内 に売却しないと使えません。
- 実際には「相続開始から約3年10か月以内」が期限です。
例:
相続から5年後に売却 → この特例は使えず、税負担が増える。
② 相続税を払っていないと使えない
- 相続税が基礎控除内でゼロの場合は対象外です。
- 「相続税を払った人だけが得する制度」なので、課税されなかった人には意味がない。
③ 売却タイミングの自由度が制限される
- 「税金を減らすために早めに売るか、それとも市場が高騰するまで待つか」という判断が難しくなる。
例:
- 相続から4年後に土地の価格が急騰したが、特例は使えず高額課税になった。
- 早めに売っていれば節税できたのに…というケースも。
④ 相続税の一部しか加算できないこともある
- 加算できるのは「その売却財産に対応する相続税額」だけです。
- 相続全体で相続税を1,000万円払っていても、売却した財産に対応する部分が200万円なら、その200万円しか加算できません。
✦ まとめ
メリット
- 譲渡所得が減って節税できる
- 相続直後の資金繰り対策になる
- 相続人間の公平感が出る
デメリット
- 適用期限が短い(3年10か月以内)
- 相続税を払っていないと使えない
- 売却タイミングの自由度が制限される
- 相続税の一部しか加算できない場合がある

この特例は「相続税を払ったうえで、不動産を早めに売る予定がある人」に向いています。
逆に「相続税ゼロの人」や「長期保有して値上がりを狙う人」にはあまりメリットがありません。
まとめ・今回の学び
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)とは?
→相続で受け継いだ土地や建物を売却したときに使える「税金を軽くする制度」です。
→相続税を納めているということがポイントです。 - なぜ期間制限があるのか?
→相続税負担と売却を結びつける救済措置の特例だから、です。
→時間が経ちすぎると不公平になるので短期間(3年)に限っています。 - 取得費加算の特例のメリット・デメリット
→メリット(代表例):節税ができる。他
→デメリット(代表例):売却タイミングの自由度の制限がある。他
今回は、『相続財産にかかる譲渡所得の課税の特例』について取り上げました。
この特例は、実生活にかなり密接したものなのではないでしょうか。

私はまだ経験がありませんが、不動産を相続して、その不動産を譲渡することになる場合を想定しておいてもいいかもしれません。
この記事に書いてある、ということだけでも覚えておいていただければ、相続・譲渡に対する負担は軽くなるのではないかと思います。
次回予告:マイホームの譲渡の特例
次回は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」について取り上げます。
この制度は、自分が住んでいた家を売ったときに大きな節税ができる非常に重要な特例です。
ただし、居住しなくなってからずっと適用できるわけではなく、期限が決まっています。
問題は次のとおりです。
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から【□1】を経過する日の属する年の【■2】までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。

果たして【□1】【■2】にはどんな数字・言葉が入るのでしょうか?
次回、詳しく解説します!お楽しみに‼️
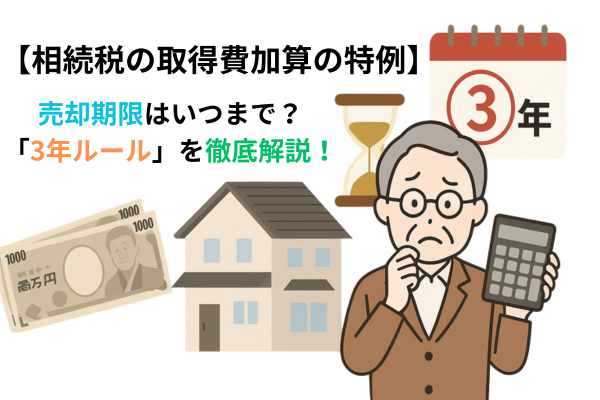



コメント