マイホームを売却するとき、一定の条件を満たせば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」という大きな節税メリットを受けられます。
ただし、この特例には「いつまでに売るか」という期限が決まっています。
今回は、その期限に関する出題を取り上げて、仕組みを整理していきます。
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除とは?
→マイホームを売って利益が出たとき、その利益から 最大3,000万円まで差し引いてくれる制度です。 - なぜ12月31日までなのか?
→税金の世界は、1月1日から12月31日までを「1年」とします。(暦年課税) - デメリットはあるか?
→期限があります。(3年ルール)
→親族売却はNG
→取得費が低いと限界があります。・・・他
📘 今回の分野:不動産の税金

居住用財産を譲渡した場合、一定の要件を満たすことで、各種の特例を受けることが出来ます。
今回は、不動産の税金に関わる、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除について解説していきます。
特例を受けるためにどのような要件があるのか。
また、デメリットはあるのか。
一つ一つ確認していきましょう‼️
❓️ 問題文の紹介
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から【□1】を経過する日の属する年の【■2】までの譲渡でなければ、『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除』の適用を受けることができない。
□1、■2に入る用語はなにか?
今回求めるべき答えは、□1が期間で■2が日付です。
前回の記事で期間は学んでいたので、□1は合っていましたが、■2を間違えてしまいました。
■2の選択肢は【12月31日、3月15日】です。

なんとなくですが、年度末付近かな、と思ったので【3月15日】を選択してしまいました。
正解を確認しましょう‼️
✅ 正解と解説の要点

自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から【□1】を経過する日の属する年の【■2】までの譲渡でなければ、『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除』の適用を受けることができない。
□1、■2に入る用語はなにか?
正解_【□1:3年】、【■2:12月31日】
□1は 3年、■2は12月31日でした。
なぜ12月31日までなのか。
それは税金の世界の課税のルールによります。
税金の世界では、1月1日から12月31日を「1年」としています。(暦年課税)

覚えていってくださいね。
✅️ポイント解説
つまり、「居住しなくなった日から3年を経過する年の12月31日まで」に売却する必要があります。
この期限を過ぎると、3,000万円特別控除は使えません。
🔍 深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除とは?
→マイホームを売って利益が出たとき、その利益から 最大3,000万円まで差し引いてくれる制度です。 - なぜ12月31日までなのか?
→税金の世界は、1月1日から12月31日までを「1年」とします。(暦年課税) - デメリットはあるか?
→期限があります。(3年ルール)
→親族売却はNG
→取得費が低いと限界があります。・・・他
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除とは?

マイホーム(自分や家族が住んでいた家とその敷地)を売って利益(=もうけ)が出たとき、その利益から 最大3,000万円まで差し引いてくれる制度です。
差し引いた残りにだけ税金(譲渡所得税・住民税)がかかります。
残りが0円になれば、その年の税金はかかりません。
適用できる主な条件(ざっくり)

- 自分が住んでいた家・敷地の売却であること
賃貸用・別荘・セカンドハウスは対象外です。 - 売るタイミングの期限を守ること
住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売る必要があります。
(=「3年ルール」) - 身内・自分の会社など“特別な関係”への売却はNG
親子・夫婦・同族会社などへの売却は原則ダメです。 - 同一年中にこの控除を二重に使うのは不可
その年に使えるのは原則1回だけです。 - 家を壊して土地だけ売る場合も、基本はOK
ただし、引っ越し→取り壊し→売却までの流れを期限内に。取り壊し後ダラダラ長期保有はNGだと思ってください。 - 確定申告が必要
税額が0円になっても、申告して初めて適用されます(住民票の除票等の添付が必要です)。
補足:所有期間が短期(5年以下)でも、この3,000万円控除は使えます。

ただし、税率の考え方は「短期・長期」で変わります(後述)。
いくら得になるの?

計算の流れはこうです。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
→ ここから 最大3,000万円を控除
→ 残りに税率(短期 or 長期、さらに所有10年以上なら軽減税率あり)をかける
- 短期(5年以下):概ね 39.63%
- 長期(5年超):概ね 20.315%
- さらに 所有10年超の居住用 は、残額のうち6,000万円以下の部分に軽減税率(約14.21%)が使えます(3,000万円控除と併用可)。
具体例でサクッと理解
例1:もうけが3,000万円以下なら税金ゼロ
- 売却価格:5,000万円
- 取得費(購入代金・仲介手数料・リフォーム一部など):3,200万円
- 譲渡費用(仲介手数料・印紙など):200万円
- 譲渡所得=5,000 −(3,200+200)=1,600万円
- 3,000万円控除を引くと 0円
→ 課税なし

確定申告は必要なので、注意してください。
例2:もうけが3,700万円、所有10年超(軽減税率あり)
- 売却価格:9,000万円
- 取得費+譲渡費用:5,300万円
- 譲渡所得=9,000 − 5,300 = 3,700万円
- 3,000万円控除後=700万円
- 所有10年超の居住用なので、700万円全額に軽減税率(約14.21%)
→ 税額の目安:約99.5万円
(控除がなければ3,700万円×20.315%=約752万円。)

控除の有り無しで差は約650万円にもなります。大きいですね‼️
例3:短期所有(5年以下)でもOK
- 譲渡所得:2,800万円
- 3,000万円控除で 0円 → 課税なし

短期だと本来は約39.63%課税。控除の威力が大きいです。
併用・非併用の考え方
- 併用OK:所有10年超の軽減税率(14.21%)は3,000万円控除と併用できます。
- 併用NG:買換えの特例や、住宅ローン残高がある自宅売却損の損益通算・繰越控除などとは原則併用できません。
「どれを使うと最もトクか」はケースバイケースです。利益が大きいなら3,000万円控除+軽減税率、有利な場合が多いです。
よくある落とし穴(試験にも実務にも出ます)

- 期限アウト:引っ越してからズルズル保有し、3年ルールを越えてしまう。
- 親族への売却:親や子へ名義移転してしまい適用不可。
- セカンドハウス:普段住んでいない別荘は対象外。
- 申告忘れ:税金ゼロでも確定申告しないと適用されません。
- 共有持分の扱い:夫婦共有で売ると、各人がそれぞれ最大3,000万円控除を使えます(その年の重複適用は×)。
手続きで用意する主な書類(目安)
- 売買契約書・仲介手数料の領収書など(取得費・譲渡費用の証明)
- 住民票の除票(いつまで住んでいたかの証明)
- 登記事項証明書(不動産の証明)
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書に添付)
制度まとめ
- 最大3,000万円を利益から差し引ける、マイホーム売却の超強力な節税。
- キモは 「いつまでに売るか」= 3年ルール。
- 10年超所有なら、軽減税率と併用でさらに有利。
- 親族売却・別荘・申告漏れはNG。
- 迷ったら、まずは「利益の見込み」「引っ越し日」「売却予定日」を並べて、期限と税額のシミュレーションをしましょう。
なぜ「12月31日まで」なのか?
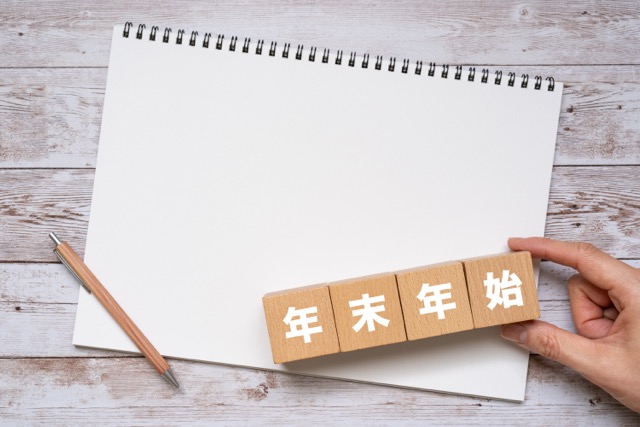
税金の世界では、【1月1日から12月31日までが「1年(課税年度)」】という扱いになります。
そのため、特例の適用期限も「○年△月」という日付で細かく切られるのではなく、
「3年経過した年の年末(=12月31日)」を区切りにしているのです。
つまり、
- 3月に居住しなくても、
- 8月に居住しなくても、

「3年経過した年の大晦日」で一律に揃えることで、実務的に分かりやすくしているわけです。
イメージで整理
- 税金は「年ごとに計算する」仕組みです。
- だから、期限も「その年の終わり」である12月31日に区切られます。
- これにより、売却のタイミングを確認しやすくし、税務処理をシンプルにしています。
12月31日迄の理由_まとめ
- 特例は「居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」までに売却が条件。
- 「12月31日まで」となっているのは、税金の計算が暦年(1月1日~12月31日)単位だから。
- 個別の日付で複雑にならないよう、年末で一律に区切っているためです。

「なぜ12月31日か?」→「税金は暦年課税だから」と押さえておくと、分かりやすいと思います。
デメリットはあるか?
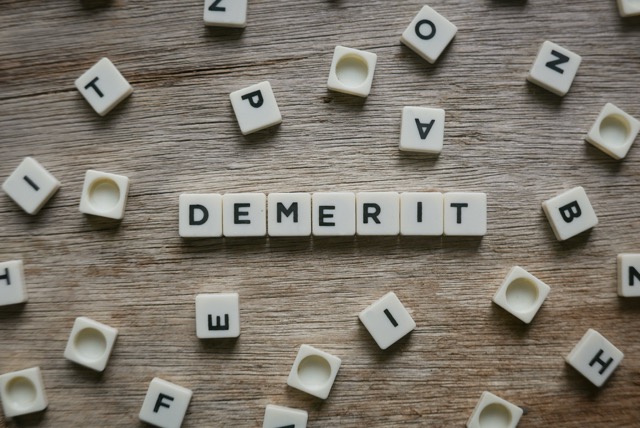
デメリット①:期限を過ぎると使えない
ポイント
- 「居住しなくなった日から3年を経過する年の12月31日まで」に売却しなければ適用できません。
- 引っ越し後、空き家を長く放置すると、控除の権利が消えます。
具体例
- 2020年5月に引っ越して空き家になった家を、2024年2月に売却 → 期限切れで 3,000万円控除は使えない。
- もし3,000万円の利益が出ていたら、そのまま課税されてしまい、税額が数百万円単位になる可能性も。
デメリット②:親族への売却は適用できない
ポイント
- 親や子、夫婦間など「特別な関係者」への売却では使えません。
- 税金を減らすために「家族間で名義を移す」ような取引を防ぐためのルールです。
具体例
- 子どもに3,500万円で家を売却 → 利益が3,000万円あっても、この控除は使えない。
- 本来なら税金ゼロになったはずでも、数百万円の税金がかかる。
デメリット③:他の特例と併用できないものがある
ポイント
- 「買換え特例」や「住宅ローン残高と損益通算できる特例」とは同時に使えません。
- どちらかを選ぶ必要があります。
具体例
- 旧宅を売って新居を買ったケース
- 「3,000万円控除」を使うと、その年の税金は減るが、将来の税負担に影響するかもしれない。
- 一方「買換え特例」を選べば、税金を繰り延べできるので、利益が大きい場合は買換え特例の方が有利になることも。
- 「3,000万円控除」を使うと、その年の税金は減るが、将来の税負担に影響するかもしれない。

ケースによっては「3,000万円控除を選んだことで、結果的に損」になる可能性あります。
デメリット④:取得費が少ない場合は恩恵が限定的
ポイント
- 古い家などで購入時の資料がなく、取得費を「5%ルール」で計算すると、利益が大きく出やすい。
- 控除でゼロにできない部分は、結局課税されます。
具体例
- 40年前に500万円で購入した土地付き住宅を、6,000万円で売却。
- 取得費が不明なので「売却額×5%=300万円」を取得費とする。
- 譲渡所得=6,000 − 300 = 5,700万円。
- 3,000万円控除しても残り 2,700万円 に課税される。
→ 控除は役立つが、それでも税額は数百万円になる。
デメリット⑤:確定申告が必須(手間がかかる)

ポイント
- 税金がゼロになっても「確定申告」をしないと控除は受けられません。
- 添付書類(住民票の除票、売買契約書、仲介手数料の領収書など)を揃える必要があります。
具体例
- 「税金ゼロだから申告しなくていいや」と思って申告しないと、後で税務署から「未申告扱い」とされ、ペナルティが発生する可能性も。
デメリット⑥:将来の税負担に影響することも
ポイント
- 「買換え特例」を選ばなかった場合、将来の新居売却で控除が使えず、逆に税負担が増えるケースがあります。
- また、同一年に複数の不動産を売る場合、控除は原則1回しか使えないため、どの物件で使うかの戦略が必要です。
具体例
- A不動産(利益2,000万円)、B不動産(利益4,000万円)を同じ年に売却。
- Aで3,000万円控除を使うと税金ゼロになるが、Bでは全額課税。
- Bで使えば「利益4,000 − 控除3,000=1,000万円」にしか課税されず、トータルで有利。
- Aで3,000万円控除を使うと税金ゼロになるが、Bでは全額課税。

選択を誤ると損をすることになります。
まとめ:デメリットを整理すると…
- 期限がある(3年ルール)
- 親族売却はNG
- 他の特例と併用不可のものがある
- 取得費が低いと限界がある
- 確定申告が必須で手間
- 複数物件・買換えでは戦略が必要
つまり、「とりあえず税金がゼロになる便利な制度」と思いがちです。
実際は 使える期限・相手先・併用条件をきちんと押さえないと、かえって不利になる場合もあります。
まとめ・今回の学び
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除とは?
→マイホームを売って利益が出たとき、その利益から 最大3,000万円まで差し引いてくれる制度です。
→「利益の見込み」「引っ越し日」「売却予定日」を並べて、期限と税額のシミュレーションをしましょう。 - なぜ12月31日までなのか?
→税金の世界は、1月1日から12月31日までを「1年」とします。(暦年課税)
→個別の日付で複雑にならないように、年末で一律に区切ります。 - デメリットはあるか?
→期限があります。(3年ルール)
→親族売却はNG
→取得費が低いと限界があります。・・・他
→実際は 使える期限・相手先・併用条件をきちんと押さえないと、かえって不利になる場合もあります。
次回予告:軽減税率の特例
次回は「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」について取り上げます。
自宅を長年所有して売却したとき、通常の税率よりも軽くなる軽減税率が使える場合があります。
では、問題です。
「個人が自宅の土地および建物を譲渡し、『居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けた場合、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち、【□1】以下の部分については、所得税および復興特別所得税【■2】、住民税4%の税率で課税される。□1、■2に入る数値はいくらか?」
税率が軽くなるラインはどこまでなのか?
そして、その数字がなぜ決まっているのか?

次回は具体的な数値と計算の流れを、わかりやすく解説します。
お楽しみに‼️
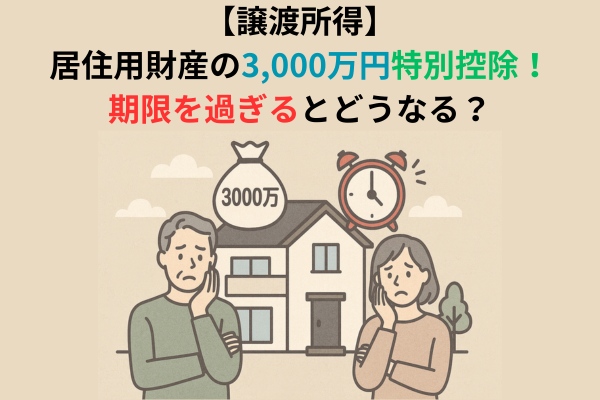



コメント