FP3級では、保険料控除の知識が問われる問題が頻出です。
なかでも「介護医療保険料控除」に該当する保険契約は範囲が限られており、選択肢に迷うことが多いテーマです。
今回はその見極めポイントを明確に解説していきます!
今回の分野:
今回はリスク管理分野における保険/所得控除(介護医療保険料控除)が問題文の範囲です。
問題文の紹介:
介護医療保険料控除の対象となるのは、次のうちどれか?
- 先進医療特約
- 傷害特約
- 定期保険特約
今回私が選んだ選択肢は、2.傷害特約 でした。

介護医療・・・じゃあ障害かな?
という、根拠のない当てずっぽうで選択しました。
正解と解説の要点:
介護医療保険料控除の対象となるのは、次のうちどれか?
- 先進医療特約 ←正解
- 傷害特約
- 定期保険特約
この問題は、先進医療特約・傷害特約・定期保険特約それぞれについて、
それがそもそも何なのか、
という点をしっかり理解しなければなりません。

まずはポイント解説を見ていきましょう!
✅️ポイント解説
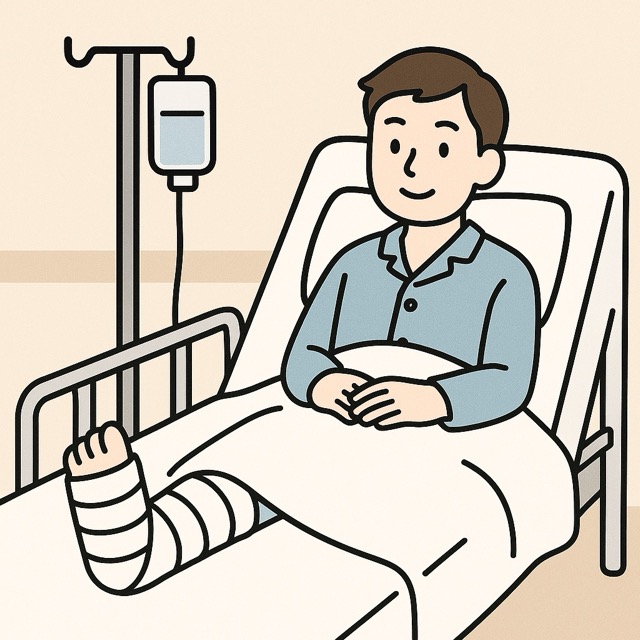
介護医療保険料控除の対象になるのは、以下のような保険契約です。
- 入院・手術・通院などの医療保障が主目的の保険
- 上記に付加される特約(例:先進医療特約)
「先進医療特約」は、医療保障の一環として付けられる特約であり、介護医療保険料控除の対象になります。
一方で、
- 傷害特約:けがによる死亡・後遺障害などに備える保険で、原則として新制度では控除対象外。
- 定期保険特約:死亡保障を目的とした保険で、こちらは一般の生命保険料控除の対象です。
深掘り考察!!:
今回の考察は、以下の点に絞って解説していきたいと思います。
- 介護医療費保険料控除とはなんなのか?
- 旧制度と新制度の違い
- 生命保険料控除の種類
「介護医療保険料控除」とは?
介護医療保険料控除は、新制度(介護医療保険料控除・一般生命保険料控除・個人年金保険料控除)の適用開始により創設された控除で、以下の保険料が対象となります。
- 医療保険(終身・定期)
- がん保険
- 介護保険
- 医療系特約(例:先進医療特約、入院給付特約 など)
傷害保険や死亡保険は医療や介護とは別物として扱われ、対象になりません。
もう少し噛み砕いた説明にすると、

病気やけがにそなえて入る保険のために払ったお金を、
「税金を安くする理由(=控除)」として使えるというルールです。
旧制度と新制度の違い
つづいて、旧制度と新制度の違いについて解説していきます。
「新」と「旧」の境界線は2012年にあるようです。
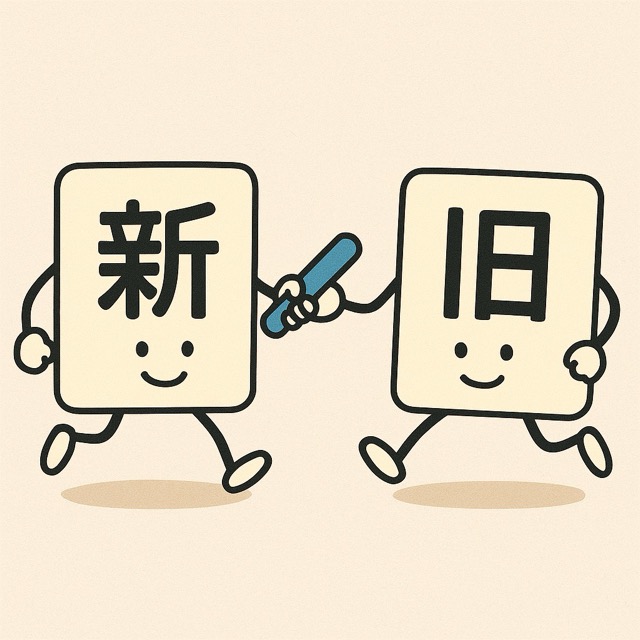
控除区分、控除対象保険、最大控除額についてまとめたので、以下をご確認ください。
| 制度 | 適用時期 | 控除区分 | 控除対象保険 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 旧制度 | 〜2011年12月31日 | 一般/個人年金(2区分) | 医療・介護・死亡保険 すべて「一般」扱い | 各区分 5万円(最大10万円) |
| 新制度 | 2012年1月1日〜 | 一般/個人年金/介護医療(3区分) | 医療・介護系保険は専用区分で控除 | 各区分 4万円(最大12万円) |
とくに、医療・介護系保険が専用枠で控除できるようになったのが新制度の特徴です。
生命保険料控除の種類

生命保険料控除には、3つの種類があります。
これは「2012年1月1日以降」の契約にあてはまる新制度に基づいています。
| 控除の種類 | 対象になる保険 | 例 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 死亡に備える保険 | 終身保険、定期保険 など |
| 介護医療保険料控除 | 病気や介護に備える保険 | 医療保険、がん保険、先進医療特約 など |
| 個人年金保険料控除 | 老後の生活資金を準備する保険 | 個人年金保険 など |
この3つのタイプの保険に入っていれば、それぞれについて税金が安くなる可能性があるということです。
🔶 いくらまで控除してもらえるの?
所得税と住民税で、上限がそれぞれ決まっています。
| 控除の種類 | 所得税の上限 | 住民税の上限 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 |
| 介護医療保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 |
| 個人年金保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 |
| 合計最大 | 12万円 | 7万円弱 |

つまり、全部の種類にうまく加入していたら、最大12万円分の控除が受けられる
ということです。
🔶 控除額の計算のしかた(所得税)
支払った金額に応じて、控除額が変わります。
| 支払った保険料(1年間) | 控除される金額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 全額控除される(=払った金額のまま) |
| 20,001〜40,000円 | 保険料 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,001〜80,000円 | 保険料 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,001円以上 | 一律 40,000円(上限) |
※住民税の計算式は少し違いますが、考え方は同じです。
🔶 控除を受けるにはどうすればいい?
毎年、10月〜11月ごろになると、保険会社から「保険料控除証明書」というハガキや書類が届きます。
これを、
- 会社員なら「年末調整」のときに提出する
- 自営業やフリーランスなら「確定申告」で使う
ことで、ちゃんと控除してもらえます。

FP3級試験対策:紛らわしい選択肢に注意!

試験では以下のような“なんとなく医療っぽい”選択肢が並ぶことが多くあります。
| 選択肢 | 見た目の印象 | 控除対象? | 理由 |
|---|---|---|---|
| 先進医療特約 | 専門的で迷う | ○ | 医療保障の一部 |
| 傷害特約 | ケガも医療? | × | 医療保険とは別分類 |
| 定期保険特約 終身保険 | 死亡保障 | × | 医療と無関係 |
まとめ・今回の学び:
- 介護医療保険料控除の対象は、【医療・介護に関連した保険】に限られる。
- 先進医療特約は対象だが、傷害特約や定期保険特約は対象外。
- 保険の名称だけで判断せず、「何に対して給付されるか?」を軸に整理する。
- 本試験では、「控除の区分(一般・介護医療・個人年金)」を理解しておくことが得点のカギ!
次回予告:死亡保険金の課税対象(贈与・相続・所得)について
次回のテーマは、「死亡保険金の課税対象(贈与・相続・所得)」についてです。
死亡保険金には「非課税になるイメージ」がありますが、実は受け取る人と契約内容の組み合わせによって、課税される税金の種類が変わることをご存じでしょうか?
- 相続税になるパターン
- 所得税になるパターン
- 贈与税になってしまうレアケース など、
見分けるポイントをわかりやすく整理していきます。

「なんとなく」で覚えていた方も、この機会にスッキリ理解できるはずです!
お楽しみに!
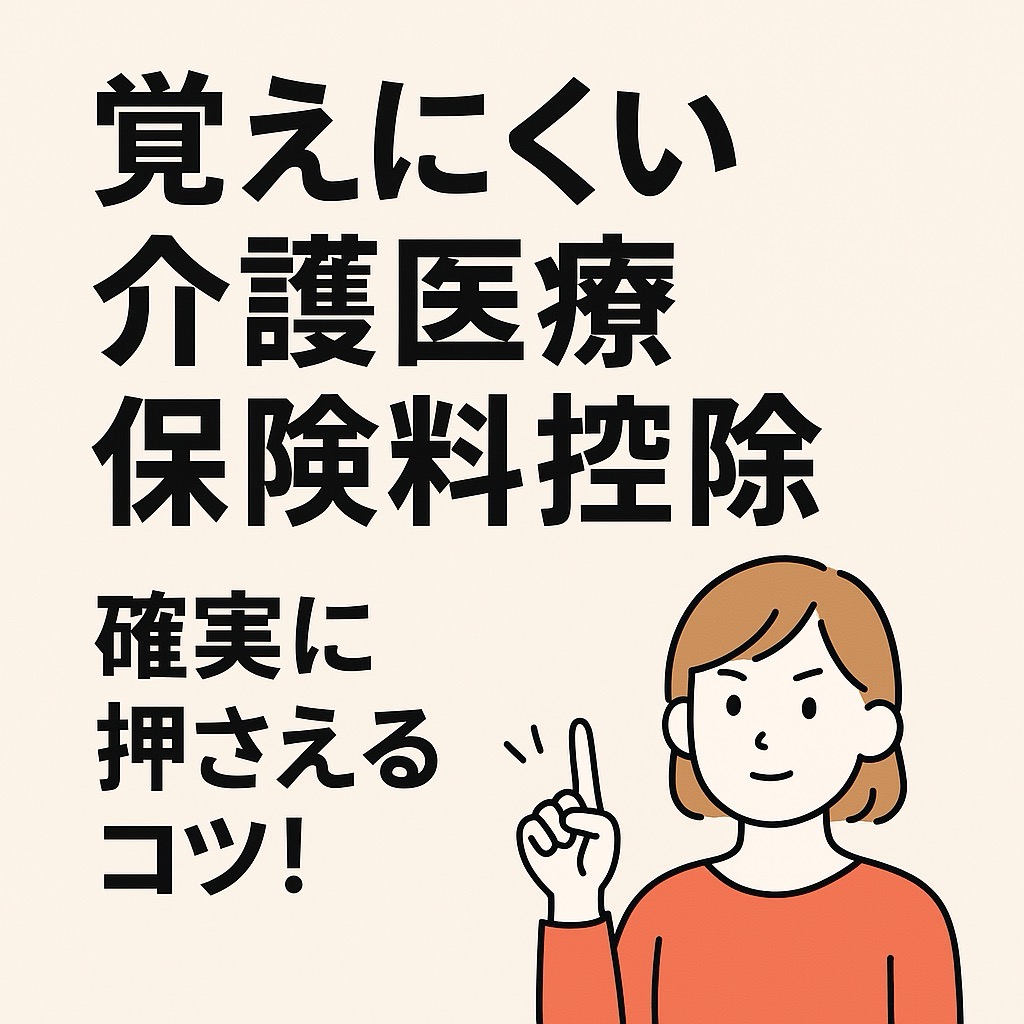

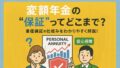

コメント