「地震保険料って、確定申告や年末調整で控除できるんですよね?」
そんな声をよく聞きますが、正しい控除額の計算方法、把握できていますか?
FP3級試験でも出題されやすい「地震保険料控除」は、◯✕問題でよく狙われます。
今回はこのテーマに沿って、仕組みと注意点をわかりやすく解説します!

こんにちは。こいちろです。
今回も一緒に新しい・正しい知識を身につけましょう
この記事は、現状に物足りなさを感じている筆者が、興味のある新たな知識をとりいれるためのブログです‼️
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 所得税における地震保険料控除は5万円が限度額‼️
- 所得税だけではなく、住民税の控除もある‼️
- 所得税と住民税の控除は、申告(年末調整or確定申告)することで両方に適用される。
📘 今回の分野:リスク管理(損害保険と税金)/地震保険料控除
今回学ぶ範囲は、リスク管理(損害保険と税金)/地震保険料控除です。
1年間に支払った地震保険料をその年の所得税から差し引くことができます。
所得税だけでなく、住民税からの控除もあるので、その使い分けをしっかり把握していきましょう‼️

❓️問題文の紹介
所得税において、個人が支払う地震保険の保険料は、5万円を限度として、年間支払保険料の2分の1相当額が地震保険料控除の対象となる。
◯か✗か?

◯と解答しました。
なんとなくですが、ほんとに全額控除になるかな〜?
という疑問があったので、半分にしてみました。
注目すべき点は、やはり1/2かどうかだと思います。
「5万円」という金額が正しいかどうかという点も疑いましょう。
それでは正解を確認しましょう。
✅️正解と解説の要点
所得税において、個人が支払う地震保険の保険料は、5万円を限度として、年間支払保険料の2分の1相当額が地震保険料控除の対象となる。
◯か✗か? →正解:✘
✅️ポイント解説
地震保険料控除の制度は以下の通りです。
- 控除額は「支払った保険料の全額(上限:5万円)」
- 所得税の控除における計算式に「2分の1」は使いません
つまり、「2分の1相当額」という記載は誤りです。
深掘り考察!!
今回の考察は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 所得税における地震保険料控除は5万円が限度額‼️
- 所得税だけではなく、住民税の控除もある‼️
- 所得税と住民税の控除は、申告(年末調整or確定申告)することで両方に適用される。
所得税における地震保険料控除は5万円が限度額‼️

【現在の地震保険料控除はシンプルに“全額控除(上限5万円)”】です。
たとえば、保険料を年間3万円支払った場合、そのまま3万円が所得控除の対象になります。
🔍 限度額がある理由とは? → 過度な節税を防ぐため
所得税の控除制度は、税負担を軽減する仕組みですが、無制限に控除できてしまうと不公平になります。
たとえば、収入の多い人が高額な保険に加入し、保険料を丸ごと控除できたら、
所得税を大きく減らせてしまいます。
これでは所得の少ない人との税負担のバランスが崩れることになります。
👉 そこで「控除できるのは最大5万円まで」という上限を設け、節税効果に公平性を持たせているのです。
所得税だけではなく、住民税の控除もある‼️

問題文中には、「所得税において」という前置きがあります。
これを「住民税において」と置き換えると正しい問題文になることになります。
以下に所得税と住民税の場合についてまとめたので、ご参考ください。
| 税区分 | 控除額の計算方法 | 控除限度額 |
|---|---|---|
| 所得税 | 支払った地震保険料の全額(※一部例外あり) | 5万円まで |
| 住民税 | 支払った地震保険料の2分の1相当額 | 2.5万円まで |
🔍 たとえば年間の地震保険料が 3万円 の場合:
- 所得税の控除対象額 → 3万円
- 住民税の控除対象額 → 3万円 × 1/2 = 1万5,000円
「所得税」と「住民税」の補足
地震保険料控除の説明では、「所得税」と「住民税」で計算方法と上限額が異なることを正しく整理しておく必要があります。

試験問題では、「どちらの税の話か?」を見落とさないように注意が必要です。
所得税と住民税の控除は、申告(年末調整or確定申告)することで両方に適用される。
🔍 そもそも「控除」ってなに?
税金の世界で「控除」というのは、収入の一部を“税金の計算から差し引く”しくみのことです。
控除があると、最終的に払う税金が少なくなるというメリットがあります。
🔸 所得税と住民税は“別々”の税金
ここがポイントです。
- 所得税:国に納める税金(国税)
- 住民税:住んでいる市区町村に納める税金(地方税)

つまり、それぞれ別々に計算され、別々に控除があるんです。
✅ 地震保険料控除は、両方にある!
あなたが1年間で支払った地震保険料に対して、以下のように控除されます:
| 税の種類 | 控除の計算方法 | 控除の上限額 |
|---|---|---|
| 所得税 | 支払った保険料の全額 | 最大5万円 |
| 住民税 | 支払った保険料の1/2(50%) | 最大2.5万円 |
🔍 例でイメージしよう
たとえば、あなたが年間で 地震保険料を3万円 支払ったとします。
- 所得税:3万円 全額が控除対象になります。
- 住民税:3万円 × 1/2 = 1万5,000円が控除されます。
つまり、合計4万5,000円分が税金の計算から差し引かれることになります。
💡 大事なポイント
- 控除を「2回申請する」わけではありません。
→ 年末調整や確定申告で1回だけ申告すれば、両方に適用されます。 - でも、申告しないと住民税も控除されないので注意が必要です。
まとめ・今回の学び
- 地震保険料控除は、所得税にも住民税にも適用される。
- 「2分の1相当額」という表現は所得税ではなく、住民税の場合の話。
それぞれに計算方法と限度額がある(全額or1/2、上限5万or2.5万) - 所得税と住民税の控除は、申告(年末調整or確定申告)することで両方に適用される。
年末調整や確定申告で1回申請すればOK!
次回予告:消費者物価指数とは何だ?
物価の動きを数値でとらえる「消費者物価指数(CPI)」は、私たちの暮らしに密接に関係しています。
でもその中身までしっかり説明できる人は案外少ないのでは?
家計に関係する「モノやサービス」の価格がどのように集計され、どこが発表しているのか…?
次回から金融資産運用の単元に入ります。
新たな知識を得られると思うとワクワクしますよね?☺️

次回も、わかりやすく、丁寧に解説していきます!
お楽しみに‼️
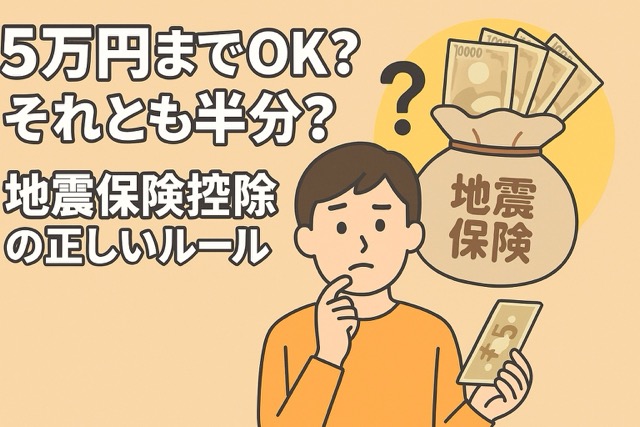



コメント