外貨預金は、為替の動きによって利益が出ることがあります。たとえば、ドル安のときに米ドルで預けて、ドル高のときに円に戻せば、その差額が「利益」になりますよね。
でもちょっと待ってください。その利益、税金がかかることをご存じですか?
今回は、FP3級でもよく出題される「為替差益と所得税の関係」に関する問題を取り上げ、分かりやすく解説していきます!
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 為替差益ってどういうもの?
- なんで雑所得になるの?
- 「為替予約あり」だと何が違う?
📘 今回の分野:金融資産運用/外貨建て金融商品
今回学ぶ範囲は、金融資産運用の外貨建て金融商品についてです。
特に「雑所得」や「一時所得」といった課税区分は、FP試験でもよく問われるポイントです。

外貨預金の扱いはややこしいため、しっかり押さえておきたいところですね。
❓️ 問題文の紹介
所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、□□□として総合課税の対象となる。
□□□に入る語句はなにか?
どのような所得の扱いになるのか?
ということが問われました。

所得が異なることで、どのような違いがあるのかを理解していませんでした。
✅ 正解と解説の要点
所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、□□□として総合課税の対象となる。
□□□に入る語句はなにか? → 正解:雑所得
正解は雑所得 とのことです。
所得の違いで何が異なるのか、しっかりと理解して正解したいと思います。

今回は間違ってしまったので、一緒に復習しましょう‼️
✅️ポイント解説
- 「為替予約を締結していない」という条件がポイントです。
これはつまり、「為替レートの変動によって利益が出た」状態を意味します。 - このときの為替差益(もうけ)は、所得税上「雑所得」として扱われ、給与や年金など他の所得と合算して総合課税されます。
- よく似たケースとして、外貨MMFやFXなどもありますが、課税方法は異なるので注意が必要です。
🔍 深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 為替差益ってどういうもの?
- なんで雑所得になるの?
- 「為替予約あり」だと何が違う?
為替差益ってどういうもの?
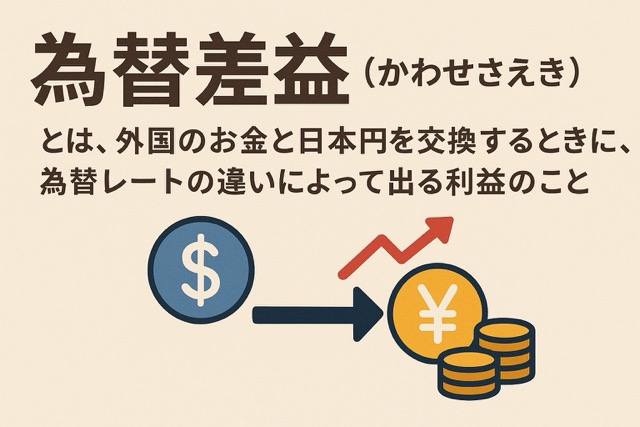
「為替差益(かわせさえき)」とは、外国のお金と日本円を交換するときに、為替レート(かわせの値段)の違いによって出る利益のことです。
🔁 具体的なイメージで説明します!
たとえば、あなたが1ドル=100円のときに、1,000ドルの外貨預金を始めたとしましょう。
このとき、使った日本円は:
100円 × 1,000ドル = 100,000円
数ヶ月後、1ドル=110円になりました。
そのときに1,000ドルを日本円に戻すとどうなるでしょうか?
110円 × 1,000ドル = 110,000円
なんと、最初より10,000円増えているんです!
✅ この10,000円が「為替差益」!
つまりこういうことです:
- 円が安くなる(=円安)と、外貨を円に戻したときに利益が出やすい。
- 外貨を買ったときより高いレートで円に戻すと、その差額が利益になります。
✋ 逆に損することも?
もちろんあります。
たとえば、1ドル=100円で買ったドルを、1ドル=90円で戻すと…
90円 × 1,000ドル = 90,000円(←1万円の損)
このように、為替差益の逆は「為替差損(かわせさそん)」といいます。
為替差益_まとめ
- 為替差益=為替レートの変動で生まれるもうけ
- 外貨を買って、レートが有利なときに円に戻すと差益が出ます。
- お金をふやせるチャンスもあるけど、損をするリスクもあります。
- 税金の扱いも変わるので、FPの勉強ではとても大事なポイント!
なんで雑所得になるの?
💡 まず「雑所得」ってなに?
税金の世界では、お金をもらったり利益が出たりしたら、その内容に応じて「何の所得か?」が決まります。
主なものはこんな感じです:
| 所得の種類 | 例 |
|---|---|
| 給与所得 | お給料 |
| 事業所得 | 自営業のもうけ |
| 不動産所得 | 家賃収入 |
| 配当所得 | 株でもらう配当 |
| 譲渡所得 | 株や不動産を売って得た利益 |
| 一時所得 | 宝くじの当選、保険の解約金など |
| 雑所得 | 上に当てはまらないいろんな利益 |
🤔 じゃあ、為替差益はどこに当てはまるの?
外貨預金で得た為替差益って、
- 自分の労働で得たお金ではない(給与所得ではない)
- 商売でもらったお金でもない(事業所得ではない)
- 株の配当や売却でもない(配当・譲渡所得ではない)
- 宝くじや保険金でもない(一時所得でもない)

つまり、他のどの所得にも当てはまらないんです。
✅ だから「雑所得」になる!
税法では、「どこにも分類されない利益は“雑所得”にしてね」と決まっているので、
外貨預金で出た為替差益は「雑所得」として扱われるのです。
🧾 雑所得になるとどうなるの?
- 総合課税になります
→ 他の所得(給与や年金など)と合計して税率が決まります。 - 人によって税率が変わります。(5%〜最大45%)
🧠 補足:他にも雑所得になるもの
- 公的年金(厚生年金、国民年金など)
- FXで得た利益(※申告分離課税という別ルール)
- ポイントサイトや副業の収入(場合によって)
✅ 雑所得とは_まとめ
- 為替差益は、他の所得に分類できないため「雑所得」になります。
- 雑所得は、総合課税の対象となり、他の所得と合わせて税率が決まります。
- FP試験では、「外貨預金の為替差益=雑所得」と覚えるのが鉄則!
「為替予約あり」だと何が違うの?
為替予約(あらかじめレートを固定する契約)をしていた場合は、利益が確定しているため
一時所得として扱われる可能性があります。
ただし、FP3級の検定試験では、そこまで細かく問われないため、
「予約なし=雑所得」と覚えておけばOKです。
まとめ・今回の学び
- 為替差益=為替レートの変動で生まれるもうけ
- 外貨を買って、レートが有利なときに円に戻すと差益が出ます。
- 為替差益は、他の所得に分類できないため「雑所得」になります。
- 雑所得は、総合課税の対象となり、他の所得と合わせて税率が決まります。
- FP試験では、「外貨預金の為替差益=雑所得」と覚えるのが鉄則!
- 為替予約をしていた場合は、 一時所得として扱われる可能性があります。
今回も一つの問題文にいろいろな情報が詰まっていました。
問題文を分解して、用語ごとに調べることで理解が深まったと思います。
次回も新たな発見をして、自分の知識を深めていきましょう。
次回予告:新NISAで国債や社債は買えるの?
新NISAがスタートして、「つみたて投資枠で何が買えるのか?」が注目されています。
でも、ふとこんな疑問がわきませんか?
「国債」や「社債」って、安定してそうだし長期投資に良さそう…でも、NISAの対象商品じゃないの?
実はこのテーマ、FP3級の試験にも出題される重要ポイントなんです。

次回は「つみたて投資枠」と「投資対象商品の条件」について、やさしく深掘り解説していきます☺️
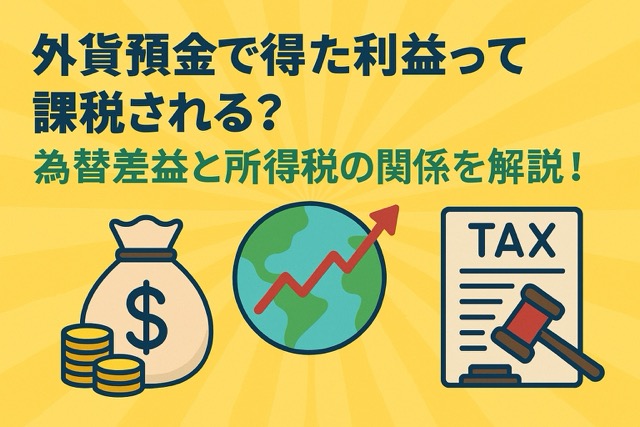


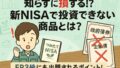
コメント