 FP
FP 【不動産投資】投資総額1億円で利回りは何%?純利回り(NOI利回り)の計算を徹底解説!_間違いから学ぶFP3級_第70回
不動産投資を学ぶときに必ず出てくるのが「利回り」という言葉です。利回りは投資の成果を測る大切な指標であり、数字をどう計算するかによって意味が変わります。今回は「純利回り(NOI利回り)」について、実際の問題を通して考えていきましょう。
 FP
FP 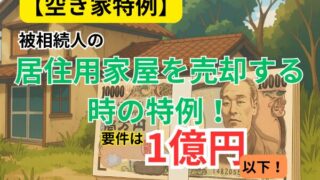 FP
FP 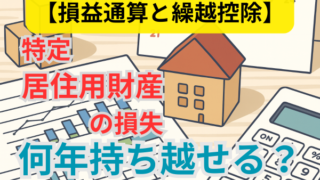 FP
FP  FP
FP 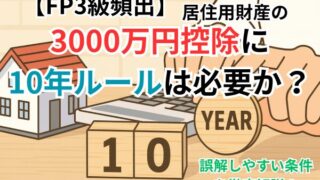 FP
FP  FP
FP  FP
FP 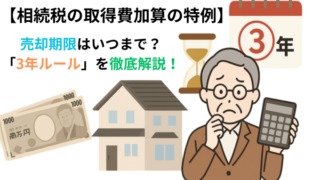 FP
FP 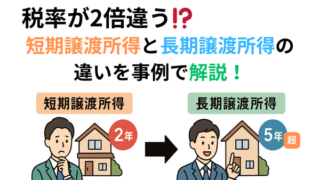 FP
FP 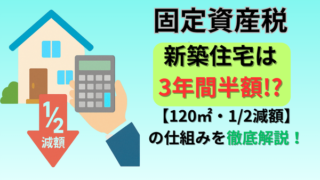 FP
FP