 FP
FP 【譲渡所得】居住用財産の3,000万円特別控除!期限を過ぎるとどうなる?_間違いから学ぶFP3級_第64回
マイホームを売却するとき、一定の条件を満たせば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」という大きな節税メリットを受けられます。ただし、この特例には「いつまでに売るか」という期限が決まっています。
 FP
FP 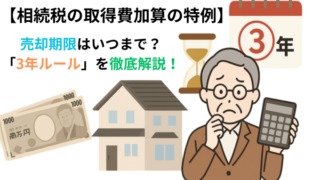 FP
FP 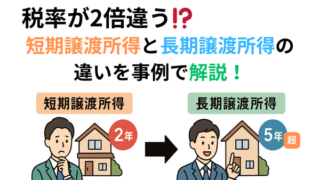 FP
FP 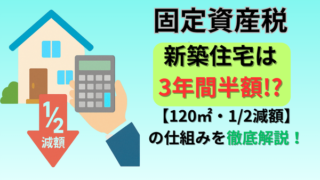 FP
FP 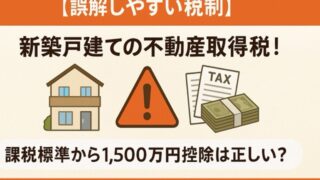 FP
FP  FP
FP 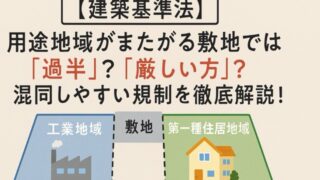 FP
FP  FP
FP 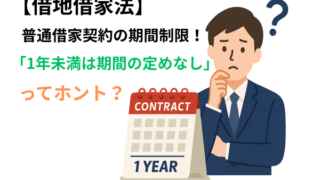 FP
FP 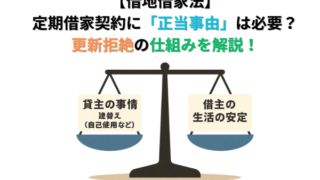 FP
FP