住宅を新築すると、毎年かかる「固定資産税」が気になる方も多いのではないでしょうか。
実は、一定の条件を満たす住宅については「固定資産税の減額措置」を受けられることがあります。
今回は、認定長期優良住宅ではない2階建て新築住宅のケースを題材に、減額の内容を整理していきます。
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 固定資産税とはなにか?
→土地や建物、償却資産(事業用の機械や設備など)を持っている人に毎年かかる地方税のことです。 - 新築住宅の税額の減額措置とは?
→新しく住宅を建てた場合、最初の数年間は固定資産税が2分の1に軽減される制度です。 - 新築住宅の税額の減額措置ができた背景
→主に「家計の初期負担軽減」と「住宅取得の促進」を目的に始まりました。
📘 今回の分野:新築住宅の特例_固定資産税

今回のテーマは、新築住宅の特例における 「固定資産税(地方税法)」 です。
住宅の新築時に適用される減額措置は、FP試験でもよく問われる重要ポイントです。
❓️ 問題文の紹介
認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、『新築された住宅に対する固定資産税の減額』の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積【□1】m²までの部分に相当する税額が【■2】に減額される。
【□1、■2】に入る数値はいくらか?
今回の問題文の選択肢は、
【□1_50 or 100 or 120、■2_1/4 or 1/3 or 1/2】です。
私が選択したのは、□1_50、■2_1/4でした。
このとき、この問題で覚えていたのは、減額措置の要件のである50㎡以上280㎡以下でした。
50㎡という数値に引っ張られて、選択肢を選んだことで間違えてしまいました。

しっかりと正しい知識を身につけておきたいですよね。
正解を確認していきましょう‼️
✅ 正解と解説の要点

認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、『新築された住宅に対する固定資産税の減額』の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積【□1】m²までの部分に相当する税額が【■2】に減額される。
【□1、■2】に入る数値はいくらか?
正解_【□1:120㎡、■2:2分の1】
正解は、□1が120㎡、■2が2分の1でした。
床面積が120㎡までの固定資産税が半分になると覚えておきましょう。

私が誤答した選択肢では固定資産税が1/4なるので、恩恵が大きすぎるかもしれませんね。
そういった点で違和感を感じていければ、正解肢に辿り着きやすくなるかもしれません。
ポイントを見ていきましょう‼️
✅️ポイント解説
新築住宅に対しては、一定期間「固定資産税が半分になる」という優遇措置があります。
- 通常の住宅:新築から3年間、120㎡までの部分が 2分の1 に減額
- なお、認定長期優良住宅の場合は特例で5年間の減額が受けられます。
🔍 深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 固定資産税とはなにか?
→土地や建物、償却資産(事業用の機械や設備など)を持っている人に毎年かかる地方税のことです。 - 新築住宅の税額の減額措置とは?
→新しく住宅を建てた場合、最初の数年間は固定資産税が2分の1に軽減される制度です。 - 新築住宅の税額の減額措置ができた背景
→主に「家計の初期負担軽減」と「住宅取得の促進」を目的に始まりました。
固定資産税とはなにか?

固定資産税とは、土地や建物、償却資産(事業用の機械や設備など)を持っている人に毎年かかる地方税のことです。
納税義務者は、1月1日の時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている者です。
- 税金の使い道 → 市町村や都道府県の収入となり、道路整備、消防、学校など地域の公共サービスに使われます。
- 課税する主体 → 原則として 市町村(東京23区は都が課税)です。
具体例で理解しよう
例1:自宅の固定資産税
- Aさんは、土地(100㎡)と新築の住宅を所有しています。
- 市が評価した 固定資産税評価額が合計1,500万円だったとします。
- 固定資産税の税率は原則 1.4%。
計算式:
1,500万円 × 1.4% = 21万円

Aさんは、この年に 21万円の固定資産税を支払うことになります。
例2:土地だけ持っている場合
- Bさんは、駐車場用に土地(200㎡)だけを所有しています。
- 評価額が2,000万円の場合、
2,000万円 × 1.4% = 28万円
→ 建物がなくても、土地を所有しているだけで固定資産税がかかります。
例3:事業用の資産
- Cさんは、工場を経営していて機械設備を持っています。
- 機械の評価額が1,000万円なら、
1,000万円 × 1.4% = 14万円

事業用の機械設備にも固定資産税がかかります。これを「償却資産税」と呼ぶ場合もあります。
ポイントまとめ
- 固定資産税は 土地・建物・償却資産を持っている人が毎年支払う地方税です。
- 計算は「固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)」で行われます。
- 評価額は市場価格より低めに設定されます。(だいたい7割程度)
- 優遇措置があります。(住宅用地の軽減や新築住宅の減額など)
固定資産税を深掘り!
- なぜ市場価格より低い評価額?
→ 税負担を一定にするためです。もし市場価格でそのまま課税したら、地価が急上昇した年に大きく税金が増えてしまい、生活に大きな影響が出ます。 - なぜ住宅用地に軽減措置?
→ 住宅取得を支援して国民生活を安定させる狙いがあります。

こう考えると、固定資産税は「資産を持っていることへの負担」であり、持ち家や土地を持っている人が毎年必ず直面する税金だとわかります。
新築住宅の税額の減額措置とは?

新しく住宅を建てた場合、最初の数年間は固定資産税が2分の1に軽減される制度です。
- 減額されるのは「建物」にかかる税金部分(※土地ではない)。
- 減額される床面積には上限があります。(120㎡まで)
- 減額される期間は住宅の種類によって違います。
減額の内容
- 一般の新築住宅
- 対象床面積:50㎡以上280㎡以下
- 減額対象部分:120㎡まで
- 減額率:2分の1
- 期間:3年間(2階建て以下の一般住宅)
- 対象床面積:50㎡以上280㎡以下
- 認定長期優良住宅(省エネ・耐久性に優れた住宅)
- 同じ条件で
- 期間が 5年間 に延長される
- 同じ条件で
具体例で理解しよう
例1:一般の新築住宅(2階建て・床面積100㎡)
- 固定資産税評価額:1,200万円
- 通常の固定資産税:1,200万円 × 1.4% = 16万8千円
- 減額措置(全床面積が120㎡以下なので全額対象):
→ 16万8千円 × 1/2 = 8万4千円

最初の3年間は 毎年8万4千円の節税です。
例2:大きな住宅(床面積150㎡)
- 固定資産税評価額:2,000万円
- 通常の固定資産税:2,000万円 × 1.4% = 28万円
- 減額対象:120㎡分のみ → 150㎡のうち120/150 = 0.8(8割)
28万円 × 0.8 = 22万4千円 - 減額後:22万4千円 × 1/2 + 5万6千円(減額対象外部分)
= 16万8千円
→ 節税額は 11万2千円/年 × 3年間 = 33万6千円。
新築住宅の減税措置_ポイントまとめ
- 新築住宅の固定資産税は 120㎡まで2分の1に減額されます。
- 期間は 一般住宅で3年、長期優良住宅で5年です。
- 節税額は数十万円にもなるので、住宅取得者にとって大きなメリットがあります。
新築住宅の減税措置を深掘り!

- なぜ「3年間」だけ?
→ 新築後の住宅ローン返済など、家計負担が大きい初期を支援するためです。 - なぜ「120㎡まで」?
→ 大豪邸まで一律に優遇すると不公平になるので、一般的な戸建住宅を想定した120㎡が上限になります。 - なぜ「長期優良住宅は5年」?
→ 省エネ・耐久性のある住宅を普及させる政策的な狙いです。
新築住宅の税額の減額措置ができた背景
背景① 住宅取得直後の家計負担の軽減

- 新築住宅を取得すると、多くの家庭で 住宅ローンの返済が始まります。
- 家計にとって最も負担が大きいのが 新築から最初の数年間。
- この時期にさらに固定資産税がそのままかかると、家計が圧迫されやすい。

そこで「新築後3年間は税金を半分にしよう」という仕組みが設けられました。
背景② 住宅取得の促進(景気対策)
- 日本はかつて「住宅不足」の時代がありました。
- 持ち家を持つことは生活の安定につながるため、国は住宅取得を後押しする政策をとってきました。
- 固定資産税の減額は「家を建てやすくする誘導策」として設けられたのです。
背景③ 公平性の確保
- 減額には「120㎡まで」という制限があります。
- これは「一般的な戸建住宅」の規模を想定した数字です。
- 大きな豪邸まで無制限に減税すると不公平になるため、上限を設けて「誰もが恩恵を受けられる」仕組みにしています。
背景④ 長期優良住宅の普及政策

- 後に制度が拡充されて、長期優良住宅(省エネ・耐久性が高い住宅)なら5年間の減額が導入されました。
- これは少子高齢化や地球環境問題を踏まえ、長く住める住宅・エコ住宅を広めるための政策的な工夫です。
背景_まとめ
- 減額措置は「家計の初期負担軽減」と「住宅取得の促進」を目的に始まりました。
- 120㎡上限は「公平性」のためです。
- 長期優良住宅への優遇は「省エネ・長寿命住宅の普及促進」が背景となります。
つまり、単なる「減税」ではなく、
👉 暮らしを支える+住宅政策を推進する+環境問題に対応する
という複数の狙いが重なっているのです。
続いて、昭和から平成にかけての住宅政策の流れについてもまとめておきます。
① 昭和時代:住宅不足と持ち家推進

- 戦後、日本は深刻な住宅不足に直面しました。
- 国の大きな政策目標は「国民に安定した住まいを供給すること」。
- 公営住宅や持ち家支援制度が拡充され、住宅を取得しやすくする政策が次々に導入。
→ この流れの中で「税制優遇」によって住宅取得を後押しする仕組みも考えられました。
② 平成時代:家計負担軽減のための減額措置

- 新築時は住宅ローン返済が始まり、家計の負担が大きくなることが予想されます。
- そこで「固定資産税を一定期間半額にする」制度が設けられ、
→ 最初の3年間(長期優良住宅なら5年)は税負担を軽減。 - これにより「新築後すぐの暮らしの安定」を支援しました。
③ 公平性の確保
- 減額は 床面積120㎡まで が対象です。
- 一般的な戸建住宅を想定し、豪邸まで無制限に優遇すると不公平になるため。

「誰にとっても恩恵があるが、贅沢住宅は対象外」というバランスを取っています。
④ 平成後期〜令和:環境・長寿命住宅政策へ
- 少子高齢化や環境問題に対応するため、長期優良住宅により手厚い優遇を追加されました。
- 「長く住める」「省エネ性能が高い」住宅の普及を後押し。
→ 単なる税の軽減ではなく、国の住宅政策と環境政策の一体的な取り組みへ。
時系列_まとめ
新築住宅の固定資産税減額措置は、
👉 戦後の住宅不足解消 → 家計支援 → 公平性の確保 → 環境配慮型住宅の普及
という歴史的な流れの中で生まれた制度です。
まとめ・今回の学び
- 固定資産税とはなにか?
→土地や建物、償却資産(事業用の機械や設備など)を持っている人に毎年かかる地方税のことです。
→計算式は、固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)優遇措置ありです。 - 新築住宅の税額の減額措置とは?
→新しく住宅を建てた場合、最初の数年間は固定資産税が2分の1に軽減される制度です。
→期間は 一般住宅で3年、長期優良住宅で5年。120㎡まで適用されます。 - 新築住宅の税額の減額措置ができた背景
→主に「家計の初期負担軽減」と「住宅取得の促進」を目的に始まりました。
_戦後の住宅不足解消 → 家計支援 → 公平性の確保 → 環境配慮型住宅の普及という歴史的な流れがあります。
今回は新築住宅の特例として、固定資産税についてまとめました。
このあたりは参考書を読むといろいろな数値が出てくるので、意図や背景も理解しておくと混乱しないと思います。
しっかりと知識が定着するまで、見に来てください😁
次回予告:譲渡所得の所有期間と税率

次回は、不動産売却に関する「譲渡所得の区分」について取り上げます。
問題文はこちらです。
問題文
「土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。◯か✗か?」
所有期間によって「短期」か「長期」かに分かれる仕組みですが、基準となる年数をしっかり押さえていないと迷いやすいポイントです。

次回は、この区分の考え方と覚え方を整理していきます!
お楽しみに‼️


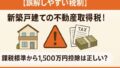

コメント